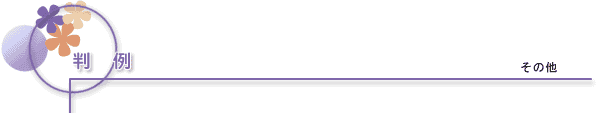 |
|
扶養
2019.6.21
父(相手方)・母(C)が和解離婚した後、未成熟子(申立人)が、成年に達した後に国外の大学に進学した場合において、和解離婚当時、申立人が国外の大学に進学することが相手方にとって想定外の出来事であること、申立人が国外の大学に進学すると最終的に決めたのが成人に達した後であってその判断による責任は申立人自身が負うべきであること、申立人はCの支援を前提に留学を考えていたこと、相手方は開業医として一定の収入があったが体調が芳しくないことなどから、申立人の申立てを却下した事例
[岡山家裁2019(令和元)年6月21日審判 家庭の法と裁判33号111頁]
[審判の概要]
本件において、申立人が進学したのは、成人に達した後のことであり、進学先も国外の大学である。
国外の大学に進学することは一般的とはいい難く、国内の大学進学に比べて国外の大学に留学する費用が高額になる傾向があることは明らかであり、国外の大学に進学する必要性は、国内の四年制大学に進学することと比べて小さい。
また、相手方は、Cとの離婚の際、Cから、申立人が国内の私立大学に進学する旨聞かされており、申立人自身も当初は国内の大学進学を考えていたことが認められる。
和解離婚の際、「申立人が大学等在学中に留学を希望する場合、相手方がその費用を負担する」とされているが、相手方は、申立人が、国内の大学に進学した上で一時的な留学をすることは想定していたと考えられるものの、国外の大学に進学することを想定していたとは認められない。また、「申立人が○年○月末日時点で大学等に在籍しているときは」とされているように、相手方は、申立人が成人に達した後の教育の費用を負担する意思があったとは認められない。
その後、申立人やCが、相手方に対し、申立人が国外の大学への進学を検討していることやその費用負担について事前に相談したという形跡はなく、相手方が申立人の国外の大学への進学を認め、又は想定していたことを認めるに足りる資料はない。
加えて、申立人が留学することを最終的に決めたのは、成人に達した後であって、その判断による責任は申立人自身が負うべきものである。
そして、申立人は、Cからの支援を前提に留学したと考えられ、仮に、Cからの支援を受けることが困難な状況にあったとしても、それは申立人の判断の結果であり、自身で甘受すべき結果である。
これらの事情に加え、相手方は開業医を続けており、現在も一定の収入を得ているが、その体調が芳しくないことも併せ考えると、相手方に申立人の国外の大学に進学する費用を負担すべき義務を負わせるのは相当でないというべきである。
2014.7.2
子が母に支払うべき扶養料の増額が認められた事例
[札幌高裁2014(平成26)年7月2日決定 判タ1417号127頁]
[事実の概要]
抗告人(母、1944年生、約70歳)は、被抗告人(子、医師)に対し、扶養料の支払を求める審判を申し立てた。母は、生活費(月額)は27万6700円が必要であると主張し、生活費から国民年金及び厚生年金の支給合計額7万6725円(月額)を差し引いた19万9975円を扶養料として毎月支払うよう求めた。子は、母の生活費(月額)は16万1700円が妥当、扶養料は月額8万4975円とすべきと主張した。
原審は、母の生活費として必要な額を月額16万5700円とし、月額9万円の扶養料の支払い子に命じた。抗告人(母)はこれを不服として即時抗告をした。
[決定の概要]
「被抗告人は抗告人に対し扶養義務(民法877条1項)を負うが、それは、生活扶助義務であるから、被抗告人らの社会的地位、収入等相応の生活をした上で余力を生じた限度で分担すれば足りるものであることを考慮して、扶養料の額は、抗告人の必要とする自己の平均的生活を維持するために必要である最低生活費から抗告人の収入を差し引いた額を超えず、かつ、被抗告人の扶養余力の範囲内の金額とするのが相当である。・・・抗告人は、昭和19年・・生まれの女性であるところ、総務省統計局の家計調査報告(平成25年)によれば、単身世帯の65歳以上女性の消費支出(月額)は、国民健康保険税1万5500円、住民税6000円、介護保険料9000円、医療・傷害保険8000円の計3万8500円であり、上記消費支出と非消費支出の合計は18万7897円となる。・・以上によれば、抗告人の平均的な生活を維持するために必要とする最低生活費は、月額18万7897円であるとするのが相当である。
そうすると、上記最低生活費から抗告人の年金収入を差し引いた額は月額11万1172円であるが(計算式187,897−76,725=111,172)、被抗告人の家計支出の内容等の一切の事情を考慮して、被抗告人の抗告人に対する扶養料は、月額11万円とするのが相当である。」
[ひとこと]
親に対する扶養料については、養育費や婚姻費用と異なり、簡易算定表や標準算定方式はなく、さまざまな計算方式があるが、本件はその一例である。審判例の公表は珍しい。
|
 |
 |
|
|



