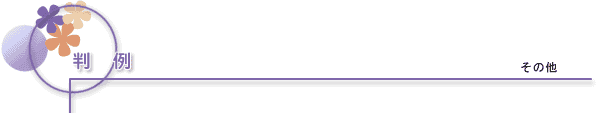 |
|
相続
2021.7.26 New!
被相続人の弟が被相続人の子らに対して特別寄与料の支払を求めた事案において、特別寄与料を認めるのが相当なほどに顕著な貢献をしたとまでは言えず、また、民法1050条2項ただし書の期間は除斥期間であるとしたうえで、「相続人を知った時」とは当該相続人に対する特別寄与料の処分の請求が可能な程度に相続人を知った時を意味するものが相当として申立てを却下した例
[静岡家裁2021(令和3)年7月26日審判 家庭の法と裁判37号81頁]
[事実の概要]
被相続人の弟(申立人)が、被相続人の子ら(相手方ら)に対して、自身の被相続人への療養看護等により同人の財産の維持増加に特別の寄与をしたとして、民法1050条1項に基づき、それぞれ特別寄与料の支払いを求めた。相手方らは、特別の寄与の有無について争った。また、本件各申立てが「相続の開始及び相続人を知った時から六箇月」(民法1050条2項ただし書)を経過した後になされたものであるとして却下を求めた。
[決定の概要]
申立人の関与は、「月に数回程度入院先等を訪れて診察や入退院に立ち会ったり、手続に必要な書類を作成したり、身元引受をしたりといった程度にとどまり、専従的な療養看護等を行ったものではなく、これをもっても、申立人が、その者の貢献に報いて特別寄与料を認めるのが相当なほどに顕著な貢献をしたとまではいえない。」「申立人による『特別の寄与』(民法1050条1項)の存在を認めることは困難である。」
民法1050条2項ただし書は除斥期間を定めたものであり、同条がその起算点を「相続の開始」を「知った時」のみでなく「相続人を知った時」にもかからしめた趣旨から考えると、「同項にいう『相続人を知った時』とは、当該相続人に対する特別寄与料の処分の請求が可能な程度に相続人を知った時を意味するものと解するのが相当である。」「申立人は、相続人の氏名及び住所を正確に知った時を意味すると解すべきである旨主張するが、以上のとおりであるから、採用できない。」本件においては、申立時点において「申立人が『相続の開始及び相続人を知った時』から6か月の除斥期間を経過していることが明らかである。」
2021.1.18
遺言成立日と異なる日付が記載された自筆証書遺言について、日付が相違していることをもって直ちに無効とするのではなくその余の無効事由について審理すべきとして差し戻した事例
[最高裁2012(令和3)年1月18日判決 家庭の法と裁判34号42頁]
[事実の概要]
本件遺言者は、平成27年4月13日に入院先の病院において、本件遺言の全文、日付(平成27年4月13日)、署名を自書した本件遺言書を作成した。そして退院して9日後(本件遺言の日から27日後)である平成27年5月10日に、本件遺言書に押印した。
原審での争点は遺言の無効確認のほかにも複数あるが、本最高裁判決では、本件遺言書には遺言の成立日(押印日、平成27年5月10日)と異なる日付(平成27年4月13日)が記載されていることから方式の不備により無効であると判断した控訴審判決(原審も同じ)の判断についてのみ判断しており、日付の相違のみならずその余の無効事由についても更に審理を尽くすべき、として差し戻した。
[決定の概要]
自筆証書によって遺言をするには、真実遺言が成立した日の日付を記載しなければならず、本件においての日付は、押印がなされて遺言が完成した平成27年5月10日というべきである。原審は、本件遺言にはこれと相違する平成27年4月13日の日付の記載があること、そしてこれが誤記等とも解されないことを理由としてその余の事情をほとんど考慮することなく本件遺言を無効と判断している。
しかし、民法968条1項が自筆遺言の方式として、厳格な遺言の方式を要するとした趣旨は、遺言者の真意を確保すること等にあるところ、必要以上の遺言の方式を厳格に解すると、かえって遺言者の真意の実現を阻害するおそれがある。
本件においては、入院中に本件遺言書の全文、同日の日付及び氏名を自書し、退院して9日後に押印している等の事情があることから、本件遺言書の無効の判断においてはかかる事情も考慮すべきである。
2020.6.26
被相続人のいとこ2名が申し立てた特別縁故者に対する相続財産分与の申立てについて、申立人2名を民法958条の3第1項の「その他被相続人と特別の縁故があった者」に該当すると認めつつ、縁故の内容・程度等の事情を勘案し、分与の額については、預金残高の1割程度に相当する金銭の一部分与を認めた例
[東京家審2020(令和2)年6月26日 家庭と法の裁判31号100頁]
[審判の概要]
「申立人両名が、いずれも民法958条の3第1項所定の『被相続人と生計を同じくしていた者』及び『被相続人の療養看護に努めた者』のいずれにも該当しないことは明らかである。」「そこで、申立人両名が、同項所定の『その他被相続人と特別の縁故があった者』に該当するか否かを検討するに、ここにいう『その他被相続人と特別の縁故があった者』とは、前述の生計同一者及び療養看護者に該当する者に準ずる程度に被相続人との間で具体的かつ現実的な交渉があり、相続財産の全部又は一部をその者に分与することが被相続人の意思に合致するであろうとみられる程度に被相続人と密接な関係があった者と解するのが相当である。」
「事実関係によれば、申立人両名は、いずれも被相続人の親族(従兄弟)に該当するところ、被相続人と申立人両名との関係は、…祖父母を起点とした親族同士における従来からの親密な交流関係の下で、従兄弟同士の親しい関係として育まれ、当該関係は、その時々の各人の生活状況等に応じて多少の濃淡はありつつも、生涯にわたり、基本的に親密なものとして継続してきたものと認められる。」
「被相続人は…年長のいとこであるAに対して親しみを込めた相応の信頼を有していたことがうかがわれる。」
「また、被相続人は、年齢の近いBとの間で親密な関係を築きつつ、Bを一定程度、個人的に頼りにする姿勢を見せていたものと認められる。」
「そして、申立人両名は、被相続人の死亡発見直後に連絡を受けて遺体の身元確認に赴いたほか、Aにおいて、遺体を引き取り、喪主として自らの費用負担で葬儀、納骨等を行った上、Aの声かけにより、申立人両名を含む親族らにおいて多大な労力をかけて被相続人の自宅内の遺品整理やごみの搬出などを行い、その際、Bにおいて、被相続人の自宅内の清掃費用等を負担するといった一連の必要ないしは有用な対応を自発的に行っていることが認められる。」
「被相続人の生前及び死後におけるこれらの事情を総合するに、…親族間全体に見られる従来からの親密な交流関係を基底としつつ、被相続人の生前における個人的な親密さや信頼感情が相応に介在していた面があることは否定できず、被相続人の死亡後における申立人両名の前述の各尽力についても、このような事情を示すものと認めるのが相当である。その意味で、被相続人と申立人両名との関係については、いずれも通常の親族としての交際の範囲にとどまるものとはいえず、当該範囲を超えて、相続財産の全部又は一部を申立人両名に分与することが被相続人の意思に合致するであろうとみられる程度に密接なものであったと認めるのが相当である。」
「ところで、…申立人両名が被相続人の財産増殖に何らかの寄与をしたとか、被相続人の心情面において強い支えとなるべき心理的援助を惜しまなかったなどといった明確かつ具体的な交渉経緯が存在するわけではない。この点において、申立人両名に分与されるべき相続財産については、相続財産全体の構成に比して、いずれも少額の割合の金銭にとどまるべきものと解するのが相当であり…以上の検討を踏まえ、申立人両名に対しては、それぞれ金5000万円を分与するのを相当と認める。」
2020.6.26
家庭裁判所が危急時遺言の確認をするにあたっては、当該遺言が遺言者の「真意に出たものであるとの心証」を得る必要があるところ(民法976条5項)、同心証の程度については、確信の程度にまで及ぶ必要はなく、当該遺言が一応遺言者の真意に適うと判断される程度のもので足りるとして、原審判を取り消し遺言を確認した事例。
[東京高決2020(令和2)年6月26日決定 家庭の法と裁判31号51頁]
[事実の概要]
遺言者は、病院で療養中であったところ、死亡の危急に迫ったので、平成30年×月19日、証人3人の立会いの上、全ての財産を長男に相続させるとの内容の遺言(本件遺言)の趣旨を口授した。遺言の証人Aが遺言確認の申立てをした。
遺言者は、同年同月8日に入院し、その後、日によって意識レベルや応答能力に変動があったが、19日には、氏名、生年月日は回答したが、どこにいるのかを答えることは出来ない状況であった。
その4日後の23日、家庭裁判所調査官が遺言者と面接したが、遺言者は、遺言書作成に至る経緯や遺言書作成当日の手続き状況、遺言内容について都度異なる回答をするほか、遺産内容も把握していないような状態であった。
原審は、遺言者が本件遺言の趣旨や効果を理解したうえで口授することができたというには疑義が残り、本件遺言は遺言者の真意に出たものとは認められないとして申立てを却下し、A及び長男が抗告した。
[決定の概要]
抗告審は、「遺言者の真意につき家庭裁判所が得るべき心証の程度については、確信の程度にまで及ぶ必要はなく、当該遺言が一応遺言者の真意に適うと判断される程度のもので足りると解するのが相当である」との一般論を示した。そのうえで、証人がいずれも、公正証書遺言の作成依頼を受けたF弁護士からの依頼に基づいて証人となった行政書士であり各供述の信用性は高いこと、遺言の際に、Aからの「誰に財産を相続させますか」との問いに、遺言者が自発的に長男の名を述べたり、遺言の内容を再確認した際にうなずくことで肯定の意思を示したりしていることなどからすれば、遺言者が本件遺言の趣旨を理解したうえでこれを口授していることがうかがわれるとした。また、本遺言の内容はF弁護士が依頼を受けた公正証書遺言の内容とも一致していること、抗告人A夫婦の手配で入院しその後同人宅に引き取られるに至った状況からみて合理性を有する内容といえること、日によって意識レベル等に変動があることからすると、23日の面談結果をもって19日における遺言者の認知機能障害の程度を示すものとみるのは相当ではないなどとして、原審判を取り消し、遺言者が本遺言をしたことを確認した。
2020.6.11
一切の財産を抗告人(長男)に相続させ、その相続の負担として原審申立人(二男)の生活を援助するものと定めた遺言について、原審申立人が抗告人からの生活の援助がなされないとして取消しを求めたところ、遺言を取り消すことが遺言者の意思にかなうものとは言えないとして遺言の取消しを認めなかった例
[仙台高決2020(令2)年6月11日 家庭の法と裁判35号127頁]
[決定の概要]
本件遺言は、遺言者の有する一切の財産を抗告人(長男)に相続させることを定め、その相続の負担として、原審申立人(二男)の生活を援助することを定めたものである。遺言者が存命中、精神疾患を患っている原審申立人に対し、最低でも月額3万円を送金してきたこと等を前提とし、原審申立人に対して少なくとも月額3万円の経済的援助をすることを抗告人に負担させるものと考えられる。
抗告人が原審申立人に対し毎月3万円の支払をしていないことは、「本件遺言に定める負担を履行していないものとはいえるが、抗告人には、負担の内容が具体的に示されればこれを完全に履行する意思もあり、本件遺言の抽象的文言からは、負担についての遺言者の意思解釈が必ずしも容易ではないことも考えると、現時点で、抗告人がその履行をしていないことについては、その責めに帰することができないやむを得ない事情があるといえる。」
「遺言者は、長年に渡り闘病生活を送ってきた原審申立人の財産管理能力に疑念を抱き、原審申立人の生活を必要に応じて援助しなければならないが、一度に多額の現金を取得するなどした場合には、浪費をするなどして困窮したり、抗告人や」遺言者の妻「に扶養料を請求したりする事態になることを回避すべく、本件遺言をしたものと推認されるものであり、そのような遺言者の意思に鑑みても、抗告人に負担の不履行があるとして、今直ちに本件遺言を取り消すことが遺言者の意思にかなうものとは認められない。」
2020.2.27
被相続人が、遺言において夫を廃除する意思を表示したとして、遺言執行者が推定相続人廃除を申し立てた事案で、廃除事由として「婚姻を継続し難い重大な事由」と同程度の非行が必要であると解すべきとし、本件ではこのような廃除事由が認められないとして、申立てを却下した事例
[大阪高裁2020(令和2)年2月27日決定 家庭と法の裁判31号58頁]
[決定の概要]
原審は、申立てを認容したが、抗告審は以下の理由により申立てを却下した。
推定相続人の廃除は、被相続人の意思によって遺留分を有する推定相続人の相続権を剥奪する制度であるから、廃除事由である被相続人に対する虐待や重大な侮辱、その他の著しい非行(民法892条)は、被相続人との人的信頼関係を破壊し、推定相続人の遺留分を否定することが相当であると評価できる程度に重大なものでなければならず、夫婦関係にある推定相続人の場合には、離婚原因である「婚姻を継続し難い重大な事由」(民法770条1項5号)と同程度の非行が必要であると解すべきである。
本件においては、被相続人は、遺言において、抗告人からの精神的、経済的虐待を受けたと主張し、具体的理由として、①離婚請求、②不当訴訟の提起、③刑事告発、④取締役の不当解任、⑤婚姻費用の不払い及び⑥被相続人の放置の各事由を挙げる。しかし、遺言時に係属中であった離婚訴訟において、被相続人は、婚姻を継続し難い重大な事由はないし、これが存在するとしても有責配偶者からの離婚請求であるか、婚姻の継続を相当と認めるべき事情がある旨主張して争ったうえ、遺言作成後に言い渡された判決においても上記事由の存在が認められないと判断された。しかも、被相続人の遺産は、抗告人とともに営んでいた事業を通じて形成されたものである。被相続人の挙げる①〜⑥の各事由は、被相続人と抗告人との夫婦関係の不和が高じたものであるが、上記事業を巡る紛争に関連して生じており、約44年に及ぶ婚姻期間のうちの5年余りの間に生じたものにすぎないのであり、被相続人の遺産形成への抗告人の寄与を考慮すれば、その遺留分を否定することが正当であると評価できる程度に重大なものということはできず、廃除事由には該当しない。
2019.11.25
被相続人の法定相続人らが相続放棄の各申述をした事案で、熟慮期間を経過しているとして却下した原審を取り消し、各申述を受理した例
[東京高決2019(令1)年11月25日 家庭の法と裁判29号64頁]
[事実の概要]
抗告人A(1932年生)及びB(1944年生)は、被相続人(2017年死亡)の法定相続人であるが、被相続人とは長い間、没交渉であり、2019年2月下旬に被相続人の固定資産税に関する書類を受領して、被相続人の死亡の事実と自分たちが法定相続人であることを知った。その後、ABは、面倒な事態に巻き込まれたくないといった思いから、相続放棄を決意したが、代表者が相続放棄をすれば足りると誤解し、2019年5月半ば、他の法定相続人Cのみが相続放棄をするに至った。当該申述書は、Bが記載し、また、3人分の申立費用額に相当する収入印紙が添付されていた。しかし、2019年6月上旬、ABは市役所の職員から、相続放棄は各人が手続を行う必要があることや、被相続人の固定資産税の滞納額の説明を受けた。これにより、ABは、同月、相続放棄の申述をしたが、原審は、民法915条1項所定の熟慮期間を経過しているとして、各申述を却下したため、ABが抗告した。
[決定の概要]
「抗告人らの本件各申述の時期が遅れたのは、自分たちの相続放棄の手続が既に完了したとの誤解や、被相続人の財産についての情報不足に起因しており、抗告人らの年齢や被相続人との従前の関係からして、やむを得ない面があったというべきであるから、このような特別な事情が認められる本件においては、民法915条1項所定の熟慮期間は、相続放棄は各自が手続を行う必要があることや滞納している固定資産税等の具体的な額についての説明を抗告人らが市役所の職員から受けた令和元年6月上旬頃から進行を開始するものと解するのが相当である。そして、…抗告人Bは同月19日に、抗告人Aは同年7月16日にそれぞれ相続放棄の申述をしたものであるから、本件各申述はいずれも適法なものとしてこれを受理すべきである。」
2019.10.21
成年後見人に選任された推定相続人ではない親族が申し立てた特別縁故者に対する財産分与の申立てについて、申立人を特別縁故者と認定し、分与の額については、成年後見人に選任された在任期間中の報酬及びそれ以前の活動その他を考慮し判断した例
[大阪家裁2019(令和元)年10月21日審判 家庭と法の裁判30号94頁]
[審判の概要]
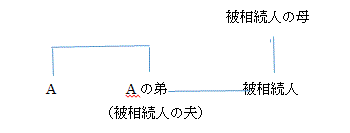
「Aは、本件申立をした後に死亡したから、その相続人である申立人らは、Aの本件財産分与申立人としての地位を相続したものと認められる。そこで、Aが被相続人と民法958条の3第1項にいう「特別の縁故があった者」(特別縁故者)に該当するか否かを検討すると、Aは、弟である被相続人の夫と同じく寝具店を経営していたことから、被相続人一家と長期間にわたって公私共に交際を続けてきた。被相続人の夫が死亡し、被相続人に認知症の症状が出始めると、Aは、頻繁に被相続人の身の回りの世話を行うだけでなく、被相続人を医療機関に受診させて訪問ヘルパーの手配や成年後見の申立をしており、被相続人を心身ともに援助した。また、Aは、被相続人の母のために、年金及び恩給の受給の手続きを行い、身元引受書を入居施設に提出し、同人が借りていた土地の立退交渉を行い、預金通帳等を管理するといった財産管理・身上監護事務を行っていたところ、被相続人がその母に対して扶養義務を負っていたことからすると、Aによる被相続人の母の財産管理、身上監護事務は、被相続人への援助とも評価することができる。被相続人について成年後見が開始した後には、その成年後見人であるAは、頻繁に被相続人と面会し、行方不明になった際には捜索に参加し、定期的に被相続人の仏壇に被相続人の隣人と積極的に交際するなど、成年後見人が行うべき財産管理、身上監護事務を超える活動をしている。そして、被相続人の死後には、Aは、被相続人の遺骨を引き取って葬儀、納骨を行うなどしている。
以上のようなAによる被相続人との交際、援助は、親族間の通常の交際の範囲を超えるものであり、Aが被相続人の成年後見人に選任された後の交際、援助については成年後見人の通常の職務の程度を超えるものというべきである。
また、被相続人は、Aに対し、死後には全財産を贈与する旨の意思表紙をしており、申立人に対して被相続人の財産を分与することは、被相続人の意思にも沿うものと考えられる。したがって、Aは特別縁故者に該当すると認められる。
続いて、相続財産の分与額を検討すると…Aは、被相続人の成年後見人に選任されその17年以上の在任期間中の後見人報酬として900万円以上を付与されていることからすると、分与額の検討に当たって、被相続人の成年後見人在任中の、Aの活動を重視することはできない。他方…Aは、被相続人の成年後見人選任前において、長期間にわたって被相続人一家と公私共に公私共に交際を続けており、被相続人の夫の死亡後には、認知症の症状が出始めた被相続人を心身共に援助した上、被相続人の母の財産管理、身上監護も行っていたものであり、これらの活動は、分与額の検討に当たって相応に重視すべきものである。さらに…被相続人は死後には全財産を贈与する旨の意思表示をしていた。
以上のほか、被相続人の相続財産の規模、内容等の本件の事情を総合考慮すると、Aには、被相続人の相続財産の10%を越える1200万円を分与することが相当である。」
2019.8.21
遺言執行者が公正証書遺言に基づいて、被相続人の長男を推定相続人から廃除(民法892条)することを求める申立をしたところ、長男の被相続人に対する暴行は厳しい非難に値するとして、申立を却下した原審を取り消し、長男を推定相続人から廃除した事例
[大阪高裁2019(令和元)年8月21日決定 家庭の法と裁判29号101頁]
[事実の概要]
長男は、被相続人に対し、H19年、H22年4月、7月と3回にわたり暴行を加え、そのうちのH22年4月の暴行により、被相続人に全治約3週間を要する両側肋骨骨折や左外傷性気胸の傷害を負わせた。被相続人は、H22年7月の暴行により鼻から出血するという傷害を負った。
被相続人は、H23年3月、公正証書遺言において、長男が、被相続人に対し、しばしば殴る蹴るの暴行を加えるなど虐待を繰り返し、また、重大な侮辱を加えたことを理由として、長男を被相続人の推定相続人から廃除するとの意思表示をした。
遺言執行者が、公正証書遺言に基づき、長男の廃除を申し立てたところ、原審は申立てを却下し、遺言執行者が即時抗告した。
[決定の概要]
原審は、長男が暴行に至った経緯についての長男の供述に一応の信用性がある一方で、遺言執行者は暴行の原因や背景について特段の主張をしておらず、被相続人の言動が長男の暴行を誘発した可能性もあるとして、長男を廃除することを認めなかった。
これに対し、抗告審においては、長男の陳述内容が、以前、弁護士宛にファクシミリにより送信した書面の記載内容と食い違っていることなどから、長男の陳述の信用性を否定した。
また、仮に、「被相続人の言動に長男が立腹するような事情があったとしても、それに対し、当時60歳を優に超えていた被相続人に暴力を振るうことをもって対応することが許されないことはいうまでもない」、「長男が被相続人に対し、少なくとも3回にわたって暴行に及んだことは看過し得ないことと言わなければならない」、また、「その結果も極めて重大である。これらによれば、長男の被相続人に対する上記各暴行は、社会通念上、厳しい非難に値するものと言うべきである」と判示し、原審を取り消し、長男を被相続人の推定相続人から廃除した。
2019.3.19
[東京高裁2019(H31)年3月19日決定 家庭の法と裁判33号82頁]
[事実の概要]
被相続人の長男が、被相続人の妻らに対し、仏具等の祭祀財産につき自らを承継者と指定する審判を求めた事案。原審は、対象とされた財産のうち被相続人が生前所有していない本件位牌等については祭祀財産に当たらないとし、被相続人が生前所有していた本件香炉等については、当事者間に祭祀承継者を長男と認める黙示の合意が成立したとして、長男を祭祀承継者と定めた。抗告審は、原審を是認したうえで、本件位牌等はいわば被相続人自体といえる遺体や遺骨とはその性質において異なり、祭祀財産に準じたものとして扱うことも困難とした。
[決定の概要]
(1)祭祀承継者に承継される祭祀財産について
被相続人の各祭祀財産のうち、①香炉、②燭台、③花立て、④仏飯具、⑤線香立て、⑥マッチ消し、⑦仏壇台(以下「本件香炉等」)については、被相続人が所有していたものと認めるのが相当であるから、被相続人妻に対し、長男に、これを引き渡すことを命ずるという限度で理由があるとした。
ただし、⑧リン、リン棒、リン布団、⑨被相続人の位牌(以下「本件位牌等」)については、被相続人の死後に購入したものである。
この点、長男は、本件位牌等も、被相続人が生前保存していた財産ではない遺体や遺骨と同様に扱われるべきであり、祭祀財産に準じたものといえると主張する。
しかし、抗告審は、たとえ被相続人が生前所有していた財産でない点で共通点があるとしても、被相続人の遺体や遺骨は、被相続人自身から生じた者であって、いわば被相続人自体であるといえるものであるのに対し、本件位牌等は、被相続人以外の主体が制作したものが取得されたものであって、その性質において遺体や遺骨と異なる。そうすると、本件位牌等を、被相続人の遺体や遺骨等のように祭祀財産に準じたものと取り扱うことは困難であるとして、長男の申立てを棄却した。
(2)祭祀財産の承継者の指定基準について
抗告審は、相続人の合意により祭祀承継者を指定できるのとの見解を採用し、長男が喪主として被相続人の葬儀を主催し、菩提寺に被相続人の遺骨を納骨し、檀徒の地位や本件墓地の永代使用権を承継し、檀徒として仏事に参加し、墓地の管理を続けてきたこと、被相続人の母の遺産分割機協議書にて長男が責任をもって法事等を行うことが記載され、これに被相続人の妻らが署名したこと、被相続人の妻が長男の要望に応じて仏壇等を引き渡したことなどを総合的に考慮して、長男と被相続人の妻らとの間で、祭祀主催者は長男と定める旨の黙示の合意があったと認めるのが相当であるとした原審の判断を相当とした。
2018.11.30
被相続人が、相続人の1人に対し、同人の子(被相続人の孫)の誕生祝いとして贈与した200万円が特別受益にあたるとした上で、うち100万円の限度で持ち戻し免除の意思を推認できる等として原審判の判断を相当とした事例
[東京高裁2018(令和元)年11月30日決定 家庭の法と裁判31号90頁]
[事実の概要]
被相続人の相続人は長女と二男の2人である。
1976(昭和51)年、二男の子(被相続人の孫)が誕生した際、被相続人は二男に対し、お祝いとして200万円を贈与した。なお、長女には子はいなかった。
二男が申し立てた遺産分割審判において、この200万円が特別受益に当たるか否か等が争われた。
原審の東京家裁は、「お祝い金は、その支出当時の被相続人の資産、社会的地位や当時の社会状況等に照らし、親としての通常の扶養義務の範囲に入ると評価される場合を除き、特別受益に当たると解されるところ、昭和51年当時における200万円という金額は、被相続人の資産、被相続人…と申立人との親子関係等を考慮するとしても、当時の貨幣価値からすると、社会通念上高額であるし、また、本件においては、相手方には同様の趣旨に基づくお祝い金が贈られていないことからすると、相続人間で均衡を失するから、200万円の贈与は特別受益に当たるというべきである。…他方で、被相続人…の孫の誕生を祝う心情と被相続人の資産等を考慮すると、100万円の限度においては親としての通常の扶養義務の範囲に入るものと認められるから、特別受益の持戻し免除の意思を推認できる。以上によれば、申立人は、昭和51年当時、100万円の生前贈与を受けたものと認められる。」と認定した。なお、その評価については、「昭和51年の物価指数は61.5であり、相続開始時の平成14年の物価指数は96.5であるから、贈与時の100万円は、相続開始時には、156万9105円の価値を有することになる。」とした。
長女は原審を不服として抗告した。
[決定の概要]
「抗告人の主張を採用することはできず、相手方については、昭和51年5月に100万円を限度とする特別受益があったと認めるのが相当である」等として、長女の抗告を棄却した。
[ひとこと]
出産祝いが特別受益に当たるか、当たるとして、持戻し免除の意思をどの限度で認めるべきかが争点とされた事例である。原審(東京家審2018(平成30)年9月27日)は、「家庭裁判所における遺産分割・遺留分の実務」の著者である片岡武元裁判官が担当しており、規範部分は実務上の参考になるため、一読をお勧めする。
|
 |
 |
|
|



