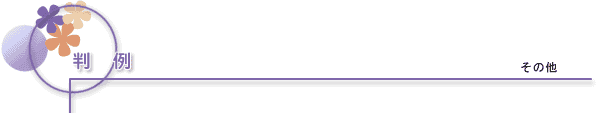 |
|
事実婚
1 事実婚の不当破棄
1−1992.10.27
男性に妻のあることを知りながら事実婚関係に入った女性から、男性に対する事実婚関係の不当破棄を理由とする損害賠償請求が認められた例
[裁判所]京都地裁
[年月日]1992(平成4)年10月27日判決
[出典]判タ804号156頁
2 年金の受給
重婚関係の場合、判例は、法律婚が実態を失い、事実上の離婚状態にあるか否かによって、いずれが受給者となるかを決定している。ただし、離婚の判断における「破綻」の認定よりも厳格であり、わずかでも音信や送金があれば、法律婚の破綻を認定しない傾向がある。
2−2008.8.26
内縁の妻が遺族厚生年金を受給している状況のもと、戸籍上の妻が、自らに対する遺族厚生年金の不支給処分の取消を請求し、認容された事例
[裁判所]福岡地裁
[年月日]2008(平成20)年8月26日判決
[出典]判タ1291号82頁
[事実の概要]
約22年間の婚姻生活の後、約7年間の夫との別居を継続していた戸籍上の妻が、夫の遺族厚生年金支給の裁定請求に対してなされた不支給処分に対して、取消しの請求をした事案。別居後、夫から戸籍上の妻に対して離婚請求訴訟が提起されたが、婚姻関係破綻が認められず棄却された経緯がある。また、戸籍上の妻は、婚姻費用分担審判により、夫が死亡するまで、夫から毎月送金を受けていた。
なお、夫には、別居後約5年間同居し親密な関係にあった女性がおり、夫死亡後は、その女性が、夫の遺族厚生年金を受給していた。
以上の状況のもと、原告たる戸籍上の妻の①配偶者要件及び②生計維持要件が満たされるかが問題となった。
[判決の概要]
①配偶者要件について、事実上の離婚状態にあるときは、もはや「配偶者」に当たらないとした上で、戸籍上の妻と夫との約22年間の婚姻生活に比して、別居期間は約7年にすぎず、他方、内縁の妻との親密な関係は5年程度であること、夫からの離婚請求は婚姻関係破綻が認められず棄却されていること、戸籍上の妻は夫からの婚姻費用の送金を受け続けていること、離婚に伴う給付は何ら行われていないことなどの事情から、事実上の離婚状態にあったとまで認めることはできないとして、要件該当性を認めた。
②生計維持要件について、生計を同一にする場合のほか、これに準じる場合も含むとした上で、戸籍上の妻は、夫からの婚姻費用の送金がなければ生計維持が困難であったとして、要件該当性を認めた。
[ひとこと]
夫と内縁の妻との約5年にわたる同居のほか、内縁の妻が夫の母親の看病をしていたといった事情もあった。婚姻費用支給という事情を重視してしまうと、夫が婚姻費用を真面目に支払うと内縁の妻が保護されないという事態に陥る危険がある。
2−2007.7.11
本妻に遺族年金受給資格を認め、内妻を受給者とした一審を取り消した事例
[裁判所]東京高裁
[年月日]2007(平成19)年7月11日判決
[出典]法学教室324号78頁 判時1991号67頁
[事実の概要]
法律上の妻と離婚しないまま、事実婚の妻と同居中に死亡した男性の遺族年金をめぐり、どちらが遺族年金を受け取るかが争われた。
[判決の概要]
本妻との婚姻関係が長期にわたって完全に実体を失っている場合に限り、内妻に受給資格があるとし、本件では、「本妻と事実上の離婚状態だったとまではいえない」として、一審判決を取り消して、法律上の妻に受給資格を認めた。
2−2007.3.8
近親婚の内縁に遺族年金受給資格を認めた例
[裁判所]最高裁一小
[年月日]2007(平成19)年3月8日判決
[出典]法学教室320号193頁 家月59巻7号63頁 判タ1238号177頁 判時1967号86頁
[事実の概要]
叔父と内縁関係にあった女性が、近親婚を理由に遺族厚生年金を支給しないのは違法だとして、社会保険庁に不支給処分の取り消しを求めた訴訟の上告審(地裁判決2−2004.6.22参照)。
[判決の概要]
「直系血族間、二親等の傍系血族間の内縁関係は、我が国の現在の婚姻法秩序又は社会通念を前提とする限り、反倫理性、反公益性が極めて大きい」「三親等の傍系血族間の内縁関係も反倫理性、反公益性という観点からみれば、基本的には認められない」との判断を示したが、「もっとも、我が国では、かつて、農業後継者の確保等の要請から親族間の結婚が少なからず行われていたことは公知の事実であり、前記事実関係によれば、上告人の周囲でも、前記のような地域的特性から親族間の結婚が比較的多く行われるとともに、おじと姪との間の内縁も散見されたというのであって、そのような関係が地域社会や親族内において抵抗感なく受け容れられている例も存在したことがうかがわれるのである。このような社会的、時代的背景の下に形成された三親等の傍系血族間の内縁関係については、共同生活の長さや子の有無、周囲の受け止め方などを総合判断し、反倫理性や反公益性が著しく低いと認められる場合には、近親者間における婚姻を禁止すべき公益的要請よりも遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与するという法の目的を優先させるべき特段の事情があるものというべきである」として原判決を破棄し、不支給処分の取り消しを認めた。
2−2006.11.16
36年間重婚的内縁関係にあった女性に対する遺族厚生年金等不支給とした決定を無効とはいえないとした事例
[裁判所]名古屋地裁
[年月日]2006(平成18)年11月16日判決
[出典]判タ1272号79頁
[事実の概要]
36年間重婚的内縁であった原告が、事実上の夫太郎の死後(平成12年8月死亡)、社会保険庁長官に対し、夫が受給していた厚生年金・共済年金の未支給分及び厚生年金保険の遺族給付を請求、国鉄共済組合に対しては遺族共済年金を支給を請求し、いずれも不支給とする処分を受けた。原告はこれらの無効を訴えて提訴した。
夫には36年間別居している法律上の配偶者がおり、配偶者が補助参加人となった。夫は別居直後から2ヶ月に1回、補助参加人に生活費を送金、平成12年2月まで続いた。夫死亡まで補助参加人には離婚の意思がなかった。
[判決の概要]
太郎と補助参加人の別居の期間は36年余の長期間に及んでいること、その間に形成された原告と太郎との重婚的内縁関係は固定化し、太郎が死亡するまで継続したこと、補助参加人は、別居直後のころを除いて、太郎との同居生活の回復など、実質的な婚姻関係を維持するための働きかけをした経緯が見受けられず、太郎が入院した際の見舞いなどにも2回ほどしか赴かなかったこと、太郎は平成6年ころ、補助参加人に対して離婚を申し出たことがあることなど、太郎と補助参加人との婚姻関係は、実質的な夫婦としての交流や精神的な依存関係が希薄化し、現実的な修復が困難な状況になっていたものと解すべき余地がある。
しかしながら、一方において、太郎は補助参加人に対し、生活費の定期的な送金を継続し、補助参加人の生活はこれに依存していたこと、太郎は、別居後も補助参加人と一緒に親族らの冠婚葬祭に出席し、限られた機会ではあるが補助参加人らと旅行をしたり、補助参加人宅を訪れたこともあり、電話や手紙、また野菜等の送付など、折にふれて音信や連絡を継続していたこと、これらの状況、経緯も認められる。
そして、補助参加人は、太郎との離婚に応じる意向を持ったことはなく、平成6年に太郎から離婚を求められた際にもこれを断り、役所に離婚届の不受理願いを提出し、太郎も、こうした補助参加人の意向を押し切ってまで法的な離婚手続に及んだり、これを準備したような経緯はなく、むしろ、上記の離婚の要請の際にいったん減額した送金を、まもなく従前と同額に回復させていること、これらの経緯をも併せ考えると、太郎は補助参加人との離婚を望みつつも、それまでの経緯や補助参加人の意向などの諸事情一切を考慮して、少なくとも法的な婚姻関係を維持、継続し、補助参加人への生活費の送金を続けてその生計を維持する意思であったものと解される。
以上の諸事情によってみれば、被告らにおいて、太郎と補助参加人との婚姻関係が全く形がい化し、事実上の離婚状態にあるものと判断せず、補助参加人を本件各遺族給付の給付対象者たる配偶者と認めて、原告を上記配偶者と認めなかったことについて、重大かつ明白な瑕疵があるとは認められない。
2−2005.5.31
近親婚の内縁の妻に、遺族年金の支給を認めなかった例
[裁判所]東京高裁
[年月日]2005(平成17)年5月31日判決
[出典]判時1912号3頁
田中通裕・判例評釈・判タ1211号34頁
[事実の概要]
地裁判決2−2004.6.22参照。
[判決の要旨]
「遺族年金制度は社会保障的性格が強く、事実婚の者が受給権を持つかどうかは、公的保護にふさわしい関係かという観点から判断すべきだ」とし、民法が禁じる三親等内の近親婚は「反倫理的で公益を害するものとされており保護することが予定されていない」として、姪の女性の受給を認めなかった。
[ひとこと]
地裁判決は受給を認めていた。重婚の場合は、法秩序に反する内縁関係という理由で遺族年金が不支給になっていないことと対比しても、厳しい判断である。
2−2005.4.21
私立学校教職員共済制度による遺族年金について、別居中の戸籍上の妻ではなく同居の内縁の妻に受給権があるとした例
[裁判所]最高裁第一小法廷
[年月日] 2005(平17)年4月21日
[出典]判時1895号50頁
[事実の概要] 2−2004.3.19(地裁判決)参照
[判決の概要]男性と戸籍上の妻は、①長期間別居していた、②生活費の負担など扶養・被扶養関係がなかった、③婚姻関係を修復する努力をしていなかった、ことなどから、婚姻関係は実体を失って修復の余地がないほど形がい化していた」とした。5人中、横尾和子裁判官のみ反対意見を述べ、別居後も戸籍上の妻らを大学宿舎に住まわせ宿舎料を支払っていたことから、形がい化していたとはいえない、とした。
[ひとこと]最高裁が一審、二審判決を支持した。二審判決は、東京高判 2004(平16)年8月19日(法学教室289号174頁)。
2−2004.6.22
近親婚の内縁に遺族年金受給資格を認めた例
[裁判所]東京地裁判決
[年月日] 2004(平成16)年6月22日
[出典] 判タ1162号140頁
法学教室287号123頁04年8月号
[判決の概要]
おじ(72歳)と姪(64歳)が、42年間内縁関係にあった。民法の禁じる近親婚の関係にあり婚姻届出は出されていなかった。女性が社会保険庁長官を相手に、遺族年金不支給処分の取消しを求めて提訴した。判決は、「内縁関係は42年にわたり、職場や地域でも抵抗なく受け入れられてきた。法的には婚姻関係に等しい。」「遺族年金は、遺族の生活の安定のために給付されるもので、民法とは目的が異なる。」「一度は親子の関係にあった者が内縁関係になった場合とは、社会的評価や抵抗感が異なる。」として不支給処分を取り消した。
[ひとこと]
近親婚で遺族年金の受給資格を初めて認めた判決。民法734条1項は直系血族又は3親等以内の傍系血族との婚姻を禁じている。おじと姪は3親等にあたる。1985年最高裁判決は、亡夫の連れ子と内縁関係にあった女性(民法735条直系姻族間の婚姻禁止に反する関係)に資格を認めていなかった。
控訴審では受給を認めず。2-2005.5.31参照。
2−2004.3.19
私立学校教職員共済の遺族年金の受給者につき、「20年近く直接会っていないなど戸籍上の妻との婚姻関係は実体を失っていた」として、事実婚の配偶者に受給権を認めた例
[裁判所]東京地裁判決
[年月日]2004(平成16)年3月19日
[出典]判時1866号34頁
[ひとこと]
控訴審でも地裁判断が支持された。
2−1999.12.27
労災保険法に基づく遺族補償年金の受給者を事実婚の配偶者とした例
[裁判所]東京地裁
[年月日]1999(平成11)年12月27日判決
2−1995.10.19
遺族補償年金の受給者を法律婚の配偶者とした例
[裁判所]東京地裁
[年月日]1995(平成7)年10月19日判決
[出典]判タ915号90頁
3 事実婚(内縁)配偶者の遺産について
3−2011.11.15
内縁解消後、財産分与審判手続中に分与義務者が死亡した場合に、民法768条の財産分与規定が準用できるとし、財産分与義務を相続人が相続するとされた例
[裁判所]大阪高裁
[年月日]2011(平成23)年11月15日決定
[出典]判時2154号75頁
[事実の概要]
昭和57年頃から抗告人X(女性)とA(男性)は内縁関係にあったが、平成18年7月にXがA宅を出て、内縁関係は解消された。Xは平成19年11月に財産分与調停を申し立てたが、合意に至らず、平成20年5月に不成立となり、審判手続きに移行した。審判手続中である平成21年7月にAが死亡し、Aの法定相続人である相手方Yら(内縁開始前に死亡した前妻との間の3名の子)が本件審判手続を受継した。
[決定の概要]
財産分与義務の相続性について
「内縁関係の解消によって財産分与請求権は既に発生している。そして、抗告人は財産分与調停を申し立てて、これを請求する意思を明らかにしているところ、これが審判に移行したのであるから、その具体的な権利内容は審判において形成されるのであって、亡太郎(被相続人)が審判中に死亡した場合、財産分与義務が相続対象となることを否定すべき理由は存在しない」とし、
民法768条(財産分与規定)の準用について
「本件は、内縁関係解消後に生存権利者が生存義務者に財産分与請求をした事案であって、・・最高裁決定の事例(いわゆる内縁関係の死亡解消)とは事案が異なるから、附帯抗告人の主張は前提を欠き、採用できない」として、
相手方Yらそれぞれに対し、金1666万円の支払いを命じた。
[ひとこと]
協議や審判等により財産分与請求の存否や額が確定しておらず、具体的な財産請求権になっていない段階でも、財産分与義務は相続されうること、及び内縁の離婚(死亡による解消は除く)の場合にも民法768条の財産分与規定が類推適用されることが確認された事案である。しかし、死亡による内縁解消の場合には、民法768条が類推適用されない(最決平12.3.10)点は変わっておらず、内縁解消後に分与義務者が死亡した場合(本件)と死亡により内縁解消をすることになった場合とで、内縁配偶者の財産関係に大きな格差が依然残ることになる。
3−2011.2.25
重婚的内縁関係にある者の一方の単独名義の建物につき,他方による建物の共有持分の取得を否定したが,一方が死亡した後は他方が単独で無償で使用する旨の合意が黙示に成立していたと認めた事例
[裁判所]名古屋地裁
[年月日]2011(平成23)年2月25日判決
[出典]判時2118号66頁
[事実の概要]
訴外Aは法律婚をした訴外Bとの間に長男であるXをもうけたが,昭和60年ころからYと交際し,同居することとなった。Yは,Aの身の回りの世話をしたほか,Aのスナック廃業の際の借金750万円を主として自己資金で返済したり,Aが設立した会社の資金もYが親族から借りるなどして工面したりした。平成11年,会社の事務所が手狭になったことから,A名義で土地を購入し,自宅兼会社の工場とする建物を建築した。Yは会社の従業員として経理を担当したほか,会社の運転資金が足りない時には,自分の定期預金等を解約したり,親戚から金銭を借り入れる等して補てんしたりした。さらには,Yは,従業員に食事を食べさせる等の生活の世話も行い,従業員からは「お母さん」などと呼ばれて慕われ,Aと従業員の結婚式の仲人を務める等,夫婦として認識されていた。AはBに訴外会社設立前は毎月20万円程度,設立後は毎月25万円から30万円程度の生活費を届けた。
Aは平成21年交通事故により死亡した。訴外会社が掛け金を支払っていたAの自動車保険3000万円と生命保険300万円は,受取人を訴外会社とされておらず,YはXに保険金で訴外会社の借金の返済をしたいと譲渡を求めたが,Xは拒否し,保険金を受領した。訴外会社は,平成22年株主総会決議により解散した。Yの訴外会社に対する貸付金は約2500万円である。
Aの相続人であるXは,Aの単独名義であった建物の共有持分権に基づき,Yに対し,建物の明渡しと賃料相当損害金の支払いを求めた。
[判決の概要]
被告は,内縁の妻として保護されるが,「重婚的内縁関係にあることに鑑み,その権利の性質に応じ、」「一夫一婦制の趣旨が没却されることがない限度で保護されるにとどまる」。
本件建物のローンが被告とAと共同事業として経営していた会社の収益から支払われていたことから,共有持分を有しているとの被告の主張は,生前被告やAが移転登記を検討していた形跡もないこと等から,斥けられた。
内縁の夫婦が居住または共同事業のために共同で使用してきた不動産について,一方の死亡後には他方の単独使用の合意の成立を認めた最一判平10.2.26(民集52巻1号255頁,判時1634号74頁)に照らし,本件の諸事情からすれば,Aの「死後は当然被告が本件建物を単独で無償使用することを想定していたと考えるのが合理的であり、被告と亡太郎の間ではかかる合意が黙示的に成立していたと認めるのが相当である。」とした。
仮に無償使用の合意が成立していたとまではいえないとしても,訴外会社が掛け金を支払ってきた保険金は本来はAが死亡したときに会社の債務の支払等に充てるために加入していたものとしか考えられないにもかかわらず,被告らが訴外会社を受取人とすることを失念していたために,Bらに支払われることになったこと,訴外会社の債務超過状態が解消されないため,精算手続を行わざるを得なくなり,被告は,生活の手段も失い,本件建物以外に住む場所も資産もないこと,被告とAとの労働によって得られた収入のうち相当額がBと原告に渡されてきたこと,Bも原告も本件建物を必要としているのではなく売却を求めめていることなどに照らすと,Aを責めることもなかった原告が,Aの死亡後に突然,被告の権利を全て否定し,建物の明渡し及び賃料相当損害金を要求することは,権利濫用として許されない。
[ひとこと]
重婚的内縁関係にある配偶者についても,一夫一婦制の趣旨が没却されない限度で保護されるとし,最一判平10.2.26(民集52巻1号255頁,判時1634号74頁)の趣旨が妥当するとして,死後の使用貸借の合意が、生前に黙示的に成立していることを認めた。Yが自己の定期預金を崩す等して経営を続けた会社の収益を原資として建築した不動産であること等,本件の経緯に照らし,妥当な結論である。
ただし、最判平成10.2.26は、類似事案であるが、その事件の前に、事実婚夫の単独名義不動産につき、事実婚妻の共有持分を認める判決が確定しており、共有物の規定を使っても使用権は認められる事案であった(無償まではいかなくとも)。本件は、「共有持分取得に相応する程度の寄与をしていると評価できる」とまで認めながら、持分を認めなかった点、他の裁判例との関係では若干疑問である。共有物ではないにもかかわらず、妻の使用借権を認めた点は、新しい判断である。
3−2010.10.21
死亡した事実婚の夫所有建物につき、妻に使用貸借権が認められた例
[大阪高裁2010(平成22)年10月21日判決 判時2108号72頁]
[事実の概要]
夫Aは妻Bとの間に子Xがいる。1965(昭40)年頃、AはY女と男女関係になり、1979年頃、甲建物をYの住居として提供した。Bの死後は、Aは甲建物でYと暮らした。Aが死亡し、Yはそのまま甲建物で暮らしている。Yは78歳で、Aの遺族年金で暮らし、近所とのつきあいも長い。Xの資産はYと比べると相当優良である。相続人である子XはYに対し、建物明渡しと、明渡し済みまでの賃料相当損害金の支払いを求めて提訴した。
Aは、2004(平16)年頃、XやY兄夫婦の前で、Aにもしものことがあったら、Yに家をやり、そこに死ぬまで住まわせて、1500万円を渡してほしいと申し渡した。
Yは、裁判で、建物を無償で使用できる使用貸借契約を黙示的に締結したと主張した。一審は、建物明渡し請求は権利濫用に当るとして棄却した。
[判決の概要]
Yは「2004(平16)年当時愛人、内縁の妻として40年もの長きにわたりAに尽くし、その間妊娠中絶まで経験した反面、十分な経済的基盤も有しない状態であった・・・本件A申渡しのあった平成16年ころには、AとYとの間で、黙示的に被控訴人(Y)が死亡するまで本件建物を無償で使用させる旨の本件使用貸借契約が成立していたものと認めるのが相当である。」として、Xの控訴を棄却した。
3−2006.7.6
27年間夫婦同然の関係にあった女性に対する所有不動産の一部の死因贈与が公序良俗に違反しないとされた例
[裁判所]東京地裁
[年月日]2006(平成18)年7月6日判決
[出典]判時1967号96頁
[判決の概要]
本件各贈与契約は、贈与者が死亡した後の法律上の妻子と事実上の夫婦同然の関係にあった女性双方の生活を案じて、事実上の夫婦関係にあった被告に対して、その所有する不動産の一部を振り分けるために贈与したもので、法律上の妻子らにも不動産のかなりの部分が残されているというべきであるから、本件各贈与契約の全部又は一部が公序良俗に反し無効となる余地はない。
3−2000.3.10
事実婚(内縁)夫婦の一方の死亡により事実婚関係が終了した場合、民法768条の財産分与規定の類推適用を否定した例
[裁判所]最一小
[年月日]2000(平成12)年3月10日決定
[出典]家月52巻10号81頁、判時1716号60頁、判タ1037号107頁
[ひとこと]
財産分与規定の準用については説が分かれていたが、最高裁は否定した。なお、生存中の離婚の場合は、事実婚にも法律婚の財産分与規定が準用されている。死亡の場合には、以下の共有の論理で解決される場合がある。
3−1982.11.30
事実婚夫婦が共同経営し資産の維持形成に寄与した場合には、民法250条によって共有持分認められた例
[裁判所]大阪高裁
[年月日]1982(昭和57)年11月30日判決
[出典] 家月36巻1号139頁、判タ489号65頁他
4 事実婚その他
4−2018.11.19
内縁関係の終了に伴う財産分与の申立てについて、財産分与の対象財産の形成及び増加につき、内縁の夫(相手方)の保有資産及び長年築いてきた社会的地位等による影響や寄与が相当程度あったとして、分与割合につき内縁の妻(抗告人)を3分の1、相手方を3分の2とした事例
[福岡高等裁判所2018(平成30)年11月19日決定 家庭の法と裁判25号53頁]
[事実及び決定の概要]
抗告人と相手方は、平成7年から平成25年までの約18年半もの長期にわたって生活を共にしており、双方の親族らとも交流があったほか、同じ団体に所属して一緒に活動を行い、旅行等にも一緒に赴くなどしていた。したがって、抗告人と相手方との間には、内縁関係が成立していると認めることができるとした。
また、財産分与における夫婦財産の清算においては、婚姻後に形成した財産について、双方の財産形成に対する経済的貢献度、寄与度を考慮し、実質的に公平になるように分配すべきものであり、これは内縁関係においても同様に考えられるとしたうえで、申立人は、上記内縁関係が成立していた期間において、家庭内において家事等に従事していたのであるから、内縁関係の終了に伴い、相手方から相応の財産分与を受けることができる立場にあることした。
ただし、相手方は、抗告人と相手方との内縁関係が成立する前から、不動産賃貸業を営む株式会社の代表取締役として、長年にわたって同社の経営に携わるなどして、相当多額の資産を保有していたこと、他方で、抗告人は同居前に破産申立てをするなど、内縁関係が成立する次点において目立った資産を保有していなかったこと、また、内縁関係が成立した平成7年5月時点で、抗告人は57歳、相手方が60歳であったこと等に照らすと、財産分与の対象財産の形成及び増加等について、相手方の保有資産及び長年築いてきた社会的地位等による影響や寄与が相当程度あったと認められるべきである。これによれば、分与割合について、抗告人を3分の1、相手方と3分の2と認めるのが相当であるとした。
4−2007.4.24
内縁の夫の過失を被害者側の過失として考慮することができるとした事例
[裁判所]最高裁第三小法廷
[年月日]2007(平成19)年4月24日判決
[出典]判時1970号54頁
[事実の概要]
内縁の夫の運転する自動車の助手席に同乗していた被上告人が、同車と上告人の運転する自動車とが衝突した事故により傷害を負い、後遺障害が残ったなどと主張して、運行供用者である上告人に対し、自動車損害賠償保障法3条に基づき損害賠償を請求したところ、上告人が、過失相殺の抗弁として、被上告人の内縁の夫の過失を被害者側の過失として考慮すべきであると主張し、その損害賠償額を争った。
[判決の概要]
不法行為に基づき被害者に対して支払われるべき損害賠償額を定めるに当たっては、被害者と身分上、生活関係上一体を成すとみられるような関係にある者の過失についても、民法722条2項の規定により、いわゆる被害者側の過失としてこれを考慮することができる。内縁の夫が内縁の妻を同乗させて運転する自動車と第三者が運転する自動車とが衝突し、それにより傷害を負った内縁の妻が第三者に対して損害賠償を請求する場合において、その損害賠償額を定めるに当たっては、内縁の夫の過失を被害者側の過失として考慮することができると解するのが相当である。
4−2006.8.30
刑法244条1項の規定は内縁配偶者には適用されないとした事例
[裁判所]最高裁
[年月日]2006(平成18)年8月30日決定
[出典]刑集60巻6号479頁、判時1944号169頁
[事実の概要]
同居中の元妻から現金約700万円を盗んだとして窃盗罪に問われ、1,2審で懲役2年6月の実刑判決を受けた男性に対する上告審。
[判決の概要]
男性側は、配偶者や同居する親族間で行われた窃盗の場合は刑が免除される刑法244条1項の適用を主張したが、最高裁は「内縁の場合には適用されない」として上告を棄却した。
|
 |
 |
|
|



