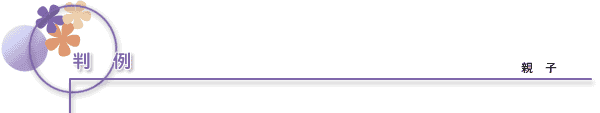 |
|
ハーグ条約
2020.4.16
ハーグ条約実施法による子の返還申立事件に係る家事調停における子の返還条項について、終局決定の変更を定めた同法117条1項が類推適用されるとした例
[最一小決2020(令2)年4月16日 家庭の法と裁判29号49頁]
[事実の概要]
抗告人(母)、相手方(父)及び両名の子は、ロシア連邦で同居していたが、子及び抗告人が日本に入国したことにより別居するに至った。その後、2017年に抗告人と相手方との間で、抗告人が子をロシア連邦に返還する旨を含む調停が家裁で成立した。しかし、子(合意当時9ないし10歳)がロシア連邦への帰国を拒否したことから、抗告人が、調停成立後、事情変更により子の返還条項を維持することが不当となったとして、国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律(いわゆる「ハーグ条約実施法」)117条1項の規定に基づき、子の返還条項の変更を求めた事案である。
なお、原審は、同項の規定は変更対象を子の返還を命ずる終局決定に限定していることや、調停において子の返還と併せて他の合意がなされる場合に子の返還条項のみを変更することが相当でないことを挙げ、抗告を棄却した。
[決定の概要]
ハーグ実施法117条1項の直接適用ではなく類推適用を認め、原決定を破棄し、東京高等裁判所に差し戻した。
「実施法117条1項の規定は、子の返還を命ずる終局決定が確定した場合、子の返還は迅速に行われるべきではあるが、子が返還される前に事情の変更により上記決定を維持することが子の利益の観点から不当となりうることがあり得るため、そのようなときには、上記決定が子に対して重大な影響を与えることに鑑みて、上記決定を変更することができることとしたものと解される。子の返還条項は確定した子の返還を命ずる終局決定と同一の効力を有するところ(実施法145条3項)、子を返還する旨の調停が成立した場合も、事情の変更により子の返還条項を維持することが子の利益の観点から不当となることがあり得るため、そのようなときに子の返還条項を変更する必要があることは、上記決定が確定した場合と同様である。」
「子の返還申立事件に係る家事調停において子の返還の合意と併せて養育費、面会交流等について他の合意がされ、その後に子の返還条項を変更するに伴って当該調停における他の定めも変更する必要が生ずる場合」は、「別途、家事事件手続法上の変更手続等により対処することが可能である」。
「以上によれば、裁判所は、子の返還申立事件に係る家事調停において、子を返還する旨の調停が成立した後に、事情の変更により子の返還条項を維持することを不当と認めるに至った場合は、実施法117条1項の規定を類推適用して、当事者の申立てにより、子の返還条項を変更することができると解するのが相当である。」とした。
2018.12.11
スペイン人父からのハーグ条約実施法に基づく返還申立てが、返還拒否事由があるとして却下された例
[東京家裁2018(平成30)年12月11日決定 家庭の法と裁判26号114頁]
[事実の概要]
X(夫・スペイン国籍)はY(妻・日本国籍)と2009年に婚姻するに際し、Yの子C(2006年生)と養子縁組した。その後XY間にはD(2011年生)とE(2015年生)が生まれ、スペインで生活をしていた。Yは日本を2017年9月5日に出発するスペイン行きの航空便を予約してある状況で、子らとスペインを出国し、同年5月13日、日本に入国した。Yは2017年9月5日を経過しても日本に留まっている。Xは、2018年2月、子らの返還を求めて、弁護士会紛争解決センターにADRの申立てをした。Yは子らを返還することには応じられないとの答弁書を提出し、同年8月に協議は終了した。同年10月16日、Xはハーグ条約実施法に基づき、子らをスペインに返還するように求めた。
[決定の概要]
Yは、帰国予定日であった2017年9月5日以後、子らをスペインに帰国させることなく日本に滞在させたままの状況に置いている。そして、Xは同日の経過を待って、スペインの中央当局に対し、子らの返還に関する援助申請をしていることから、子らのスペインの返還に向けた手続の必要性を認識したということができる。そうすると、遅くとも、同日の経過をもって、Yは子らをスペインに返還しないことを明確に示し、XもYによる子らの留置を明確に認識したというべきであり、Yによる子らの留置は、遅くとも2017年9月5日に開始したと認められる。子らは学校や保育園で周囲の者と積極的にかかわるほか、学校や保育園以外でも活動の範囲を広げ、地域社会との関係を形成している。そして、C及びDについては、日本での生活を肯定的に受け止めており、Eについても言語能力を含め心身ともに順調に成長しているとうかがわれることからすると、子らはいずれも新たな環境である日本での生活に適応したというべきである。
以上検討したとおり、子らの返還申立ては、Yによる子らの留置から1年を経過した後にされたものと認められ、子らは新たな環境である日本での生活に適応しているということができ、実施法28条1項1号に規定する子の返還拒否事由があると認めることができる。そして、本件記録を検討しても、裁量により子らをスペインに返還すべき事情は認められないものとして、Xの申立てを却下した。
2018.7.17
ハーグ条約実施法に基づく返還決定後の人身保護請求事件の差戻審で請求が認容された事例
[名古屋高裁2018(平成30)年7月17日判決 判時2398号87頁、LEX/DB25560800]
[事実の概要]
最高裁第一小法廷2018(平成30)年3月15日判決(家庭の法と裁判15号65頁)の差戻審。
[判決の概要]
1子が自由意思に基づいて監護者の下にとどまっているとはいえない特段の事情
意思能力がある子の監護について、子が自由意思に基づいて監護者の下にとどまっているとはいえない特段の事情があるときは、監護者の子に対する監護は人身保護法・同規則にいう拘束に当たる(最高裁昭和61年7月18日第2小法廷判決民集40巻5号991頁)。
本件のように国境を越えて日本への連れ去りをされた場合についての上記特段の事情の判断基準については、最高裁第一小法廷2018(平成30)年3月15日判決(家庭の法と裁判15号65頁)の「判決の概要」の1の部分に拠るものとした。
本件については、被拘束者は13歳で意思能力を有しているが、11歳〇カ月のときに来日し、その後請求者と意思疎通を行う機会が十分ないまま、拘束者に大きく依存して生活せざるを得ない状況にある。拘束者は、返還決定が確定したにもかかわらず、被拘束者を米国に返還しない態度を示し、代替執行に際しても、被拘束者の面前で解放実施に激しく抵抗した。これらの事情に鑑みると、被拘束者は返還決定や代替執行の意義、返還された後の生活の情報を含め、拘束者の下にとどまるか否かについての意思決定をするために必要とされる情報を十分得ることが困難であった。また、意思決定に際し、拘束者は被拘束者に不当な心理的影響を及ぼしてきた。
その他の事情から、被拘束者が自由意思に基づいて拘束者の下にとどまっているとはいえない特段の事情がある。
2拘束者による拘束に顕著な違法性(人身保護法2条1項、人身保護規則4条)
返還決定に基づいて代替執行の手続がされたにもかかわらず抵抗し、返還決定に従わないまま被拘束者を監護していることは明らかであり、監護を解くことが著しく不当であるような特段の事情が認められない限り、拘束には顕著な違法性がある。
拘束者は、返還決定確定後の事情の変更(ハーグ条約実施法117条1項)が認められる事案であり、返還決定の変更申立てを行うことを検討しているとしたが、被拘束者が日本の生活に順応しているといった主張内容は条約実施法117条1項の事情の変更に当たらない。
拘束者による被拘束者に対する拘束には顕著な違法性がある。
以上より、判決は、請求を認め、拘束者に対し、被拘束者を釈放し、請求者への引渡しを命じた。
2018.3.15
ハーグ条約実施法に基づく返還決定後人身保護請求を棄却した原判決を破棄し差し戻した事例
[最高裁第一小法廷2018(平成30)年3月15日判決 民集72巻1号17頁、判タ1450号35頁、判時2377号47頁、家庭の法と裁判15号65頁、LEX/DB25449323]
[事実の概要]
いずれも日本国籍を有する父母は1994年に婚姻し、長男(1996年生)、長女(1998年生)をもうけたあと、2002年ころ家族4人で米国に移住した。二男は、2004年米国で出生した(国籍留保の届出をし、米国籍と日本国籍の重国籍)。
父母の関係は2008年ころから悪化し、2016年1月、母は父の同意を得ることなく、二男(当時11歳3か月)を連れて日本に入国し、以後日本で二男とともに暮らし、監護している。
父は2016年7月、東京家庭裁判所にハーグ条約実施法27条の基づく返還命令の申立てをした。同年9月、同家庭裁判所は、母に対し、返還命令の決定をし、返還決定はその後確定した。
父は返還決定に基づき、東京家庭裁判所に子の返還の代替執行の申立てをし、子の返還を実施させる決定(実施法134条1項、138条)を得た。
執行官が2017年5月、母の住居において、実施法140条1項に基づく母による子の監護を解くための必要な行為をしたが、母は激しく抵抗した。二男は執行官に対し、日本にいることを希望し、米国には行きたくないと述べた。執行官は子の監護を解くことができないとして、解放実施に係る事件を終了させた。
父は、米国カリフォルニア州上位裁判所において、離婚の訴えとともに、二男についての監護等に関する命令を求めた。2017年8月、同裁判所は、父が二男についての監護を単独で行うことなどを内容とする命令をした。
本件は、父が母により二男である被拘束者が法律上正当な手続によらないで身体の自由を拘束されていると主張して、人身保護請求を求めた事案である。原審である名古屋高等裁判所は、二男(被拘束者)が現在日本での生活環境になじんでいること、判断能力が欠けているなどという事情はうかがわれないことなどから、自由な意思に基づいて日本にいることを希望する旨の意思を表明したというべきであるとし、母(拘束者)の二男に対する監護が人身保護法・同規則にいう拘束に該当するとは認められず、父(請求者)の請求は、二男の自由に表示した意思に反するとした。また、母による監護が上記拘束に当たるとしても、違法性が顕著ではないとし、父の請求を棄却した。
父が上告。
[判決の概要]
1 被上告人の被拘束者に対する監護が人身保護法及び同規則にいう拘束に当たるか否か等
「意思能力がある子の監護について、当該子が自由意思に基づいて監護者の下にとどまっているとはいえない特段の事情のあるときは、上記監護者の当該子に対する監護は、人身保護法及び同規則にいう拘束に当たると解すべきである(最高裁第二小法廷昭和61年7月18日判決民集40巻5号991頁)。本件のように、子を監護する父母の一方により国境を越えて日本へ連れ去りをされた子が、当該連れ去りをした親の下にとどまるか否かについての意思決定をする場合、当該意思決定は、自身が将来いずれの国籍を選択することになるのかという問題と関わるほか、重国籍の子にあっては将来いずれの国籍を選択することになるのかという問題とも関わり得るものであることに照らすと、当該子にとって重大かつ困難なものというべきである。また、上記のような連れ去りがある場合には、一般的に、父母の間に深刻な感情的対立があると考えられる上、当該子と居住国を異にする他方の親との接触が著しく困難になり、当該子は、上記の意思決定をするために必要とされる情報を偏りなく得るのが困難な状況に置かれることが少なくないといえる。これらの点を考慮すると、当該子による意思決定がその自由意思に基づくものといえるか否かを判断するに当たっては、基本的に、当該子が上記の意思決定の重大性や困難性に鑑みて必要とされる多面的、客観的な情報を十分に取得している状況にあるか否か、連れ去りをした親が当該子に対して不当な心理的影響を及ぼしているかなどといった点を慎重に検討すべきである。」
被拘束者は現在13歳で意思能力が認められる。しかし、本件の事情に鑑みると、被拘束者は、被上告人の下にとどまるか否かについての意思決定をするために必要とされる多面的、客観的な情報を十分に取ることが困難な状況に置かれている。被上告人は、被拘束者に対して不当な心理的影響を及ぼしている。
以上より、拘束者が自由意思に基づいて監護者の下にとどまっているとはいえない特段の事情があり、被上告人の拘束者に対する監護は、人身保護法及び同規則にいう拘束に当たる。
2 被上告人による拘束に顕著な違法性(人身保護法2条1項、人身保護規則4条)があるか否か
「国境を越えて日本への連れ去りをされた子の釈放を求める人身保護請求において、実施法に基づき、拘束者に対して当該子を常居所地国に変換することを命ずる旨の終局決定が確定したにもかかわらず、拘束者がこれに従わないまま当該子を監護することにより拘束している場合には、その監護を解くことが著しく不当であるような特段の事情のない限り、拘束者による当該子に対する拘束に顕著な違法性があるというべきである。」
本件の事情に鑑み、被上告人による被拘束者に対する拘束には、顕著な違法性がある。
以上より、原審には法令違反があるとして、破棄した上、被拘束者の法廷への出頭を確保する必要がある点を考慮し、原審に差し戻した。
2017.12.21
ハーグ条約実施法に基づく返還命令の決定は、確定後の事情変更により維持することが不当になったとして、変更し、申立てを却下した事例
[最高裁第一小法廷2017(平成29)年12月21日決定 判タ1449号94頁、判時2372号16頁、家庭の法と裁判15号84頁、LEX/DB25449155]
[事実の概要]
父母と子ら4名(2014年当時、6歳5ヶ月から11歳7ヶ月)は米国で同居していたが、2014年7月、母は父に同年8月中に米国に戻る旨約束して子らを連れて日本に入国し、子らとともに母の両親宅に居住している。母は父から同年9月以降もしばらく日本にいるように言われ、父の了承を得て子らをインターナショナルスクールに入学させたが、その後米国への帰国について父母間で意見が対立するようになり、2015年8月、子らについてハーグ条約実施法26条による子の返還の申立てをした。申立てに係る手続において、年長の2子は、返還を強く拒絶し、年少の2子も拒否的な意見を述べたほか、子ら全員兄弟姉妹で離れることを望まなかった。また父はそのころには監護養育のための経済的基盤を有していなかった。
2016年1月、大阪高裁は、年長の2子については実施法28条1項5号の返還拒否事由があると認めながら、同項ただし書の規定を適用すべきものとし、年少の2子については、実施法28条1項4号5号の返還拒否事由がないとして、子ら全員を米国に返還するよう命ずる決定(変更前決定)をした(同月確定)。
父が子らの返還の代替執行を申し立て、同年9月、執行官が子らに対し説得を行って子らを父に面会させようとしたり、年長の2子と父との間で会話させたりしたが、執行不能により終了させた(ハーグ条約実施法による子の返還に関する事件の手続等に関する規則89条2号)。
[決定の概要]
抗告人(父)は、「変更前決定の確定後、居住していた自宅を明渡し、それ以降、本件子らのために安定した住居を確保することができなくなった結果、本件子らが米国に返還された場合の抗告人による監護養育態勢が看過し得ない程度に悪化したという事情の変更が生じたというべきである。そうすると、米国に返還されることを一貫して拒絶している長男及び二男について、実施法28条1項5号の返還拒否事由が認められるにもかかわらず米国に返還することは、もはや子の利益に資するものとは認められないから、同項ただし書により返還を命ずることはできない。」また、長女及び三男のみを米国に返還すると、子らを日米に分離する結果を生ずることになる等一切の事情を考慮すれば、同項4号の返還拒否事由があると認められる。
以上より、変更前決定は、その確定後の事情の変更によってこれを維持することが不当となるに至ったとして、実施法117条1項により変更し、申立てを却下するのが相当である。
原審の判断は是認できるとして、抗告を棄却した。
小池裕裁判官の補足意見がある。
[ひとこと]
外務省によれば、実施法117条1項に基づく初の申立てとのことである(読売新聞2017年12月28日10時09分配信)。
2017.9.15
ハーグ条約実施法に基づき、父が母に対し、子をシンガポールに返還するように求めた事案において、父の暴力につき同国で個人保護命令が発令されているが、その後父が同命令に反する行動をとっていない等により、返還拒否事由は認められないとして、子の返還が命じられた事例
[大阪高裁2017(平成29)年9月15日決定 判例時報2372号40頁、家庭の法と裁判16号91頁、LEX/DB25560926]
[事実の概要]
X(夫・シンガポール国籍)とY(妻・日本国籍)は2014年婚姻し、長女(2014年生)をもうけた。長女は出生以来、XY夫婦と一緒にシンガポールで生活していた。Yは2016年長女を連れて日本に帰国し、以降、わが国で生活している。現在、長女のシンガポールへの渡航は妨げられている(本件留置)。XはYに対し、2017年、ハーグ条約実施法に基づき、長女をシンガポールに返還するよう求めた。原審は、返還拒否事由は認められないとして、Yに対し長女の返還を命じた。これに対し、Yが抗告した。
[決定の概要]
返還拒否事由があるかにつき、①重大な危険(法28条1項4号)について、Yはシンガポールの個人保護命令にはXのYに対する暴力を防ぐ効果がないと主張するが、Yは日本に帰国後も保護命令の審理や長女との面会交流のためにシンガポールに複数回入国しているが、Xはその間保護命令に反する行動をとっておらず、そこに一定の抑止効果を認めることができる。また、Yは長女がシンガポールに返還されるとその心身に重大な害悪が生じる、YのPTSDが悪化するなどと主張し、意見書、診断書を提出するが、意見書は医師としての具体的な診断結果に基づくものではなく、長女がシンガポールに返還されれば長女の心身に重大な害悪が生じることが予想されるとか、その可能性をいうにすぎず、診断書についても、YのPTSDが悪化すると予想されるとか、Xが長女に暴力を振るうなどの可能性を指摘するにすぎないから、いずれも採用できない、②監護の権利の不行使(法28条1項2号)について、Xが長女を監護し得なかったのは、Yがシェルターに入所してXに居所を秘匿していたからであり、Xが監護の権利を放棄したのではない、③本件留置に係る承諾(法28条1項3号)について、Xが本件留置を事後に承諾したとみることはできないとして、Yに対し長女の返還を命じた原決定は妥当であるとして、Yの抗告を棄却した。
2017.2.24
[大阪高裁2017(平成29)年2月24日決定 判タ1461号132頁]
父から母に対し、ハーグ実施法に基づき、子を常居所地国であるオーストラリア連邦に返還することを求めたところ、当事者がオーストラリアと日本を行き来していたこと等から常居所地国がいずれであるかが争点となり、常居所地国はオーストラリア連邦ではないとして申立てを棄却した例
2015.1.30
ハーグ条約に基づき、スリランカに住む男性が、西日本で暮らす妻に、5歳の娘のスリランカへの返還を求め、返還が認められた事例
[大阪高裁2015(平成27)年1月30日決定 同月31日付産経新聞(大阪)朝刊]
[大阪家裁2014(平成26)年11月19日決定 法学教室№412・179頁]
[事実の概要]
夫の仕事のため2013年2月より夫婦と娘はスリランカに移住していたが、2014年6月、3人は一時帰国した。再び3人でスリランカに戻る予定であったが、妻は夫に戻る意思がないことを伝え、夫のみがスリランカに戻り、別居するようになった。夫、妻、娘はみな日本人。夫は妻に娘の返還を求めたが、話し合いが決裂したため、2014年10月16日、ハーグ条約(「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約」)に基づき、娘のスリランカへの返還を求めて大阪家裁に申立てをした。同家裁は返還を認める決定を言い渡した。妻はこれを不服として、大阪高裁に即時抗告した。
[決定の概要]
原審では、スリランカが、ハーグ条約に基づいて連れ去られた子が原則戻る国とされる「継続的に居住していた国」に該当するかが争われたが、子が継続的に居住していた国に該当するかどうかは、「居住年数や目的、状況などを総合的に考慮し、個別に判断すべき」としたうえで、娘が帰国後も現地の学校に通学する予定であったことなどから、スリランカが「継続的に居住する国」に該当すると判断した。妻側は、娘をスリランカに戻せばその心身に悪影響を及ぼしかねないと主張したが、原審はこれを排斥し、返還を命じた。大阪高裁は、一審決定を支持し、妻の即時抗告を棄却した。
[ひとこと]
本件は、国内の裁判所による返還命令が公表された初めてのケースである。
|
 |
 |
|
|



