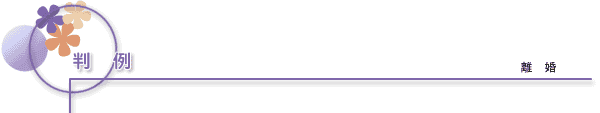 |
|
3−財産分与
3−1 分与割合
裁判や調停の実務では、夫婦で財産を分けるときの割合は、原則2分の1とされている。ただし、特殊な才能等により高額の収入が得られた場合には、下記の裁判例のように修正されることがある。普通のサラリーマンでは修正はまずない。96年の法務省の民法改正案は、「各当事者の寄与の程度は、その異なることが明らかでないときは等しいものとする」としている。
3−1−2017.3.2
相手方が当選した宝くじの当選金を原資とする資産は夫婦共有財産であるとし、分与割合については、相手方が小遣いの一部を充てて宝くじの購入を続けて本件当選金を取得したこと等に鑑み、申立人を4、相手方を6とした事例
[東京高等裁判所2017(平29)年3月2日決定 判時2360号8頁、判タ1446号114頁、家庭の法と裁判13号71頁]
[事実の概要]
原審相手方(夫)は、毎月の小遣いから宝くじを購入していたところ、宝くじの当選により2億1000万円を得た。原審相手方は、この当選金を充てて住宅ローンを完済し、当選金を原資とする預貯金や保険を有していた。本件において、①宝くじの当選金又はこれを原資とする資産が夫婦共有財産といえるか、②宝くじの当選金を原資とする資産が夫婦共有財産である場合における分与の割合が争われた。
[判決の概要]
原審(前橋家裁高崎支部平2016(平成28)年9月23日審判)は、①について、当選金又はこれを原資とする資産の一部を原審相手方の特有財産とし、②これ以外の夫婦共有財産部分について、2分の1の割合で分与した。
これに対し、抗告審は、①について、宝くじの「購入資金は、夫婦の協力によって得られた収入の一部から拠出され、本件当選金も家族の住居費や生活費に充てられたのだから、本件当選金を原資とする資産は、夫婦の共有財産と認めるのが相当である」として、当選金又はこれを原資とする資産の全部を夫婦共有財産とした。
そのうえで、②「原審相手方が自分で、その小遣いの一部を充てて宝くじ等の購入を続け、これにより偶々とはいえ当選して、本件当選金を取得し、これを原資として…資産が形成された」との「事情に鑑みれば、資産形成については、原審申立人より原審相手方の寄与が大きかったというべき」であるとして、原審申立人を4、原審相手方を6の割合で分与した。
3−1−2014.3.13
医療法人の夫婦各名義の出資持分のほか、夫の母名義の出資持分も財産分与の対象になるとしたうえで、本件医療法人の純資産評価額の7割相当額をもって出資持分の評価額とし、さらに、高額な収入の基礎となる特殊な技能が、夫の婚姻前の個人的な努力によって形成され、婚姻後もその才能や労力によって多額の財産が形成されたことを理由に寄与割合を夫6対妻4とした事例
[大阪高裁2014(平成26)年3月13日判決 判タ1411号177頁、LEX/DB25540391]
[事実の概要]
1986(昭和61)年 夫が医師資格を取得。
1992(平成4)年 婚姻届出 以後、長男及び二男を設ける。
婚姻後 夫が診療所を開設し、その後法人化。
2010(平成22)年4月 妻が夫に対し、神戸家裁伊丹支部に離婚等請求訴訟を提起。
同年6月 夫が離婚請求等反訴を提起。
2012(平成24)年12月20日判決。
夫も妻も判決を不服として控訴(妻は附帯控訴)した。
[判決の概要]
控訴審での争点は多岐に亘るが、以下、財産分与についての判断(本件医療法人につき何を財産分与の対象財産とするか、評価のあり方、寄与割合)について概要を紹介する。
◎何を財産分与の対象財産とするか
「本件医療法人が所有する財産は、婚姻共同財産であった法人化前の診療所に係る財産に由来し、これを活用することによってその後増加したものと評価すべきである。そうすると、控訴人(夫)名義の出資持分2900口のほか、形式上控訴人の母が保有する出資持分50口及び被控訴人(妻)名義の出資持分50口の合計3000口が財産分与の対象財産になる」
「本件医療法人が控訴人と被控訴人の婚姻届出後に開設され、控訴人が経営してきた旧診療所を引き継いだ本件診療所を法人化して設立されたものであることなどを考慮すると、控訴人の母名義の出資持分をも財産分与の対象財産とするのが婚姻届出後別居時までに形成された婚姻共同財産を清算するという財産分与制度の趣旨目的に副うものというべきである」
◎評価のあり方
「本件医療法人の出資持分の評価額を算定するに当たっては…本件医療法人の純資産評価額の7割相当額をもって出資持分3000口の評価額とするのが相当である」
◎寄与割合
「控訴人が医師の資格を獲得するまでの勉学等について婚姻前から個人的な努力をしてきたことや、医師の資格を有し、婚姻後にこれを活用し多くの労力を費やして高額の収入を得ていることを考慮して、控訴人の寄与割合を6割、被控訴人の寄与割合を4割とすることは合理性を有する」
[ひとこと]
原則5:5の寄与割合を6:4に修正したケースである。なお、養育費の終期(離婚時未成年)を22歳に達した後最初に到来する3月としている点(原審も同じ)も注目される。
3−1−2004.6.18
財産分与につき、同族会社資産も清算対象とし、寄与率を2分とし、詳細な認定がなされた事例
[裁判所]広島高裁岡山支部
[年月日]2004(平16)年6月18日判決
[出典]判時1902号61頁
[事実の概要]
原告妻と被告夫は、昭和48年11月婚姻、平成9年11月に原告が被告方を出て別居した。娘3人息子1人がいる。夫婦は協力して自動車修理業を営んできた。夫には不貞、妻への暴力があり、しつけとして息子の手に火のつい煙草をおしつけたり、子の希望しない高校へ無理に行かせるなどの行為もあった。
[判決の概要]
夫に対し、慰謝料500万円、弁護士費用50万円の支払いを命じ、財産分与として同族会社資産も含めて清算対象として妻の寄与率5割を乗じ、妻の取得分を約3億2639万円と算出。不動産の分配等具体的な取得方法を命じた。
同族会社の財産については、「丙川社は、一審原・被告が営んできた自動車販売部門を独立するために設立され、丁原社は、一審原・被告が所有するマンションの管理会社として設立されたものであり、いずれも一審原・被告を中心とする同族会社であって」と記述し、寄与率については、「一審原・被告がその経営に従事していたことに徴すると、上記各会社名義の財産も財産分与の対象として考慮するのが相当である・・一審原告が家事や四名の子の育児に従事しながら、一審被告の事業に協力し続け、資産形成に大きく貢献したことに徴すると、一審原告の寄与率は五割と解され」と述べた。
3−1−2003.9.26
共有財産の原資のほとんどが夫の特有財産であり、その管理・運用も夫が行っていた事案において、婚姻関係破綻の原因が主として夫にあるとした上で、妻に対する扶養的な要素を加味し、財産分与額を、婚姻関係夫婦共有財産の価格合計の5%とした事例
[東京地裁2003(平成15)年9月26日判決 LLI/DB L05833916]
[事実の概要]
原告(夫)は、東証一部上場会社である株式会社を初めとする多くの会社の代表者で、社団法人、財団法人等の多くの理事等を占めていた。
原告は、被告(妻)と、1980(昭和55)年以降生活を共にするようになり、1983(同58)年に婚姻届出をしたが、その間に、以下のような誓約書を作成した。
一,離婚に対する財産分与について
将来甲乙お互いにいずれか一方が自由に申し出ることによって、いつでも離婚することができる。
(一)甲の申し出によって協議離婚した場合は左記の条件に従い乙より財産の分与を受け、それ以外の一切の経済的要求をしない。
※以下、略
(二)尚、乙の申し出によって協議離婚した場合は前項、第(一)項の金額の倍額とする
※以下、略
原告と被告の婚姻関係は、主として原告の不貞や原告の被告に対する暴行により破綻した。
原告は、被告との離婚を求める訴訟を提起した。被告は反訴を提起し、原告との離婚を求めるとともに、別居開始当時の巨額な財産のほぼ半額を、慰謝料も加味した財産分与として、その分与を求めた。
[判決の概要]
1誓約書について
本件誓約書は、将来、離婚という身分関係を金員の支払によって決するものと解されるから、公序良俗に反し、無効である。
予備的に、「協議離婚、裁判離婚を問わず、最終的に、離婚が定まった場合に、原被告のいずれかが申し出たかによって、将来の財産分与額を定めた婚姻財産契約であると」と解釈することは、本件誓約書の明確な文言に反する。仮に、かかる解釈が可能で、かつ、他の無効事由が認められないとしても、本件誓約書が、協議離婚の場合しか想定していないことは明らかである。したがって、本件誓約書は、裁判離婚が問題となっている本件においては効力はない。
2原告の財産形成に対する被告の寄与の有無、程度について
(1)財産分与の対象財産
被告の寄与が問題となるのは、被告と原告が継続的な同居を始めた昭和55年以降と解するのが相当であり、原則として、その後原告が取得した財産が、分与の対象となる共有財産となり得る。その取得原資のほとんどが、原告の特有財産である点は、被告が取得すべき財産分与を算定する際の事情として考慮すれば足りる。
また、原告は、巨額の特有財産を有しているが、それについても、被告がその維持に寄与している場合には、財産分与を認めるのが相当である。
(2)被告の寄与の有無・程度
被告は、成功した経営者、財界人である原告の、公私に亘る交際を妻として支え、精神的にも原告を支えたことからすると、間接的には、共有財産の形成や特有財産の維持に寄与したことは否定できない。
しかし、共有財産の原資はほとんどが原告の特有財産であったこと、その運用、管理に携わったのも原告であること等からすると、被告が原告の共有財産の形成や特有財産の維持に寄与した割合は必ずしも高いと言いがたい。
婚姻が破綻したのは、主として原告の責任によるものであること、被告の経歴からして、職業に携わることは期待できず、今後の扶養的な要素も加味すべきことを考慮に入れると、財産分与額は、共有財産の価額合計約220億円の5%である10億円を相当と認める。
3−1−2001.12.26
退職金等について妻がその維持形成に寄与したのは同居期間のみであるとした例
[裁判所]横浜家裁
[年月日]2001(平成13)年12月26日審判
[出典]家月54巻7号64頁
[事案の概要]
99年に協議離婚した元妻から元夫に対し財産分与請求がなされた。退職金1761万円は、勤務した12年2カ月を対象としたものだが、そのうち、夫婦が同居してその維持形成に寄与したのは5年8ヶ月。「その同居期間だけを寄与期間と計算すべきである。そうすると、1761万円に寄与期間率(0.4658)を乗じた820万円が計算の基礎となるところ、申立人の妻の寄与率について2分の1を下回るべき特段の事情は認められないから、それを乗ずると410万円になる。」とした。
[コメント]
退職金についても、妻が寄与したのは同居期間に対応する分のみとする扱いは、ほぼ定着。
3−1−2000.3.8
海上勤務の夫の寄与割合を高く認めた例
[裁判所]大阪高裁
[年月日]2000(平成12)年3月8日判決
[出典]判時1744号91頁
[事案の概要]
夫が1級海技士の資格を持ち、1年に6ヶ月ないし11ヶ月の海上勤務をするなど海上勤務が多かったことから多額の収入を得られ、一方妻は主婦であった事案において、「資格を活用した結果及び海上での不自由な生活に耐えたうえでの高収入であれば夫の寄与割合を高く判断することが相当である」として、妻の寄与割合を3割とし、夫から妻に対する2300万円の財産分与を認めた事例
[コメント] 分与割合3割というのは、現在では極めて例外的。
3−1−1994.5.31
芸術家夫婦の財産分与につき、妻の家事労働を評価し、妻の寄与を6割を認めた事例
[裁判所]東京家裁
[年月日]1994(平成6)年5月31日審判
[出典]家月47巻5号52頁 判タ臨時増刊913号140頁 民商法116巻3号139頁
[事実の概要]
妻が、協議離婚した夫に対して、財産分与及び慰謝料として不動産についての所有権(共有持分権)移転登記手続を求めた。
[判決の概要]
清算的財産分与の清算割合は、本来、夫婦は基本的理念として実質上の共有財産の清算と解するのが相当であるから、原則的には平等であると解するべきであるが、妻と夫の婚姻生活の実態によれば、妻と夫は芸術家としてそれぞれの活動に従事するとともに、妻は家庭内別居の約9年間を除き約18年間専ら家事労働に従事してきたこと、及び当事者双方の共同生活について費用の負担割合、収入等を総合考慮すると、前記の割合を修正し、妻の寄与割合を6、夫のそれを4とするのが相当である。
3−1−1987.7.17
将来妻が住宅ローンの返済をしていくこととなる高度の蓋然性等を考慮した上、不動産に対する夫の共有持分全部を妻に分与した事例
[裁判所]大阪家裁
[年月日]1987(昭和62)年7月17日審判
[出典]家月39巻11号135頁
[事実の概要]
金融機関からの借入金をもって不動産を取得した不動産を財産分与の対象とする場合にその価額を評価するに当たり、それまでに支払った前記借入金の割賦弁済金の総額をその価格とみるのは相当でなく、支払利息を控除した元金充当分の合計額が当該不動産の実質的価値を表しているとみるのが相当であるとして、その合計額の2分の1の金額の財産分与を命じた。
[判決の概要]
離婚に伴う財産分与において、清算の対象となる不動産の取得のための借入金が未だ完済されていなかった場合に、夫と共に連帯債務者となっている妻が、主としてこれを支払い、離婚後も専らこれを弁済していく高度の蓋然性があるという事情を考慮し、かつ、離婚後についての夫の有責性をも慰謝料的要素として考慮した上、前記不動産に対する夫の2分の1の共有持分全部を妻に分与した。
3−1−1985.9.5
金融機関からの借入金をもって不動産を取得し、同借入金を割賦弁済中である場合に、当該不動産を財産分与の対象とするときの評価方法について判示した事例
[裁判所]名古屋高裁金沢支部
[年月日]1985(昭和60)年9月5日決定
[出典]家月38巻4号79頁
[事実の概要]
金融機関からの借入金をもって不動産を取得した不動産を財産分与の対象とする場合にその価額を評価するに当たり、それまでに支払った前記借入金の割賦弁済金の総額をその価格とみるのは相当でなく、支払利息を控除した元金充当分の合計額が当該不動産の実質的価値を表しているとみるのが相当であるとして、その合計額の2分の1の金額の財産分与を命じた。
[ひとこと]
支払利息は金員借入のための対価として債権者に支払われたものであり、借主から見れば経費として費消してしまったものとの判断がなされている。2010年現在の判例は、支払い割賦金総額を現在価値に換算して評価するもの、支払い済み元金部分のみで評価するもの、というように、事案ごとの事情により判断は分かれている。
3−1−1967.11.14
離婚につき双方に責任がある場合の財産分与審判の1事例
[裁判所]新潟家裁
[年月日]1967(昭和42)年11月14日審判
[出典]家月20巻7号49頁、判タ233号209頁
[事実の概要]
妻は、夫が、女性関係につき極めて自由な考え方を持ち、売春婦と機会ある毎に接触するのをみて、結婚当初より心よからず思っていた。夫が、夫妻の経営する美容店に客として出入りしていた女性と肉体関係を結ぶ等したことから、妻は、自殺を企てるまでに至り、そのうち、夫以外の男性と公然と交際し始めた。夫は、不貞を行った妻に暴力を振るい、そのことから夫妻は別居となり、離婚調停が成立し、財産分与審判が行われた。
夫は、離婚は妻の不貞行為に原因するものである等の理由から、妻に対して財産分与する必要はないと主張した。
[判決の概要]
当事者が離婚するに至った直接の原因は妻の不貞行為によるものと一応言えるかもしれないとしつつも、長年にわたる、妻の存在を無視した夫の節度のない女性関係が大きな影響を与えていることは明らかであるから、当事者の離婚には双方ともその責任を負わねばならないとした。
そして、夫妻が経営する美容室の基礎を築いたのは妻の手腕力量に負うところが多大であること、夫妻共有名義の建物(借用金残額あり。)についての妻の有形、無形の内助の功も十分評価すべきこと等をあげ、夫の要求は独断に満ちているとの評価を下した上、一切の事情を考慮して財産分与の額及び方法を検討し、前記建物及び夫名義の土地について、夫の単独所有とするかわりに、夫から妻へ現金を支払う等の財産分与を認めた。
3−2 将来の退職金
将来の退職金は、受領できる蓋然性が高い場合には、夫婦の婚姻期間(同居期間)に対応する分について財産分与の対象となるとする判例はほぼ定着した。ただし、現実にまだ受給していないので、その額の計算方法や、支払い方法(現在の支払いか受給時の支払いか)については判例は分かれている。寄与割合は同居期間に対応する分の2分の1とする例がほとんどである。
3−2−2007.1.23
離婚後5年以内に支給される見込みがある退職金の財産分与について、原審は退職時に一定額を支払うよう命じたが、控訴審はこれを変更し、退職金手取額と退職時期を変数とする計算式による計算により算出された金額を退職時に支払うことを命じた例
[裁判所]大阪高裁
[年月日]2007(平成19)年1月23日判決
[出典]判タ1272号217頁
[事実の概要]
夫(昭和26年生 55歳)と妻(昭和32年生 48歳)は、昭和63年に婚姻し、同年に出産した娘(18歳)がいる。夫が妻に対して離婚訴訟を提起し、妻が反訴し、財産分与を求めた。原審は、離婚を認め、財産分与の判断の中で退職金について、夫が退職金を支給されたときに550万円を支払うことを命じた。妻が控訴し、夫も付帯控訴した。控訴審は原判決を変更し、以下のように命じた。
[判決の概要]
夫婦の間の婚姻期間中の財産形成についての寄与割合2分の1、現時点で退職した場合の勤続期間約30年、別居までの婚姻期間はその勤続期間の2分の1の約15年であるから、仮に、現時点で退職した場合には、被控訴人は、控訴人に対し、退職手当が支給されたときに、実際に支給される退職手当(ただし、所得税及び住民税の徴収額を控除した額)の4分の1の割合の額を財産分与として支払うこととするのが相当である。すなわち、勤続期間に占める婚姻同居期間の割合2分の1に、夫婦間の寄与割合2分の1を掛けて得られる4分の1の割合の財産分与をするのが相当であるからである。
ただし、現時点で退職した場合の支給割合は、基準俸給額の100分の5000(50か月分)であるが、平成19年3月以降に退職する場合には、勤続期間が31年になり、以後勤続期間1年につき支給割合100分の100(1か月分)増えることになる。そして、勤続期間が今後31年を超えることにより支給割合が増えることによる退職手当の増加については、控訴人の寄与はない。そして、この勤続期間の増加による支給割合の上昇は、支給割合が100分の5500(55か月分)に達するまで認められている。
そうすると、勤続期間が30年を超えて退職した場合には、実際に支払われる退職手当のうち、勤続期間30年の場合の支給割合(100分の5000)に相当する退職手当の額に対し、上記4分の1の割合を掛けるのが相当である。
・・・以上によれば、被控訴人が控訴人に対し、退職手当の財産分与として支払うべき額は、別紙1「退職手当財産分与計算式」記載の計算式によって求められる退職手当財産分与額のとおりとなる。
(別紙1)退職手当財産分与計算式
退職手当財産分与額=退職手当支給額(ただし、所得税及び住民税の徴収額を控除した額)÷4×50÷A
計算式の説明:Aは、被控訴人が中小企業金融公庫を退職した時期に応じて次の数値を用いる。
平成19年2月以前に退職した場合 A=50
平成19年3月以降、平成20年2月以前に退職した場合 A=51
平成20年3月以降、平成21年2月以前に退職した場合 A=52
平成21年3月以降、平成22年2月以前に退職した場合 A=53
平成22年3月以降、平成23年2月以前に退職した場合 A=54
平成22年3月以降退職した場合 A=55
[ひとこと]
原審も控訴審も、支払時期を退職時とした点は同じであるが、原審が一定額の支払いを命じたのに対し、控訴審は退職金の支給額が退職時期に応じて変動することから、退職時期を変数とする計算式を定め、これによって定まる金額の支払いを命じた。この件の就業規則に即した計算式であるので一般化はできないが、退職金の算定方法の珍しい1例である。
3−2−2000.12.20
将来の退職金につき、現在自己都合により退職した場合の退職金試算額のうち同居期間に対応する907万円、将来定年退職した時(9年後に定年)のそれが1160万円、年金の存在などを考慮し、将来退職手当を受けたときに550万円を支払うことを命じた例
[裁判所]名古屋高裁
[年月日]2000(平成12)年12月20日判決
[出典]判タ1095号233頁
3−2−1999.9.3
夫が退職時に受給する額から、中間利息を複利計算で控除して現在の額に引きなおし、その5割に相当する額を妻に分与することを命じた例
[裁判所]東京地裁
[年月日]1999(平成11)年9月3日判決
[出典]判時1700号79頁
3−2−1998.3.18
将来の退職金を清算対象とし、他の清算も差し引きして計算し、受領時に金500万円を支払うことを命じた例
[裁判所]東京高裁
[年月日]1998(平成10)年3月18日判決
[出典]判時1690号66頁
[コメント]横浜地裁1997(平成9)年1月22日判決の控訴審判決。定額とした。
3−2−1998.3.13
7年後に夫が受領する退職金の4割の支払いを命じた例
[裁判所]東京高裁
[年月日]1998(平成10)年3月13日決定
[出典]家月50巻11号81頁
[コメント]退職金も分与割合2分の1とする例が圧倒的。4割というのは珍しい。
3−2−1997.1.22
夫が(将来)退職金を受領したとき、その受領金額の2分の1を払うことを命じた例
[裁判所]横浜地裁
[年月日]1997(平成9)年1月22日判決
[出典]判時1618号109頁
[コメント] 将来の受領時に支払うことを命じている。
3−3 退職金と年金方式部分
3−3−1999.7.30
退職金につき、年金方式部分について解約した場合の受取金を合算して計算し、その5分の2につき、財産分与を命じた例
[裁判所]横浜地裁相模原支部
[年月日]1999(平成11)年7月30日判決
[出典]判時1708号142頁
3−4 年金
2004年6月、離婚時年金分割を認める法改正があった。2007年4月から合意・審判・判決による報酬比例部分の分割が可能になり(合意分割)、2008年4月からは、それ以降の3号被保険者期間における報酬比例部分の2分の1が当然分割になった(3号分割)。判例は、対象期間における保険料納付に対する夫婦の寄与の程度は特別の事情のない限り互いに同等とみるのが制度の趣旨と解している。改正前には大阪高裁及び東京高裁等で年金を原資として定期金払いを財産分与として認めるとの確定判例があった。なお、年金分割制度は財産分与とは別の制度として作られた。企業年金の分割については今後も財産分与の中で問題になりうる。
3−4−2019.8.21
婚姻後約9年間同居後、約35年間別居し離婚したケースにつき、年金分割についての請求すべき按分割合を0.5とした事例
[大阪高裁2019(令和元)年8月21日決定 判例時報2443号53頁]
[事実の概要]
婚姻後約9年間同居後、約35年間別居し離婚した事案につき、原審は、保険料納付に対する夫婦の寄与を同等とみることが著しく不当であるような例外的な事情がある場合に当たるとして、年金分割について請求すべき按分割合を0.35としたため、抗告人が即時抗告した。
[判決の概要]
抗告人と相手方の婚姻期間44年間中、同居期間は9年間程度にすぎないものの、夫婦は互いに扶助義務を負っているのであり(民法752条)、このことは夫婦が別居した場合においても基本的に異なるものではなく、老後のための所得保障についても夫婦の一方又は双方の収入によって、同等に形成されるべきものである。抗告人と相手方が別居するに至ったことや別居期間が長期間に及んだことについて、抗告人に主たる責任があるとまでは認められないことを併せ考慮すれば、別居期間が長期間に及んでいることをしん酌しても、特別の事情があるということはできず、按分割合を0.5と定めるのが相当である。
3−4−2013.10.1
元夫が元妻に対し、離婚成立後に申し立てた私学共済年金に関する年金分割について、按分割合が0.3と定められた例
[東京家裁2013(平成25)年10月1日審判 判時2218号69頁]
[審判の概要]
審判は、①申立人(元夫)が1000万円単位の負債を負う等、相手方(元妻)が家計のやりくりに苦労したであることが認められること、②申立人が退職後も生活費を負担したが家計を維持するには不足しており、相手方が専任教員として勤務するようになってからは、相手方の収入を主として家計を維持されていたことの各事実を認めつつ、③申立人は婚姻中の33年間、一部上場企業に勤め、相当額の収入を得ており、1000万円単位の借入金も大部分は退職金で返済したこと、④相手方は、婚姻期間約50年間のうち30年近くは専業主婦であり、その間の家族の生計は、申立人の給与収入により維持されていたこと、⑤退職金額を双方が明らかにしていないこと、⑥前件離婚調停では、相手方自身の判断で財産分与について合意していること、その他一切の事情を考慮して、年金分割の按分割合を0.3と定めるのが相当であるとした。なお、本審判より前に、元妻が元夫に対して申し立てた夫加入の厚生年金の分割については、割合を0.5とする審判が確定していた。
[ひとこと]
離婚時年金分割との関係において、婚姻期間中の保険料等納付は、互いの協力により、それぞれの老後等のための所得保障を同等に形成していくという意味合いを有しているものと評価して、対象期間における保険料等納付に対する夫婦の寄与の程度は、特別の事情がない限り、同等とみなされている。
本事案は、請求すべき按分割合を0.3と定める審判として珍しい判断である(確定)。
3−4−2008.10.22
年金分割についての請求すべき按分割合を0.5と定めた事例
[裁判所]東京家裁
[年月日]2008(平成20)年10月22日決定
[出典]家月61巻3号67頁
[事実の概要]
XとYとは、昭和52年に婚姻し、平成19年11月に離婚の裁判が確定した。Xは、年金分割について請求すべき按分割合を0.5と主張したのに対し、Yは、Xとは平成6年から別居しており、婚姻期間約30年中のうち約13年は配偶者としてのつとめを一切せず、また長女が成人して以降の9年間は夫婦協力の事実は一切ないとして、この間のXの寄与はゼロであると主張した。
[判決の概要]
老齢基礎年金は、夫婦双方の老後等のための所得保障としての社会保障的意義を有し、離婚時年金分割制度との関係では、婚姻期間中の保険料納付は互いの協力によりそれぞれの所得保障を同等に形成してゆくという意味合いを有しているので、対象期間における保険料納付に対する夫婦の寄与は、特別の事情がない限り、互いに同等と見るのが原則である。
そして、法律上の夫婦は、互いに扶助すべき義務を負っており、別居により具体的な行為としての協力関係が薄くなっている場合であっても、老後等のための所得保障についても夫婦の収入によって同等に形成されるべき関係にある。
本件においても、仮にYが主張する事実が認められるとしても保険料納付に対する夫婦の寄与が互いに同等でない見るべき特段の事情にあたるとはいえないとして、Xの主張を認容した。
3−4−2008.6.16
当事者間に離婚時年金分割をしない旨の協議があるとして、請求すべき按分割合に関する処分の申立てを却下した事例
[裁判所]静岡家裁浜松支部
[年月日]2008(平成20)年6月16日審判
[出典]家月61巻3号64頁
[事実の概要]
XとYとは、昭和52年に婚姻し、平成19年4月に協議離婚した。Yは、これに先立つ平成16年、Yが平成18年から受領する年金について、その半分を生活費のためにXに分与することを約する覚書を作成した。その後、XとYとは、離婚に際し、平成19年から支給される共済年金は、全額Yが取得し、年金分割制度によるXの取り分はすべて放棄する旨の離婚協議書を作成した。Xは、①Yから離婚協議書を作成しないと離婚届出に印を押さないといわれたので、上記離婚協議書を作成した、②平成16年に作成された覚書で年金分割についての合意がなされていると主張した。
[判決の概要]
離婚当事者は、協議により按分割合について合意することができるのであるから、協議により分割をしないと合意することができ、上記年金分割制度を利用しない旨の合意も、公序良俗に反するなどの特別の事情がない限り、有効である。
離婚協議書の作成時には、XとYとの間に何らのトラブルもなかったこと等から、上記合意を無効とすべき事情は存在しない。
平成16年の覚書は、離婚時年金分割制度が施行される前のものであるころから、離婚時年金分割制度における合意と認めることはできないとして、申立てを却下した。
3−4−2008.3.14
年金分割についての請求すべき按分割合を0.5と定めた原審判が是認された事例
[裁判所]広島高裁
[年月日]2008(平成20)年3月14日決定
[出典]家月61巻3号60頁
[事実の概要]
原審(広島家裁平成20年2月18日審判)は、保険料納付に対する夫婦の寄与は、特別の事情がない限り、同等と見るのを原則とすべきであるとし、①約7年6ヶ月の婚姻期間のうち同居期間は約5年1ヶ月に過ぎないこと、②申立人(妻)は婚姻期間中に約840万円を浪費又は隠匿したことは、いずれも特別の事情には当たらないとして請求すべき按分割合を0.5と定めたのに対し、相手方(夫)が抗告した。
[判決の概要]
按分割合を定めるに当たって、事実上の離婚状態にあることが客観的に明白な破綻別居期間を対象の婚姻期間から除くとしても、別居したことから直ちに婚姻関係が破綻して事実上の離婚状態になっていたものとはいえず、本件でも斟酌しなければ不相当というべき明白な破綻別居期間を認定することはできない。
妻に浪費又は隠匿の事実があったとしても、当該事項は財産分与等で解決すべき事項であるから、上記特別の事情に当たるとは認められないとして、抗告を棄却した。
[ひとこと]
夫から抗告の許可を申し立てたが、最高裁第三小法廷は、平成20年9月2日、抗告を棄却した(判時2046号28頁ないし29頁参照)。
3−4−2008.2.1
年金分割についての請求すべき按分割合を0.5と定めた原審判が是認された事例
[裁判所]名古屋高裁
[年月日]2008(平成20)年2月1日決定
[出典]家月61巻3号57頁
[事実の概要]
原審(岐阜家裁平成19年12月17日審判)は、請求すべき按分割合を定めるに当たって考慮する対象期間における保険料納付に対する夫婦の寄与の程度は、特別の事情がない限り、互いの同等と見るのが相当であるところ、婚姻期間中の借金や同居期間が婚姻期間の約半分であること等の事情は、特別の事情ということはできないとして請求すべき按分割合を0.5と定めたのに対し、相手方(夫)が抗告した。
[判決の概要]
厚生年金保険等の被用者保険が有する主として夫婦双方の老後の所得保障を同等に形成してゆくという社会保障的性質及び機能に鑑みれば、厚生年金保険法78条の2第2項が規定する一切の事情を考慮するにあたっても、特段の事情がない限り、その按分割合は0.5とされるべきである。
本件では、婚姻期間332ヶ月中、単身赴任期間が155ヶ月、別居期間が31ヶ月あったが、単身赴任は仕事上の都合によるもので、そもそも別居とは異なり、特段の事情には該当せず、また、夫婦の相互扶助の欠如などによって夫婦関係が悪化して別居に至ったとしても、その期間31ヶ月にとどまり、上記制度趣旨に照らせば、特段の事情には当たらない。
抗告人(夫)の借金は、夫名義である以上、夫が負担するのは当然であり、借金が生じたことだけをもっては特段の事情には該当しないとして、抗告を棄却した。
[ひとこと]
夫から抗告の許可を申し立てたが、最高裁第三小法廷は、平成20年5月27日、抗告を棄却した(判時2046号28頁ないし29頁参照)。
3−4−2007.6.26
年金分割について、按分割合を0.5と定めた原審判が是認された事例
[裁判所]札幌高裁
[年月日]2007(平成19)年6月26日決定
[出典]家月59巻11号186頁
[事実の概要]
AとBは、昭和46年に婚姻、平成19年に調停離婚したが、Aが定年退職する前に7年間完全別居、定年退職した後、7年間家庭内別居をしていた。原審が、年金分割について、按分割合を0.5と定めたところ、Aが婚姻期間中に別居期間があることを理由に抗告をした。
[判決の概要]
婚姻期間中の保険料納付や掛金の払込みに関する寄与の程度は、特段の事情がない限り、夫婦同等とみるのが相当であるところ、婚姻期間中に別居期間(家庭内別居を含む。)がある旨の抗告人の主張は、前記特段の事情には該当しないとして、抗告を棄却した。
[ひとこと]
約36年間の婚姻期間中、14年間別居期間(家庭内別居を含む)があったとしても、年金分割の請求割合は0.5と判断している。長期間の別居期間があるケースとして、参考になる。ただし、本件は完全別居後に家庭内別居をしたという変則的な事例である。
3−4−2004.3.26(仙台地判2003.12.4の控訴審判決)
[裁判所]仙台高裁判決
[年月日]2004(平成16)年3月26日
[出典]未公表
[事案の概要]仙台地判2003.12.4に同じ
[判決]控訴棄却
[ひとこと]「年金を受給する権利も夫婦が共同で築いた財産の一部」との地裁判決を踏襲。
3−4−2003.12.4
[裁判所]仙台地裁判決
[年月日]2003(平成15)年12月4日
[出典]未公表
[事案の概要]
昭和42年に婚姻。子2人は成人。夫は公務員だったが判決時は無職。妻は専業主婦。夫から妻に対し粗暴な言動が繰り返され、骨折や頚椎捻挫の傷害を負わせた。子らに対しても暴力や精神的虐待があった。平成14年、妻はDV保護命令の発令を受け別居した。
[判決の概要]
慰藉料600万円、清算的分与として1300万円、年金収入の中から原告被告いずれかが死亡するまで月6万円の支払いを被告に命じた。
[ひとこと]
判決は、「年金を受給する権利も夫婦が共同で築いた財産の一部」と評価した。未公表だが、年金の判例の1つ。
3−4−2002.9.17
[裁判所]東京高裁
[年月日]2002(平成14)年9月17日判決
[出典]判例集未搭載
[事案の概要]
婚姻期間39年、家庭内別居がはじまってから約4年、完全な別居から1年強。妻は63歳で、夫から妻に対して離婚請求がなされた。不和の原因は双方にある。妻は夫及び夫の父の共有名義の家に住み、夫は入退院後仮住居を持ち、住所を妻に知らせていない。夫の母は妻同居しているが関係が悪い。判決は、不動産のうち夫婦財産といえる部分の半分である約279万円と、妻が死亡するまで月9万円の支払いをすることを夫に命じ、離婚を認めた。妻側は、不動産の分与を受けないと困窮すると主張したが、すでに相当額の預貯金及び退職金を分配しているので、その主張は採用しないとした。
[コメント]
双方の年金額の差額の4割の分割を認めた。東京高裁判決であり確定したので、意義は高い。これで年金の分割の判決は定着したというべきか。5割でなく4割としたのは、すでに相当額の現金が分与されていること、5割でも別居中の送金額8万円を上回ることなどを考慮したのかもしれない。不動産の明け渡しと金員の支払いを同時履行にしてもよかったのではないか?
3−4−2002.5.9
[裁判所]東京地裁
[年月日]2002(平成14)年5月9日判決
[出典]判例集未搭載
[事案の概要]
婚姻期間34年、別居6年、子供2人は成人。ただし1人は病気療養中。妻(59歳)から夫(68歳)に対する離婚請求。夫は会社経営をしていたが破綻している。婚姻中収入に比し小額の生活費しか入れず、妻に対して思いやりのない態度・暴言あり。子どもに対してもかなり冷酷な言動があった。判決として、慰謝料1,000万円、財産分与として原告(妻)死亡まで月14万5,000円を支払うことを夫に命じた例
[コメント]
夫の年金受給権は「夫婦の協力によって得られたものであるというべき」「扶養という観点からの財産分与は認めることはできない」としており、扶養的財産分与ではなく清算的財産分与として位置付けている。
3−4−2001.3.22
[裁判所]仙台地裁
[年月日]2001(平成13)年3月22日判決
[出典]判時1829号119頁
[事案の概要]
婚姻期間33年、夫に不貞・暴言・暴力あり。慰謝料700万、自宅不動産価額の2分の1の894万円のほか、将来退職共済年金が支給されたときは、その10分の3を支払うことを夫に命じた例
3−4−1999.7.30
[裁判所]横浜地裁相模原支部
[年月日]1999(平成11)年7月30日判決
[出典]判時1708号142頁
[事案の概要]
婚姻39年の夫婦につき、扶養的財産分与として今後夫の受領する年金額と妻の受領する年金額との差額の4割相当である月16万円を、妻死亡時まで夫から妻に対して支払うことを命じた例
[コメント]
控訴審では、「完全に破綻しているとまで認めるのは相当でない」として離婚請求を棄却
東京高判13(01)年1月18日判例タ1060号240頁
3−4−1999.11.10
[裁判所]大阪高裁
[年月日]1999(平成11)年11月10日判決
[出典]判例集未公表
[事案の概要]
5−4−1999.4.30の控訴審判決。慰謝料を300万円にアップし他はそのまま認め、年金分割も認めた。
[コメント]
高裁で年金分割を正面から認めた。高齢、すでに年金受給中、ということで認めやすい(認めざるをえない)状況にあったといえるのかもしれない。
3−4−1999.4.30
[裁判所]大阪地裁
[年月日]1999(平成11)年4月30日判決
[出典]判例集未公表
[事案の概要]
婚姻歴45年、夫71歳、妻68歳の高齢夫婦。破綻後6年経過。破綻の主たる原因として夫の賭事のための浪費によるサラ金のトラブルが認定されている。夫の年金は月額28万円強、妻は主婦で無収入である。2つの不動産がある。判決は、妻が長男とともに居住する方の不動産の夫の持分を妻に財産分与するとともに、慰謝料200万円、年金につき、「支給がうち切られるか被告(妻)の死亡に至るまで、毎月末日限り、金8万円ずつ支払え」とした。
3−4−1998.3.18
[裁判所]東京高裁
[年月日]1998(平成10)年3月18日判決
横浜地判平成9(97)年1月22日の控訴審判決
[出典]判時1690号66頁
[事案の概要]
双方の今後の収入や必要な支出、所有財産の状況等の諸事実を勘案して、年金について扶養的財産分与は認めないとした判例
3−4−1997.1.22
[裁判所]横浜地裁
[年月日]1997(平成9)年1月22日判決
[出典]判時1618号108頁
[事案の概要]
結婚19年、再婚、夫の年金額年591万円の事案で、扶養的財産分与として、夫から妻に対し、毎月15万円を妻死亡時まで支払うことを命じた判例
3−4−1984.12.26
[裁判所]東京地裁
[年月日]1984(昭和59)年12月26日判決
[出典]判例集未搭載
[事案の概要]
夫がギャンブル好きで、サラ金からの借金を繰り返し自宅も借金返済のために売却しその後夫は行方不明、夫の唯一の財産が将来得る年金という事案で、夫が平均余命まで生きた場合の支給年金額の合計額から利子を控除した832万6530円のうち金400万円を、夫から妻に支払うことを命じた例
3−5 生活費の未払分と財産分与
3―5−1997.6.24
[裁判所]東京地裁
[年月日]1997(平成9)年6月24日判決
[出典]判タ962号224頁
[事案の概要]
離婚訴訟において財産分与の額を定めるについて、婚姻継続中の婚姻費用分担の未払額を算定した上、これを考慮した事例
3−6 債務の財産分与
3―6−1999.9.3
[裁判所]東京地裁
[年月日]1999(平成11)年9月3日判決
[出典]判時1700号79頁、判タ1014号239頁
[事案の概要]
夫婦共同生活の中で生じた債務は財産分与の対象となるとして、主文でその負担を求めた例
3−7 不動産登記の手続きと金銭の支払いを同時履行
3―7−1998.2.26
[裁判所]東京高裁
[年月日]1998(平成10)年2月26日判決
[出典]家月50巻7号84頁
[事案の概要]
離婚訴訟に伴う財産分与請求について、妻の不動産の共有持分権を夫に分与するとともに、不動産の取得に対する当事者双方の寄与の割合、残債務の状況、夫が夫婦の連帯債務である購入資金を支払う旨の意思を明らかにしていることその他諸般の事情を考慮して双方の負担割合を定めた上、妻から夫への不動産の共有持分権の全部移転登記手続と、夫が妻に対して負担する金員の支払いとを同時履行(引換給付)にすべきものとした事例
3−8 その他
3−8−2020.8.6
[最高裁第一小法廷2020(令和2)年8月6日決定 最高裁ホームページ、家庭の法と裁判30号50頁]
[事実の概要]
抗告人は相手方に対し、財産分与の審判を申し立てた。原審は、抗告人名義の建物等を相手方に分与しないものと判断した上で,抗告人に対し相手方への209万9341円の支払を命じた。抗告人からの不動産の明渡し請求に関しては、所有権に基づくものとして民事訴訟の手続において審理判断されるべきものであるとして、家事事件手続法154条2項4号に基づき相手方に対し抗告人への本件建物の明渡しを命ずることはしなかった。
[決定の概要]
「財産分与の審判において,家庭裁判所は,当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して,分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定めることとされている(民法768条3項)。もっとも,財産分与の審判がこれらの事項を定めるものにとどまるとすると,当事者は,財産分与の審判の内容に沿った権利関係を実現するため,審判後に改めて給付を求める訴えを提起する等の手続をとらなければならないこととなる。そこで,家事事件手続法154条2項4号は,このような迂遠な手続を避け,財産分与の審判を実効的なものとする趣旨から,家庭裁判所は,財産分与の審判において,当事者に対し,上記権利関係を実現するために必要な給付を命ずることができることとしたものと解される。そして,同号は,財産分与の審判の内容と当該審判において命ずることができる給付との関係について特段の限定をしていないところ,家庭裁判所は,財産分与の審判において,当事者双方がその協力によって得た一方当事者の所有名義の財産につき,他方当事者に分与する場合はもとより,分与しないものと判断した場合であっても,その判断に沿った権利関係を実現するため,必要な給付を命ずることができると解することが上記の趣旨にかなうというべきである。
そうすると,家庭裁判所は,財産分与の審判において,当事者双方がその協力によって得た一方当事者の所有名義の不動産であって他方当事者が占有するものにつき,当該他方当事者に分与しないものと判断した場合,その判断に沿った権利関係を実現するため必要と認めるときは,家事事件手続法154条2項4号に基づき,当該他方当事者に対し,当該一方当事者にこれを明け渡すよう命ずることができると解するのが相当である。」として、原審を破棄し差し戻した。
[ひとこと]
家事審判法の時代、2004(平成16)年の人事訴訟法成立前は明渡しも財産分与の処分の一環として認める見解および裁判例(東京地判平9.10.23判タ995号234頁)があったが、人事訴訟法が、離婚訴訟と併合審理できる民事訴訟を関連損害賠償請求に限定したため、明渡し請求の別訴が必要と理解する見解があり、一方で、家事審判規則56条、49条により明渡しを併せて命じる決定があった(大阪高決平成21年2月20日未公表・家月64巻8号112頁・松本)。しかし、2013(平25)年から家事事件手続法が施行されその154条2項4号が、財産分与審判において、「・・物の引渡し・・その他の給付を命ずることができる。」としたので本件論点の行方が注目されていたところ、本件決定によって決着した。
3−8−2020.3.24
協議あるいは審判等によって財産分与請求権の具体的内容が形成される前の段階で、財産分与対象財産であることの確認を求める訴えは、確認の利益(権利保護の利益)を欠き不適法であるとして、却下した例
[大阪地裁2020(令2)年3月24日判決 判タ1485号207頁]
[事実の概要]
24年ほど続いた内縁関係の解消後、原告(40台後半の女性)が被告(70台後半の男性)に対し、有限会社の株式などの財産が財産分与対象財産であることの確認を請求した。なお、原告は、2018年に、被告を相手方として、財産分与請求調停事件を申し立てているが、その顛末については判決では触れられていない。
[判決の概要]
「夫婦の一方は、夫婦の他方が所有する財産について、協議あるいは審判等によって財産分与請求権の具体的内容が形成される前の段階(すなわち、その範囲及び内容が不確定・不明確なものにとどまっている段階)において、財産分与対象財産であることの確認を求めることはできず、このような確認を求める訴えは、確認の利益(具体的には、権利保護の利益)を欠き、不適法というべきである。」
3−8−2018.8.31
離婚に関する公正証書において、抗告人兼相手方(原審申立人)名義の住居に相手方兼抗告人(原審相手方)と子が一定期間居住することを認める条項が設けられていたが、原審申立人より、扶養的財産分与の目的を達したとして、原審相手方に対し住居の明渡しを求め、却下された例
[東京高裁2018(平30)年8月31日決定 判タ1465号91頁、家庭の法と裁判25号75頁]
[決定の概要]
「本件申立ては、使用貸借の終了に基づく本件住居の明渡請求であり、民事訴訟において審理、判断されるべき事項である。
…しかし、もとより離婚した元配偶者に対する法的な扶養義務はなく、原審申立人は、原審相手方との間で、離婚に伴う給付として本件公正証書どおりの合意をしたために、その合意に基づいた義務を負っているにすぎない。また、離婚に伴う財産分与の性質が扶養的なものであったとしても、必ずしも事情変更による取消し、変更が認められるものではない。扶養的財産分与が定期金として合意された場合は、民法880条を類推し事情変更による取消しや変更を認める余地もあるが、一時金や分割金として合意された場合は、履行後の事情変更による取消しや変更を認めることは著しく法的安定性を欠くと考えられ、許されないといわざるを得ない。そうすると、原審申立人が原審相手方に対し、扶養的財産分与として使用貸借権を設定したとしても、財産分与の結果、当事者間に使用貸借契約が成立したのであるから、原審申立人の本件住居の占有は同契約に基づくものであり、本件公正証書第2条について民法880条の類推による取消し、変更を認めることはできない。
…仮に、民法880条の類推による取消し又は変更ができると解するとしても、…公正証書作成後、それを維持することが当事者の衡平を欠くといえるような事情の変更を生じたとは認められない。」
3−8−2018.7.26
財産分与審判前の共有財産(建物)の名義人である元夫から元妻に対する明渡請求は権利濫用に当たるとして、損害賠償請求のみが認められた例
[札幌地裁2018(平成30)年7月26日判決 判時2423号106頁]
[事実の概要]
原告(元夫)と被告(元妻)は、婚姻後に原告名義でマンションを購入した後、離婚をした。被告は離婚後も本件マンションに居住し、被告から原告に対し、本件マンションなどの財産分与を求める審判手続が係属中である。原告が被告に対し、所有権に基づく建物明渡し及び賃料相当損害金の損害賠償請求を求めて提訴した。
[判決の概要]
婚姻期間中に形成された財産関係の離婚に伴う清算は財産分与手続によるのが原則であるあるから、本件マンションの帰趨は財産分与手続で決せられるべきであり、このことは本件マンションの住宅ローンの負債額が原告及び被告の総資産額の合計を上回っている場合であっても変わらない。このような意味で、被告は、財産分与との関係で、本件マンションの潜在的持分を有しているところ、当該持分はいまだ潜在的、未定的なものであっても財産分与の当事者間で十分に尊重されるべきである。よって、原告が、近々財産分与申立事件の審判が下される見込みである中、同手続外で本件マンションの帰趨を決することを求めることは、被告の潜在的持分を不当に害する行為と評価すべきであり、権利濫用に当たるというべきである。
被告には、原告との離婚成立以降、本件マンションの占有権限がないから、被告は、原告に対し、本件マンションの所有権侵害の不法行為に基づき、遅くとも離婚成立日の翌日から本件マンションの明渡済みまで、賃料相当損害金の支払義務を負う。
3−8−2017.6.30
元夫婦の共有名義の不動産には、住宅ローンを被担保債権とする抵当権が設定されているが、元妻が住宅ローンの債権者に対し、住宅ローンの残高とほぼ同額の預金債権を有していることから、預金、債務とも0円と評価した上、抵当権が実行される可能性は低いとして、元妻の共有持分を元夫に財産分与した例
[東京高裁2017(平29)年6月30日決定 判時2372号20頁、判タ1451号140頁、家庭の法と裁判16号100頁、LEX/DB25560923]
[事実の概要]
原審申立人(元夫)が原審相手方(元妻)に対し、離婚後に、共有不動産の元妻の持分を元夫が取得することを求める財産分与請求をした。
分与対象不動産は、持分が各2分の1の共有名義となっており、住宅ローンは元妻が主債務者、元夫が連帯保証人となっている。住宅ローンを被担保債権とする抵当権が設定され、かつ、元妻は住宅ローン債権者に対する預金担保として、住宅ローン残高とほぼ同額の預金債権を有している。分与対象財産は、本件不動産のほか、二人で設立した会社の株式等があり、元夫の保有する(実質)共有財産額は約3870万円、元妻のそれは約9378万円である。本件不動産の時価は4073万円である。
[決定の概要]
原審(東京家審2016(平28)年3月30日)は、本件不動産の住宅ローンは原審相手方(元妻)が主債務者、原審申立人(元夫)が保証人となっており、原審相手方(元妻)が返済を怠った場合、抵当権が実行される可能性があること、原審申立人(元夫)が同債務を返済すると求償関係の問題が生じることから、本件不動産の原審相手方(元妻)持分を元夫に分与することは相当でないと判断して共有のままとし、金銭による清算のみを命じた。
これに対し、抗告審は、本件住宅ローンは、原審相手方(元妻)名義の普通預金が担保として設定されており、住宅ローンの残高は普通預金の額とほぼ同額であることから、預金と債務を併せて評価し、各0円とした上、二人がローンにつき連帯債務を負っていること等から抵当権が実行される可能性は相当程度低いとして、原審相手方(元妻)の持分を元夫に分与することが相当であると判断した。そして、元妻の持分を元夫に分与した場合に、元夫が元妻に現金で支払うべき分与額を約717万円と算定した。
[ひとこと]
清算的財産分与の場合、積極財産の評価額から債務を控除して具体的な分与を決定するのが実務の考え方である。この考え方に従うと、本件では、本件不動産の評価額から被担保債務額を控除し、具体的な分与を決定することになる。しかし、本判決は預金債権と住宅ローン残高(借入金債務)がほぼ同額であること、二人が連帯債務を負っていることから抵当権が実行される可能性は相当程度に低いという事情を考慮し、預金債権、債務を各0円と評価して、不動産評価額から被担保債務額を控除しないこととした。ローン残がある共有不動産の分与方法について、一つの考え方を示したといえる。
3−8−2017.6.27
離婚に伴う財産分与が、民法768条3項の規定の趣旨に反して不相当に過大なものとして、国税徴収法39条(平成28年改正前のもの)の「著しく低い額の対価による譲渡」にあたるとされた例
[東京地裁2017(平成29)年6月27日判決 判タ1462号74頁]
[事実の概要]
原告(元妻)は、元夫Aから協議離婚に伴う財産分与として、宅地の譲渡を受けた。これに関し、原告は、Aの滞納に係る国税につき、国税局から第2次納税義務の納付告知処分を受け、その取り消しを求めて訴えた。
原告による控訴は棄却され(東京高判平成30年2月8日)、最高裁は、上告を棄却し、上告不受理決定をした(最高裁判所平成30年9月13日)。
3−8−2014.8.21
夫婦の共有名義の自宅建物から退去して妻子と別居した夫が、妻に対し、共有物分割請求として夫の単独所有とすること及び建物明渡しを求めることは、権利の濫用に当たり許されないとして、原審の請求棄却判決を維持した事例
[東京高裁2014(平成26)年8月21日判決 LLI/DB L06920484]
[事実の概要]
X(夫)とY(妻)は、子2人と一緒自宅建物(XY共有名義)に居住していたが、Xの不貞行為やYに対する暴行等を経て夫婦関係は悪化し、Xは自宅建物から退去して別居を開始した。その後、Xは、Yに対し、民法258条に基づく共有物分割請求として、本件建物をXの単独所有とすること並びにXのYに対する価格弁償金の支払いと引換えに、Y持分のXに対する持分全部移転登記手続及び本件建物の明渡しを求めて、訴訟を提起した。原審(東京地判2014(平成26)年4月10日)は、Xの請求について権利濫用であるとして棄却したため、Xは控訴した。
[判決の概要]
1 Xは、Yに対して同居・協力・扶助の義務(民法752条)に基づく居所の確保義務を負いながら、別居して、Yを相手方とする離婚調停手続と平行して本件各請求をするに至り、Yはこれによる心痛によって精神疾患に罹患して通院せざるを得なくなり、また過重の労働をしながら子らと3人で本件建物に居住することによってようやく現在の家計を維持している状況にある。
2 XはYとの間で、子らが27歳に達するまでYが無償で本件建物に居住することを合意しており、婚姻費用分担調停における調停条項において、婚姻解消するまでの間、Yが本件建物に無償で居住することを前提としてXがYに対して支払う婚姻費用分担額が定められ、Xが本件建物の住宅ローン及び水道光熱費等を引き続き負担することを確認する合意がなされている。Xの本件各請求は、かかる合意を覆すものである。
3 本件建物は就学時期にある子らの通学及び通院の拠点となっているところ、Xの本件各請求が実現されれば、Y及び子らの生活環境を根本から覆し、また現在の家計の維持を困難とすることになる。他方、本件各請求を実現しないとXの生活が困窮することは認めることはできない。
4 以上の事実に加えて、Xは有責配偶者である。有責配偶者であるXの請求によって離婚前に夫婦の共有財産に該当する本件建物に係る共有物分割を実現させてXの単独所有としてYに本件建物の明渡しを命じ、離婚に際しての財産分与による夫婦の共有財産の清算、離婚後の扶養及び離婚に伴う慰謝料等と分離し、これらの処分に先行して十分な財産的手当のないままにY及び子らの生活の本拠を失わせ、生計をより困難に至らしめることは、正義・公平の理念に反し、また、有責配偶者からの離婚請求が許される場合を限定して解すべき趣旨に悖る。
5 以上を総合考慮すれば、XのYに対する本件各請求は、著しく不合理であり、妻であるYにとって甚だ酷であるから、権利濫用に当たり許されない。
[ひとこと]
配偶者に対する自宅建物の共有物分割請求が権利濫用に当たるか否かについて、最判1995(平成7)年3月28日(民集174号903頁)の基準のもと、具体的事情を総合考慮して丁寧に検討した高裁判例であり、実務上参考になる。
3−8−2012.12.27
離婚訴訟の財産分与手続において清算対象とならなかった夫婦共有不動産について、離婚判決確定後にその共有関係が争われた事例
[東京地裁2012(平成24)年12月27日判決 判時2179号78頁]
[事実の概要]
夫Xと妻Yは、土地を購入し、その土地上に建物を新築して(いずれもX名義で登記)入居した。しかし、その後Xは本件建物を出てYと別居するに至った。
YがXに離婚及び財産分与を求めて訴訟を提起したところ、XがYに対して財産分与として707万円余りを支払うこと等の内容で判決が確定した(東京高裁)。なお、本件不動産について残余価値は0円と評価されたため清算対象とならず、預金のみが財産分与の対象とされた。
上記判決確定後、Xは本件建物の鍵を損壊して居住を始めた。そこで、YがXに対し、占有権に基づき本件建物の明渡しを求めるとともに、占有侵奪の不法行為に基づき損害賠償(慰謝料)を求める訴訟を提起したところ、Yの主張をいずれも認める判決が言い渡され、XはYに本件建物を明け渡した。
そこで、XはYに対し、①所有権に基づき本件建物の明渡しを求めるとともに、②使用料相当損害金の支払いを求めて訴訟を提起した。
[判決の概要]
①は棄却し、②の一部を認容した。
1いわゆるオーバーローンの不動産や、不動産の価値と住宅ローン残高がほぼ同程度であるとして残余価値がないと評価された不動産は、離婚訴訟の財産分与の手続においては清算の対象とならない。その結果、夫婦共有財産と判断された不動産について清算が未了のままとなる事態が生じ得るが、不動産の購入にあたって自己の特有財産から出捐をした当事者は、出捐をした金員の清算につき判断がなされないまま財産分与額を定められてしまい、他方で、たまたま当該不動産の登記名義を有していた相手方当事者は、出捐者の損失のもとで不動産の財産的価値の全てを保有し続けることができるという極めて不公平な事態を招来する。
そこで、夫婦の一方がその特有財産から不動産売買代金を支出したような場合には、離婚の際の財産分与とは別に、当該不動産の共有関係について審理判断がなされるべきである。
Yは、本件不動産を購入・建築するにあたり、自らの婚姻前の預貯金を解約して出捐していること、Xからの婚姻費用の支払いが開始されてから離婚が成立するまで住宅ローンをY固有の財産から負担してきたと評価できることから、本件不動産のうち少なくとも3分の1についてはYの持分に属する。
共有物の持分の割合が過半数を超える者であっても、共有物を単独で占有する他の共有者に対し、当然には、その占有する共有物の明渡しを請求することはできないから、XはYに対し、所有権(持分権)に基づき、当然には本件建物の明渡しを求めることはできない。
2Yは本件建物のうち持分3分の2については権原なくして占有しているから、XはYに対し、不法行為に基づき、使用料相当損害金の支払いを求めることができる。
[ひとこと]
不動産の価値と住宅ローン残高が同等、あるいは後者が前者を上回るため残余価値がないと判断された不動産については、実務上は財産分与の対象から外されている。しかし、その清算未了の不動産をめぐっては、本件のような紛争が生じかねない。本判決は、財産分与の対象とならなかった不動産について、財産分与の手続とは別に、実質的共有関係の清算を審理判断したものとして、実務上意味がある。
本件は、原告が所有権は100%自分にあるとしての主張であったが、もともと共有の登記になっていれば、一般的には、離婚後に共有物分割請求訴訟を提訴して解決している。
3−8−2011.2.14
婚姻中、夫の不貞発覚後、妻の不満を抑える目的で妻に贈与された財産は、妻の特有財産になったと認めるべきであり、財産分与として清算対象にはならないとされた事例
[裁判例]
大阪高決2011(平23)年2月14日 家月64巻1号80頁、民商146-3-115
[事実の概要]
夫(相手方)の不貞発覚後、婚姻期間が20年を超えることから、居住用不動産の贈与税の免除規定を使い、夫は妻(抗告人)に不動産を贈与しその旨登記した。その後、夫は不貞相手と暮らすようになり、夫婦は協議離婚した。夫は妻に対し、清算的財産分与として、不動産の評価額の2分の1である1080万円の支払いを求めた。
[決定の概要]
「本件贈与は、・・・抗告人が相手方による不貞行為を疑い、現に相手方による不貞行為を疑われてもやむを得ない状況が存在した中で、・・・抗告人の不満を抑える目的で行なわれたものであることからすると、婚姻中ではあるものの、確定的にその帰属を決めたもので、清算的要素をもち、そのような場合の当事者の意思は尊重すべきであるから、本件贈与により本件各不動産は・・・抗告人の特有財産となったと認めるべきである。
なお、特有財産であっても特段の事情が認められる場合には、財産分与として清算の対象とすべき場合もあるが、・・・抗告人が本件贈与により取得した特有財産を清算の対象としなければ公平の観点や社会通念上不当であるような特段の事情があるとは認められない。」
[ひとこと]
この論点で裁判例として公表されたものはおそらく初めてである。
3−8−2009.9.4
標準算定方式に基づいて算出した額を上回る部分の婚姻費用分担金の支払を財産分与の前渡しとした原審判を変更し,財産分与の前渡しとして評価することは相当ではないとした事例
[裁判所]大阪高裁
[年月日]2009(平成21)年9月4日決定
[出典]家月62巻10号54頁
[事実の概要]
3−8−2009.4.17と同じ事案である。前妻(X)が抗告し、Yが附帯抗告した。
[判決の概要]
当事者が自発的に,あるいは合意に基づいて婚姻費用分担をしている場合に,その額が当事者双方の収入や生活状況にかんがみて,著しく相当性を欠くような場合であれば格別,そうでない場合には,当事者が送金した額が,いわゆる標準算定方式に基づいて算定した額を上回るからといって,超過分を財産分与の前渡しとして超過することは相当ではない。そして,本件では,賞与を除く給与の手取り額の2分の1を下回る額が著しく相当性を欠いて過大であったとはいえない。
別居時の財産の2分の1からXが管理していたY名義の預金の別居時の残高を差し引いた約500万円を支払うべきとした。
[ひとこと]
奈良家裁2009(平成21)年4月17日審判(家月62巻10号61頁、3−8−2009.4.17)の判断を変更した。
なお,高松高判平成9.3.27家月49-10-79は,婚姻中円満な時期に過当に負担した婚姻費用は,その清算を要する旨の夫婦間の合意等の特段の事情のない限り,いわば贈与の趣旨でなされ清算を要しないが,破綻後の過当な負担については財産分与で清算しうるとしつつ,具体的事案に即して過当とはいえないとして財産分与での考慮を否定している。
3−8−2009.5.28
共有不動産に妻子が居住中である事案において、夫持分については清算的財産分与として夫に取得させるとともに、扶養的財産分与として妻に対し賃貸することを命じた事例
[裁判所]名古屋高裁
[年月日]2009(平成21)年5月28日判決
[出典]判時2069号50頁
[事実の概要]
夫は妻に対し、離婚及び共有マンション(妻子が居住中)の夫持分の移転登記手続等を求めて訴訟提起した。妻は、婚姻関係は破綻しておらず、有責配偶者からの離婚請求は許されないと主張したが、原審は夫の請求を認め、その主張に沿う財産分与を命じた。
妻は控訴し、さらに離婚や損害賠償、本件マンションの夫所有部分について妻が賃借権を有することの確認等を求めて、反訴を提起した。
[判決の概要]
清算的財産分与は、特段の事情がない限り、別居時の財産を基準にすべきである。従前の紛争の経過に照らすと、本件別居時に、夫が妻に対し、将来にわたり本件マンションの使用を許諾していたとは認められない。
しかしながら、本件別居は、夫による悪意の遺棄に該当し、遠い将来における夫の退職金等を分与対象に加えることが現実的ではなく、更に一部が特有財産である本件マンションが存在する。このような場合には、本件婚姻関係の破綻につき責められるべき点が認められない妻には、扶養的財産分与として、離婚後も一定期間の居住を認めて、その法的地位の安定を図るのが相当である。
したがって、①本件マンションの夫の持分を夫に取得させるとともに、②扶養的財産分与として、夫に対し、当該取得部分を、賃料月額○○円、賃貸期間を長女が高校を卒業する××年3月までとの条件で妻に賃貸するよう命ずるのが相当である。
[ひとこと]
共有不動産について、別居原因など諸事情を考慮しながら、扶養的財産分与として4万円強の家賃の賃貸を命じた。夫が婚姻費用分担審判の中で、自分のローン支払分を家賃相当額として控除することを強硬に主張し減額が認められたので、それと全く同額を家賃相当分として認定している(従って時価相場よりも安い可能性があり、そのことをもって扶養的と評価している可能性もある。家賃の相場額を支払うならば扶養にならないので)。財産分与の1つとして、判決によって賃貸借あるいは使用貸借の設定を命ずる方法は確立しているが、最近の公表判例が少ないので紹介した。
なお、本事案は、夫の不貞相手が特定できない事案であった。原判決は、この点を重視して夫の不貞行為を否定したが、本判決では、かなりの量のラブホテルの割引券や利用カード、ホテルの名入りのライターが発見されたことから、「氏名不詳の相手」との不貞関係を認めた点も注目される。他に、退職金について、同居期間に対応する部分は、本来、財産分与の対象となる夫婦共有財産であると認定しながら、受給が15年先ということを考慮し、清算的財産分与の対象とせず扶養的財産分与の要素して斟酌するにとどまった。受給が10年程度先のものでは清算的財産分与が認められているが、それでは、何年以上先の場合まで認めるかの判例の限界ははっきりしてない。否定の一事例として参考になる。
3−8−2009.4.17
標準算定方式に基づいて算出した額を上回る部分の婚姻費用分担金の支払を財産分与の前渡しと評価した事例
[裁判所]奈良家裁
[年月日]2009(平成21)年4月17日審判
[出典]家月62巻10号61頁
[事実の概要]
前妻Xと前夫Yは,二女をもうけたが,Xの宗教活動をめぐってXYが対立するようになり,YはXと二女を残して別居した。Yが提起した離婚訴訟につき,離婚を認める判決が確定した。
その後Xは,財産分与と年金分割を求める調停を申し立てたが,不成立となり,審判移行した。
[判決の概要]
財産分与の対象となる財産につき,別居当時の預金残高と別居の年にYが受領した退職金の合計額と認定し,別居後もYが受領した賞与の合計も分与対象となるとのXの主張を退けた。
そうするとYはXに506万円を支払うべきとも思われる(寄与は2分の1ずつ)。しかし,Yは,別居後、標準算定方式に基づいて支払うべきであった金額を上回る婚姻費用を分担し,その超過額は454万円余りに及ぶ。これは事後的扶養というべき財産分与の前渡しの意味を有しているというべきである。そこで,506万円−454万円の52万円が分与すべき財産となる。
[ひとこと]
本審判は,大阪高裁2009(平成21)年9月4日決定(家月62巻10号54頁、3−8−2009.9.4)によって変更された。年金分割についての本審判(3−8−2009.4.17)の判断も変更された(3−8−2009.9.4)
3−8−2009.2.26
過酷な暴力を継続して受けていた妻の夫に対する財産分与の合意、慰謝料の支払約束は、その自由意思に基づいたものではなく、無効であるとされた事例
[裁判所]仙台地裁
[年月日]2009(平成21)年2月26日判決
[出典]判タ1312号288頁
[事実の概要]
イスラエル国籍のX男と日本国籍のY女は婚姻し、3人の子をもうけた。X男は、婚姻後に別の女性と関係を持ったり、わいせつ行為を行ったりしたほか、Y女が自分の思い通りにならないと怒鳴りつけるなどした。また、Y女の不貞行為が明らかになると、Y女に対する暴言や暴行を繰り返すようになった。協議離婚成立後も、X男は、Y女に対する激しい暴行等を繰り返し、恐怖で抵抗できないY女に、「不動産等をX男に分与する」旨記載した財産分与合意書及び「X男に対して2000万円の慰謝料を10日以内に支払う」旨記載した慰謝料等支払約束書を作成させた。
X男は、Y女に対し、上記合意書や約束書等に基づく不動産所有権移転登記手続及び慰謝料2000万円の支払いを求めて提訴した。
[判決の概要]
本件財産分与合意書及び本件慰謝料等支払約束書は、いずれも、X男が、Y女の不貞行為を責める態度に終始し、X男に対する暴力を繰り返し、Y女を自己のコントロール下に置いた上で、Y女をしてX男の指図どおりの内容で本件財産分与合意書及び本件慰謝料支払約束書を作成させたものであって、Y女の自由意思に基づいて作成された文書ではない。したがって、本件財産分与合意書及び本件慰謝料等支払約束書に表示されたY女の意思表示は、意思表示としての効力を有さず、いずれも無効というべきである。
[ひとこと]
強迫による意思表示は取消すことができるが(民法96条1項)、脅迫の結果、完全に意思の自由を失った場合には、その意思表示は無効であり民法96条の適用の余地はない(最判昭33.7.1民集12-11-1601)。本件は、後者の場合として無効を認めた1例。判決からは原告による苛烈な暴力の様子、これにより被告がサラ金からの借金を工面しようとしたこと、風俗で働くことを命じられたこと、最後は被告の母のサポートにより女性センターに保護された経緯が伺える。早期にDV法による保護を受けられていたらと思う例である。
3−8−2006.5.31
扶養的財産分与として使用貸借権を設定した事例
[裁判所]名古屋高裁
[年月日]2006(平成18)年5月31日決定
[出典]家月59巻2号134頁
[事実の概要]
妻Aと夫Bは平成11年6月4日に離婚。離婚後、AがBに対し、清算的財産分与、慰謝料的財産分与及び共有名義のマンションについて使用貸借権の設定を求めた事案。Aは共有名義のマンションに長女(昭和61年生)次女(昭和63年生)長男(平成6年生)と居住し、住宅ローンはBが返済している。
[判決の概要]
離婚に伴う慰謝料請求を基礎付けるに足りる事実は認められないが、妻が経済力の豊かな夫から突然申し出られた離婚を短期間で受け入れた背景には、妻が離婚を受諾しやすい経済的条件の提示があったからであると推認されること、妻の婚姻費用として提供した1000万円近い持参金が夫婦共有財産として残存していないこと、妻が子らと居住する建物に関する費用を夫が負担することを前提に子らの養育費が算定されていることなどの諸事情を考慮すると、離婚後の扶養的財産分与として、妻及び子らが居住する建物について、期間を離婚から第3子が小学校を卒業するまでの間とする使用貸借契約を設定することが相当であるとした。
[ひとこと]
夫から文書で、妻が子供を育てている間は家賃なしで共有名義のマンションに居住しそれ以降は話し合いとする旨の提案がなされていたことが、扶養的財産分与を認めるうえで影響を与えたケース。
3−8−2005.6.9
損害保険金の財産分与対象性
[裁判所]大阪高裁
[年月日]2005(平成17)年6月9日決定
[出典]家月58巻5号66頁
[事実の概要]
夫Aと妻Bは平成6年3月に婚姻し、平成15年9月に調停離婚した。Aは平成12年8月に交通事故で負傷し、損害保険会社から5200万円の損害保険金が支払われた。離婚調停では保険金についての合意が成立せず、Bは財産分与の審判を申し立てた。Aは家事育児全般に従事し、その結果Bは事業に専念できたという事情がある。
[判決の概要]
相手方(夫)が交通事故により取得した損害保険金のうち、傷害慰謝料、後遺障害慰謝料に対応する部分は相手方の特有財産というべきであるが、逸失利益に対応する部分は財産分与の対象となると解するのが相当であるとして、相手方に対し、症状固定時から調停離婚成立日の前日までの逸失利益に対応する額のおおむね半額及びこれに対する遅延損害金の支払いを命じた。
[ひとこと]
従来から主張されていた考え方を判例上も明示した。損害保険金のうち、慰謝料部分は本人の精神的苦痛を慰謝するものだから財産分与の対象にはならないが、逸失利益に対応する部分は対象になるとした。
3−8−2004.10.15 財産分与と詐害行為
離婚に伴う不動産の財産分与のうち、不相当に過大な部分について詐害行為にあたり取り消されるべきであるとし、受益者(元妻)に対して価格賠償が命じられた事例
[裁判所]大阪高裁
[年月日]2004(平16)年10月15日判決
[出典]判時1886号52頁、判タ1187号115頁判決評釈
[事実の概要]
X(○○信用保証協会)からY1(元夫)に対する求償金請求に関し、Y1からY2(元妻に対して土地建物の財産分与がなされたことにつき、XからY1に対し、①通謀虚偽表示による無効、あるいは②詐害行為として取り消す、移転登記を求めた事案。
[判決の概要]
「離婚における財産分与は、分与者が既に債務超過の状態にあって当該財産分与によって一般債権者に対する共同担保を減少させる結果になるとしても、それが民法768条3項の規定の趣旨に反して不相当に過大であり、財産分与に仮託してされた財産処分であると認めるに足りるような特段の事情のない限り、詐害行為として、債権者による取消しの対象となり得ない。そして、上記特段の事情があるときは、不相当に過大な部分について、その限度において詐害行為として取り消されるべきものと解するのが相当である。」
「本件財産分与のうち、不相当に過大な部分のみを取り消し、価格による賠償を命じるのが相当である。」とした。
具体的には、土地はY1の特有財産、建物は実質上夫婦の共有財産であるとして、土地及び建物の合計額からローン残を引いた額(分与した額)から、建物の半分の価額(本来分与すべきであった額)を差し引いた額の価格賠償を妻に対して命じた。
[ひとこと]
本件では、離婚後も同居し夫婦生活を続けているが、離婚に伴う法的効果が発生することを意図して離婚したものであるとして、通謀虚偽表示による無効は認めなかった。妥当である。
3−8−2004.6.18
同族会社資産も財産分与対象とし、詳細な認定がなされた事例
[裁判所]広島高裁岡山支部
[年月日]2004(平16)年6月18日判決
[出典]判時1902号61頁
[事実の概要]原告(妻)と被告(夫)は昭和48年11月に婚姻。3人の娘と息子1人がいる。妻は平成9年11月に家を出て別居。夫は婚姻当初から妻へ暴力をふるったり、子らへ行き過ぎた体罰を行ったりした。不貞もあった。
[判決の概要]
慰謝料500万、弁護士費用50万を認めたほか、財産分与について詳細な認定を行った。
「丙川社は、一審原・被告が営んできた自動車販売部門を独立するために設立され、丁原社は、一審原・被告が所有するマンションの管理会社として設立されたものであり、いずれも一審原・被告を中心とする同族会社であって、一審原・被告がその経営に従事していたことに徴すると、上記各会社名義の財産も財産分与の対象として考慮するのが相当である。」「一審原告が家事や四名の子の育児に従事しながら、一審被告の事業に協力し続け、資産形成に大きく貢献したことに徴すると、一審原告の寄与率は五割」とし、夫婦中心で経営した同族会社の資産も財産分与の対象として考慮し、妻の寄与率を5割、妻は3億2639万円の財産分与をうけるのが相当とした。
3―8−1999.5.18
[裁判所]東京家裁
[年月日]1999(平成11)年5月18日決定
[出典]家月51巻11号18頁
[事案の概要]
財産分与事件において、相手方が離婚の約1年後に勤務先会社から支払いを受けた約914万円について、同金員は離婚時にはその支給が決定されておらず、支給の趣旨も同会社の合併による解散に伴う相手方の爾後の生活保障というものであるから、この支給時期、態様及び趣旨からして、同金員は財産分与の対象となる退職金又は功労金には該当しないとした例
|
 |
 |
|
|



