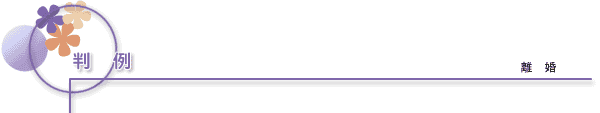 |
|
渉外離婚(国際離婚)
2 離婚の準拠法
離婚の準拠法は,下記の通りである(法の適用に関する通則法・以下「法適用」という。27条本文,25条)。
第1に,夫婦の本国法が同一であるときはその本国法(共通本国法)
第2に,共通本国法のないときは夫婦の共通常居所地法
第3に,共通常居所地法もないときは夫婦に最も密接な関係のある地の法律,
但し,夫婦の一方が日本に常居所を有する日本人の場合は日本法となる(法適用27条但書)
平成16年に従来の「法例」が法適用に改正されたので、多くの判例では法例の旧条文が引用されている。
2−2019.1.17
[東京家裁2019(平成31)年1月17日判決 家庭の法と裁判22号121頁]
ミャンマー国籍を有し、イスラム教徒であり、日本の永住権資格を持つ夫婦について、夫からの一方的な宣言により(夫が妻に対し「タラーク」と3回唱えれば)離婚が成立するとのイスラム法の適用の結果は日本の公序に反し、通則法42条により排除し、こうした離婚は無効とし、そのうえで、日本の離婚法を適用して妻からの離婚請求を認め、子の親権者の指定及び離婚慰謝料の請求については、イスラム法の適用(親権者夫、慰謝料は認めらなくなる結果となる)を日本の公序に反するとして排除し、日本法に基づき判断した例(ただし、被告夫は裁判を欠席し書面も提出していない事例)
2−2011.8.18
1974(昭和49)年に日本で協議離婚の届出をした韓国人夫婦について、1989(平成元)年改正前の法例を適用し、離婚の有効性を認めた事例
[東京地裁2011(平成23)年8月18日判決 渉外判例研究619巻111頁]
[事実の概要]
原告X(韓国籍)は、A(韓国籍)と1964年韓国において婚姻の届けをし、同年、Bを出生した。1974年、XとAの協議離婚届が日本で提出され受理された。Aは、日本に不動産を所有していたが、1992年遺言をせずに死亡した。Bは本件不動産につき、相続を原因とする所有権移転登記を行い、その後BからYに対し、売買を原因とする所有権移転登記がなされた。Xは、本件離婚は無効であり、Xが本件不動産の5分の3の持分を相続したとして、Yに対し持分の所有権移転登記手続を求める訴えを提起した。
[判決の概要]
1974年の離婚の有効性は、平成元年6月28日法律27号改正前の法例16条本文に基づき、夫の本国法の適用を受けて判断すべきものと解される。さらに、韓国国際私法付則2項は、同法施行前に生じた事項については、従前の国際私法によるものと規定しており、韓国国際私法18条は離婚については夫の本国法によると定めているから、反致の問題は生じない。韓国民法によると、1974年の離婚の有効性については、1977年の改正前の韓国民法に準拠すべきことになる。1977年の改正前の韓国民法834条は、「夫婦はその協議により、離婚をすることができる。」と規定し、同836条1項は、「協議上の離婚は、戸籍法の定めるところにより申告をすることによって、その効力を生ずる。」と規定している。これらの規定の文言及び内容に照らすと、韓国民法834条は離婚の実質的要件を定め、同836条1項は、その方式を定めたものと解される。韓国民法834条の実質的要件については、離婚当事者双方が届出の時点で離婚意思を有していたことが要件になると解すべきである。また、韓国民法836条1項の方式に関しては、法律行為の方式の原則規定たる通則法改正前の法例8条が適用され、同条2項に基づき、行為地たる日本法に則った方式によることができることになると解される。したがって、韓国民法836条1項による届出については、日本において日本法の規定する届出を行えば足りるというべきである。本件離婚の有効性について、Xが自ら離婚届を提出したかはともかくとして、少なくともAが提出していたことについて認識していたというべきであり、その後、Aが死亡するまで遂に同居することなく長年にわたって別居状態を続け、本訴提起まで離婚が無効であるとして、離婚届けが出された状況を是正するための措置を何ら執ってこなかったからすれば、届出時点において真意による離婚意思を有していたと推認することができるというべきである。したがって、Xは離婚意思を有しており、離婚届けも提出されているのであるから、離婚は有効に成立しているというべきである。
[ひとこと]
本判決は、1974(昭和49)年になされた離婚およびその方式について、平成元年改正法例附則2項の不遡及原則の効力は維持されているとして、改正前法例16条及び8条を適用して準拠法を定めた。なお、韓国民法について、1977年に「協議上の離婚は、家庭裁判所の確認を受け、戸籍法の定めるところにより、申告をすることによって、その効力を生ずる。」(836条1項)と改正されているが、本件離婚には改正前の法律が適用されている。
2−2009.6.4
日本在住の中国人夫婦が日本でした協議離婚について、中国法に定める離婚の要件(婚姻登記機関への出頭、子の扶養者・養育費の負担・財産関係の協議の処理)を満たしていないとしても、日本法の方式として欠けるところがなければ、離婚自体が無効になるとは認められないとした例
[裁判所]大阪家裁
[年月日]2009(平成21)年6月4日判決
[出典]戸籍時報645号31頁(渡辺惺之教授評釈)
[事実の概要]
日本定住の中国人(中華人民共和国)X男と、中国人Y女が、平成14年に中国で知り合い、中国において同国の方式で婚姻した。その後Yは来日し、定住者としてXと婚姻生活を続けていたが、夫婦関係が悪化し、日本で居住する市の役所に協議離婚届を提出した。その後、Yは、駐日中国領事館でXとの離婚届出の手続をし、婚姻要件具備証明の交付を受け、懇意となった日本人男性Z男と日本の方式で婚姻した。
これに対し、Xが、XYの協議離婚は、X男に離婚の意思がないのに届出されたもので無効であるとして、離婚無効確認請求の訴えを提起した。
[判決の概要]
本件離婚の準拠法は中国法であるが、法律行為の方式については行為地法によることができること(通則法34条2項)を確認した上で、中国法では離婚届出の際に当事者双方の出頭と婚姻登記機関による離婚意思確認の手続が定められているが、これらは方式の問題であるから、これらの手続がなされていなかったとしても、当事者に離婚意思があったと認められる本件では、行為地法である日本法の定める方式としては欠けるところはないから、本件離婚届出が無効になるものではないとした。
さらに、「中国方式の協議離婚の場合、子の扶養者、養育費の負担、財産関係が協議により適切に処理されていることが求められているので、日本の役所が日本の方式で協議離婚を受理する際も中国法によって、扶養者、財産関係の協議事項の確認をするのが望ましい」が、日本の役所がこれをせずに協議離婚届を受理したとしても、「離婚意思の合致が認められる場合に受理した協議離婚は有効である」とした。
[ひとこと]
従来、中国法による「婚姻登記機関への出頭による離婚合意の確認」を欠く場合に、実質的要件を欠き無効とする判例(大阪家判平成19.9.10戸籍時報630号2頁)と、方式要件の問題として通則法34条2項を適用して有効とする判例(高松高判平5.10.18判タ834号215頁)があったが、後者の立場をとった判例。
2−2007.9.10
在日中国人夫婦が日本で行った協議離婚について、離婚意思を有していたことは認めながら、日本の協議離婚による離婚は、準拠法である中国法の定める離婚意思の確認要件を充足しないという理由により、離婚を無効とした例
[裁判所]大阪家裁
[年月日]2007(平成19)年9月10日判決
[出典]戸籍時報630号2頁(渡辺惺之教授評釈)
[事実の概要]
中国人男女が、中国で婚姻後、夫婦とも来日し、日本において婚姻生活を送っていたが、夫婦関係は破綻し、日本の市役所に協議離婚届を提出した。夫は、本件協議離婚は、公営住宅の入居申込書と誤解して署名したものであり、離婚の意思を欠き無効であると主張して離婚無効確認の訴えを提起した。
[判決の概要]
離婚の準拠法は、夫婦の本国法すなわち中国法であるが、協議離婚の方式については、行為地法すなわち日本法による場合でも有効となることを確認した。そして、中国法における協議離婚の要件を個別に検討し、①双方の協議離婚意思は存在する、②離婚登記は協議離婚の方式の問題であるから日本法上の協議離婚の届出により要件が満たされているとした一方、③婚姻登記機関の審査、④婚姻登記機関への双方の出頭、⑤協議離婚時に双方が国外に居住を移している場合には人民法院への離婚提訴が必要、という③④⑤の要件については、単に協議離婚の方式に当たるとはいえず中国法が適用となるとした上で、要件は満たされていないとし、結局、本件協議離婚は無効とした。
[ひとこと]
本判例に従えば、日本在住の中国人夫婦は、日本の協議離婚による離婚はできないことになる、とのことである(上記、渡辺教授評釈より)。
2−1998.5.29
[裁判所]横浜地裁
[年月日]1998(平成10)年5月29日判決
[出典]判タ1002号249頁
[判決の概要]
米国人夫から中国人妻に対する離婚請求について夫婦が日本で共同生活をしていたことや原告と夫婦間の子が日本の定住資格を有していることから離婚の準拠法を密接関係地法である日本法とした。
2−1991.10.31
[裁判所]横浜地裁
[年月日]1991(平成3)年10月31日判決
[出典]判時1418号113頁
[判決の概要]
準拠法の基準時点は,口頭弁論の終結時である
2−1991.3.4
[裁判所]水戸家裁
[年月日]1991(平成3)年3月4日審判
[出典]家月45巻12号57頁
[判決の概要]
フランス人夫からイギリス人妻に対し離婚請求した事案で日本法を密接関係地法として離婚の準拠法とした。
|
 |
 |
|
|



