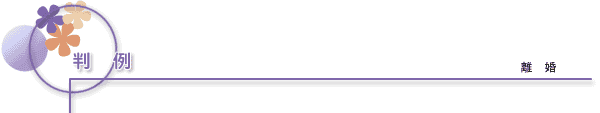 |
|
7 その他
7−2021.3.25
民法上の配偶者は,婚姻関係が実態を失って形骸化し,かつその状態が固定化して近い将来解消される見込みのない,いわば事実上の離婚状態にある場合には,中小企業退職金共済法14条1項の配偶者には該当せず,死亡による退職金の受給権者に該当しないとした例
[最高裁第一小法廷2021(令和3)年3月25日判決 最高裁Webサイト]
[判決の概要]
「中小企業退職金共済法は,中小企業の従業員の福祉の増進等を目的とし、退職金の支給を受ける遺族の範囲及び順位の定めは,被共済者の収入に依拠していた遺族の生活保障を主な目的としており,民法上の相続とは別の立場で受給権者を定めたものと解される。
このような目的に照らせば,上記退職金は,共済契約に基づいて支給されるものであるが,その受給権者である遺族の範囲は,社会保障的性格を有する公的給付の場合と同様に,家族関係の実態に即し,現実的な観点から理解すべきであって,上記遺族である配偶者については,死亡した者との関係において,互いに協力して社会通念上夫婦としての共同生活を現実に営んでいた者をいうものと解するのが相当である(最高裁昭和54年(行ツ)第109号同58年4月14日第一小法廷判決・民集37巻3号270頁参照)。
そうすると,民法上の配偶者は,その婚姻関係が実体を失って形骸化し,かつ,その状態が固定化して近い将来解消される見込みのない場合,すなわち,事実上の離婚状態にある場合には,中小企業退職金共済法14条1項1号にいう配偶者に当たらないものというべきである。なお,このことは,民法上の配偶者のほかに事実上婚姻関係と同様の事情にあった者が存するか否かによって左右されるものではない。」と判示した。
7−2019.2.12
離婚訴訟において、原告の不貞行為を主張して請求棄却を求めている被告が、不貞行為の相手方である第三者に対して提起した損害賠償請求訴訟は、人事訴訟法8条1項にいう「人事訴訟に係る請求の原因である事実によって生じた損害の賠償に関する請求に係る訴訟」に該当するとした事例
[最高裁第三小法廷2019(平成31)年2月12日決定 判タ1460号43頁]
[事案の概要]
配偶者Aから離婚訴訟を提起されたYは、AはXと不貞行為をした有責配偶者であると主張して請求棄却を求める一方、Xに対し、不貞行為を理由とする損害賠償請求訴訟を横浜地方裁判所に提起した。
Xは、人事訴訟法8条1項に基づき、上記損害賠償請求訴訟を、離婚訴訟の係属する横浜家庭裁判所に移送するよう申し立てた。
原々審(横浜地方裁判所)は上記申立てを認め、移送の決定をした。Yは即時抗告をしたが、原審(東京高等裁判所)はこれを棄却した。
そこで、Yが許可抗告の申立てをしたところ、原審がこれを許可した。
最高裁は、以下のとおり判示して、Yの許可抗告を棄却した。
[決定の概要]
「人事訴訟法8条1項…の趣旨は、人事訴訟と審理が重複する関係にある損害賠償に関する請求に係る訴訟について、当事者の立証の便宜及び訴訟経済の観点から、上記人事訴訟が係属する家庭裁判所に移送して併合審理をすることができるようにしたものと解される。
上記の趣旨に照らせば、離婚訴訟の被告が、原告は第三者と不貞行為をした有責配偶者であると主張して、その離婚請求の棄却を求めている場合において、上記被告が上記第三者を相手方として提起した上記不貞行為を理由とする損害賠償請求訴訟は、人事訴訟法8条1項にいう『人事訴訟に係る請求の原因である事実によって生じた損害の賠償に関する請求に係る訴訟』に当たると解するのが相当である。」
7−2016.1.7
離婚給付等契約公正証書の離婚慰謝料請求権に基づく債権差押命令の申立を却下した決定に対してされた執行抗告が認容され、債権差押命令が発令された事例
[東京高裁2016(平成28)年1月7日判決 判例時報2312号98頁]
[事実の概要]
A(妻)とB(夫)が作成した離婚給付等契約公正証書(以下「本件執行証書」という)では、前文で「BとAは、離婚することに合意し、離婚に伴う子の養育費、慰謝料、財産分与の支払いについて、以下のとおり合意した。」とした上で、慰謝料について、「BはAに対し、離婚による慰謝料として金850万円の支払義務があることを認め、平成22年9月末日までに金400万円、平成28年5月末日までに金450万円を第1条1項に定める方法により支払う。」旨記載されている。Aが本件執行証書を債務名義とし、本件執行証書記載の慰謝料請求権の未払分の一部を請求債権として、Bの有する預金債権の差押さえを求めたところ、執行裁判所(原審)は、当該慰謝料請求権は離婚が成立した際に初めて発生するものであるから、請求が債権者の証明すべき事実の到来にかかる場合にあたり、執行文及び当該事実が到来したことを証する文書の謄本が債務者に送達されたことが執行開始の要件になるところ、その証明がされていないとして、Aの申立てを却下した。そこで、Aが執行抗告をした。
[判決の概要]
本件執行証書は、抗告人と債務者とが離婚することを合意するとともに、離婚に伴う養育費、慰謝料、財産分与の支払を合意したものである。この離婚の合意は、協議離婚をすることの合意と解されるものであり、協議離婚は、届出を必要とする要式行為であるから、その届出がされて初めて離婚の効力を生ずるものであり、離婚に伴う慰謝料請求権も、特段の事情がない限り、離婚の効力が発生するまで成立しないものと解されるが、この協議離婚の法的性質から、離婚当事者が離婚の成立時期より前の一定の時期を期限として離婚に伴う慰謝料請求権を発生させる合意をすることが法的に無効とされる理由はないと解され、このような合意の存在は、上記の特段の事情に当たるものというべきである。一般的に離婚の効力発生を要件として負担することになると解される子の養育費及び財産分与の支払について、本件執行証書の条項では、離婚の効力が発生した離婚成立月を始期として支払うこととするものと、具体的に定める期日又は具体的に定めた期間に一定額を支払うとするものとがあり、後者の支払合意は、素直な文言解釈としては、離婚の成立を要件としない支払義務を定めたものと解されるものである。そして、本件条項で合意している債務者の慰謝料支払義務も、一定の期日までに一定額を分割して支払うという内容のものであるところ、本件条項で支払うとされている慰謝料について、本件執行証書の前文では「離婚に伴う」慰謝料と、本件条項では「離婚による」慰謝料となっているが、その支払が一定の期日までに一定額を分割して支払うとされていることに照らして、この「離婚に伴う」又は「離婚による」という文言が一義的に離婚の成立ないし離婚の効力発生に基づくという意味を表すものと解することはできないというべきであり、素直な文言解釈としては、離婚の成立を要件としない支払義務を定めたものと解するのが相当である。以上の次第であるから、本件申立てに係る債権差押命令は発令されるべきものであり、これと異なる原決定は相当でなく、本件抗告は理由があるから、原決定を取り消し、上記債権差押命令を発令する。
7−2013.7.5
離婚訴訟の係争中だった配偶者、原告の叔母が、離婚訴訟を有利に進めるために、原告を強制的に医療保護入院させることを計画した上、被告会社及び被告介護支援事務所と共謀して、原告を拘束して精神医療センターに連行し、その際、原告と長女に対して傷害を負わせたとして、被告らに対して請求した損害賠償が一部認容された事例
[大阪地裁2013(平25)年7月5日判決 LEX/DB25501586]
[事実の概要]
原告Aと被告Cは1975年に婚姻した夫婦であった。原告Bは、AとCの長女である。被告Dは原告Aの母の妹である。
被告E会社と被告F介護支援事務所は、患者の搬送業務等を行う会社である。
2009年2月、Aは、大阪家庭裁判所において、Cに対する離婚請求訴訟を提起した。
同年11月、Cは、Aに対し、自宅への立ち入りを妨害することの禁止を請求する裁判を提起するとともに、立入妨害禁止仮処分命令を申し立てた。仮処分命令申立事件につき、2010年3月、Cによる立ち入り等について、本案の立入妨害禁止訴訟が終局するまでの暫定的な和解が成立した。2011年1月、Cは、後述のG医師の診断書をもとにAに訴訟能力がないと主張し、Aにつき精神鑑定の申立てをしたが、同年2月、本案の立入妨害禁止請求は棄却された。Cは控訴したが、同年6月、大阪高等裁判所は控訴を棄却した。
2011年1月、Cは、後述のG医師の診断書をもとに弁論再開の申立てをしたが、同28日、離婚や財産分与、慰謝料請求を認容する離婚訴訟の判決が言い渡された。A及びCがそれぞれ控訴したが、大阪高等裁判所は、同年6月、いずれの控訴も棄却した。Cは上告、上告受理申し立てをしたが、最高裁判所は、上告棄却、不受理の各決定をした。これによりACは離婚した。
Cは、同年1月11日、精神医療センターを訪れ、精神保健福祉士に対し、離婚訴訟や立入妨害禁止訴訟等の証拠を取捨選択したものを渡した。
Aは、C及びDが契約を締結したE会社の従業員らとE会社から派遣の要請を受けたF介護支援事務所の従業員らにより、同年1月14日、Aは、その意に反して、有形力を行使され、精神医療センターに搬送された。その際に、AとBは傷害を負った。精神医療センターの医師Gは、Aにつき、病歴書面、Cの説明、Aに対する問診の結果に基づき、統合失調症であるとの診断をするとともに、医療保護入院の必要があると診断した。同センターのH医師は、精神保健指定医として、Aにつき、入院治療が必要であると判断し、Cを精神保健福祉法上のAの保護者としてその同意ありとして、医療保護入院の措置を執った。Aは同日、同センターの閉鎖病棟の保護室に隔離された。G医師は、同日付で、Aが統合失調症であるとの診断書を、C及びDに交付した。
離婚訴訟等におけるAの代理人を務めていた弁護士が、精神医療センターに対し、CはAと裁判係争中のため、その保護者になることはできないと抗議した結果、医療保護入院が取り消され、同日午後9時ころ、退院した。
Dは、2011年1月24日、大阪家庭裁判所に対し、扶養義務者指定、保護者順位変更及び選任の申立てを行い、同裁判所は、Dが提出したG医師の上記診断書等をもとに、同月31日、DをAの扶養義務者と定める等の審判をした。Aは、同年4月12日、大阪家庭裁判所に上記審判の取消しを求める申立てを行い、大阪家庭裁判所は、同月31日、申立てを認め、審判を取り消す旨の審判をした。
C、DがE、Fと共謀の上、Aを精神医療センターに連行し、その際にA、Bに傷害を負わせたこと等、さらに搬送後の一連の行為につき、損害賠償を請求するとともに、Cに対し、診断書の引渡しを請求したのが本件である。
[判決の概要]
本件の事実関係と、2008年以降Aと別居し、尋問以外に顔を合わせてもいなかったCが、Aの自傷他害のおそれがあることなど取り急ぎ精神科医療を受けなければ本人の保護が図れないなどの状態にはないとの認識をもつ機会もなかったこと等から、本件搬送その他一連の行為を不法行為と認めた。Dについては、実際の搬送には直接関与しておらず、医師にもAの病状を語っておらず、一貫してCが主導していることから、Cの話を聴いてAが病気だと信じて行為に及んだという陳述を排斥するには至らないとして、故意過失を否定した。
E会社は、AとAの代理人弁護士から、Cと係争中であると聴いたにもかかわらず、被F介護支援事務所に増員を依頼して、Aの意に反する搬送に及んだこと、AとBが抵抗した際にそれぞれ加療を要する傷害を負わせたこと等から、E会社とF介護支援事務所は損害賠償責任を負う。
以上より、本件搬送その他一連の行為につき、CはAに対し200万円の損害賠償責任を負うとし、EとFは内33万円を連帯して賠償責任を負うとした。Bについては、C、E,Fが連帯して11万円の賠償責任を負うとした。
Cが診断書の返還を拒否しているところ、診断書の取得については、Aの人格権が違法に侵害されたと認めつつ、このままCが所持することによって、Aの人格権がさらに侵害される可能性はないとし、引渡請求権があるとは認められないとして斥けた。
[ひとこと]
係争中の夫の恣意的な資料の提出等情報提供に影響されて、容易に医療保護入院の措置がなされてしまった上、違法行為を経て入手された診断書が裁判所にも提出され、一部の判断に影響もしたという、それぞれの機関の専門性や制度の運用をも懸念させられる事案である。
7−2011.7.27
家事審判法9条1項乙類に掲げる事項につき、他の家庭に関する事項と併せて申し立てられた調停が成立しない場合、同項乙類に掲げる事項が審判に移行するか否かが問題となった事例
[裁判所]最高裁三小
[年月日]2011(平成23)年7月27日決定
[出典]家月64巻2号104頁、判タ1357号85頁、判時2130-3
[事実の概要]
元妻Xは、元夫Yと協議離婚をした後、Yに対して、①財産分与、②慰藉料、③子どもの所持品の引渡し、④年金分割の4つを申立ての趣旨とする家事調停の申立てを1通の申立書に記載してし、一般調停事件として受け付けられたが、同調停は不成立となった。Xは、①財産分与と④年金分割については、家事審判法9条1項乙類事項であるから、調停不成立により審判手続に移行したとして、家庭裁判所に審判期日の指定を求めたが、家庭裁判所は、同調停は一般調停と理解され審判へ移行しないとして、Xの審判期日の指定申立てに応じない旨を家事審判官名で書面により回答した(以下、「本件回答書」)。そこでXは、本件回答書が、「審判期日指定の申立てに対する却下審判」に当たるとの前提に立って、これを不服として抗告した。
原決定(東京高決平23.3.31家月64-2-104)は、審判事件における当事者には期日指定申立権がないと解されること、本件回答書は、その体裁及び内容からして、弁護士宛の連絡文書にとどまるとし、「審判期日指定の申立てに対する却下審判」とみることはできないとして、抗告を不適法として却下した。
そこでXが、原決定は憲法32条違反であるとして特別抗告をしたのが本件である。
なお、財産分与及び年金分割につき、離婚後2年が経過しており、Xは、再度審判申立てをすることができない状態であった(民法768条2項、構成年金保険法78条の2第1項)。
[決定の概要]
Xの抗告理由は、原決定の単なる法令違反を主張するものであるとして、抗告を棄却した。
[ひとこと]
最高裁決定では、なお書きとして、Xが申し立てた「調停事件のうち財産分与及び年金分割を求める部分は、家事審判法9条1項乙類に掲げる事項に該当し、又は同事項とみなされるのであって、同事項に該当しない他の家庭に関する事項と合わせて調停の申立てがされた場合であっても、抗告人が調停不成立のときに審判への移行を求める意思を有していないなど特段の事情がない限り、その事件名にかかわらず、家事審判法26条1項に基づいて審判に移行するものと解される(・・手数料に不足があるときは、これを追加して納付することを要する)」との見解を示している。
審判申立に期間制限があるときには、裁判所は申立時に申立人の意向を十分に確認し、乙類調停として受理できるよう申立方法をアドバイスするなど、申立人の権利保護に配慮すべきであろう(判時2130-3同旨)。
7−2009.7.16
離婚届の作成時から約9か月後に届出がなされた事案について、その期間における夫婦の関係その他の事情を考慮して、届出時点での離婚意思及び届出意思を認めた事例
[裁判所]東京高裁
[年月日]2009(平成21)年7月16日判決
[出典]判タ1329号213頁
[事実の概要]
X(夫)は、戸籍上は協議離婚届により離婚した旨が記載されているが、用紙に自ら署名押印したことはなく、Y(妻)が無断でしたものとして、離婚が無効であることの確認を求めた。
原審(千葉家裁平成21年2月6日判決)は、以下のとおり、届出当時、Xが離婚意思及び届出意思を持っていたとはいえないとして、Xの請求を認容した。
①離婚届がXの意思に基づいて署名押印されたものと認定することができない。
②仮にXが署名押印したとしても、未成年者である子の親権や財産分与について協議がなされた形跡もないから、夫婦喧嘩の成り行きで署名押印したとしても、当然に離婚意思及び届出意思を持ってされたものかどうかも定かではない。
③仮に作成時に離婚について合意ができていたとしても、届出までの約9か月間、XとYは同居を続けており、Xは離婚を前提とする行動を取っていないし、Yも、今後Xが定職について稼働するようになれば離婚しないことも考えていたのであり、作成当時に、確定的な離婚の意思を有していたのかさえ疑問である。
[判決の概要]
Xは、自ら署名・押印をして、Yに届出を委ね、Yもその日のうちに署名押印したものと認められるから、作成当時、Xが離婚意思及び届出意思を有していたことは明らかである。
Yは、わずかながらもXが定職に就いてくれれば離婚しなくてもよいと期待していたために、約9か月の間本件届出をすることがなかったが、その間、XとYの婚姻関係は改善されず、届出の前月には夫婦の自宅を売却して借入金や滞納税の支払に充て、残った代金を双方が分割取得し、以後別居状態になるなど、生活状況がXの期待に反して激変した。他方、XからYに対し離婚の届出をしないようにとの申出があったことは認められない。
したがって、Xの離婚意思に変動は認められず、届出当時、Xは離婚意思及び届出意思を有していたものと認めるのが相当である。
[ひとこと]
本件では、届出が約9か月遅れたという事情があるが、判決は詳細に事実経過を認定し、Xの離婚意思に変動は認められないとした。なお、原審の上記②の点についても、「XとYは、未成年者の親権者や財産分与の協議をした形跡はないが、Xは親権者の指定をYにゆだねたものと認めるのが相当であり、財産分与についても、Yが離婚時にすべてを解決することまで考えていなかったことによるものとも考えられるから、上記認定の妨げになるものではない」との判断を示した。類似事案の参考になると思われる。
7−2009.3.31
別居する妻子の住所における妻子に対する訴状等の訴訟関係書類の交付をもって、別居する夫の住所における補充送達として有効であるとし、夫からの送達無効としてなされた再審請求が棄却された事例
[裁判所]東京高裁
[年月日]2009(平成21)年3月31日決定
[出典]判タ1298号305頁
[事実の概要]
前訴損害賠償請求事件において敗訴した夫が、前訴において訴状等の訴訟関係書類は、17年前から別居している妻子の住所に送達されており、有効な送達を欠くとして民事訴訟法338条1項3号の再審事由があるとして再審の訴えを提起した。原審の再審開始決定に対し、前訴の当事者が抗告した。
[判決の概要]
妻子の居住する前訴送達先において常時居住していたとは認められないが、前訴送達先に配達される相手方(夫)あての郵便物等の受領を同所に常時居住している相手方の妻らに依頼していて、相手方において前訴送達先に赴いて同郵便物等を受取に行っていたものであり、また、相手方に対する連絡先として前訴送達先を指定しており、相手方とその妻らは必要があれば随時電話で連絡を取り合っていたものである。そして、相手方は、前訴送達先の隣地である相手方共有地を本店所在地とする会社を設立し、これを経営していた(相手方は、同会社により、その所有(共有)する不動産の管理、売買取引等をしていたものと推認される。)ところ、同所には建物(事務所)はなく、前訴送達先の固定電話を同会社の連絡先とし、実質的には前訴送達先を同会社の事務所としていたものであり、また、本件訴訟関係書類が送達された2年ほど前に極短期間相手方肩書地を住所とする住民登録の届出をしたほかは、現在まで一貫して前訴送達先を住所として住民登録の届出をし、自動車運転免許証も前訴送達先を住所として交付を受けていたものである。
前訴送達先は、相手方について、送達場所としての民事訴訟法103条1項の住所(同会社について、同項の事務所)というべきである。
[ひとこと]
珍しい例である。別居中の夫婦の関係についての一判断であるので紹介した。
7−2008.11.18
夫婦間の共有物分割請求は妨げられるものではなく、家裁の管轄に属するものではないとした例
[裁判所]東京地裁
[年月日]2008(平成20)年11月18日中間判決
[出典]判タ1297号307頁
[事実の概要]
判決から詳細な事情はわからない。原告(夫か妻か不明)持分5分の4、被告持分5分の1の建物につき、地裁に共有物分割請求の提訴をした事案である。提訴より前に、原告は被告を未成年子の親権者とする離婚届を勝手に届け出て、離婚無効確認の審判がなされた経緯がある。
[判決の概要]
財産分与と共有物分割請求との関係については、遺産分割と共有物分割請求との関係(最三小判昭62.9.4判タ651号61頁、判時1251号101頁は、遺産の分割については共有物分割が許されず、遺産分割の審判手続によるものとする)と同様に解することはできず、夫婦間の共有物分割請求(地方裁判所の管轄)は妨げられるものではない・夫婦の中には、一方の側からの離婚請求が、有責配偶者であること等の理由から排斥される事案もあり、たとえこのような事案であっても、夫婦の共有名義となっている財産の共有物分割の途が閉ざされるべき理由はない・・
[ひとこと]
オーバーローンの共有不動産が、財産分与の対象外とされる点から考えても、共有物分割請求の方法が財産分与とは別途認められるのでなければ、当事者は紛争の解決手段を失うことになる。中間判決で明示した点が珍しい。
|
 |
 |
|
|



