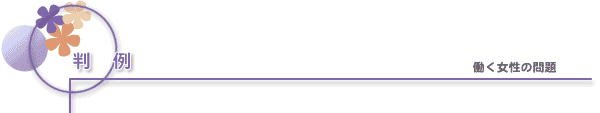 |
|
1 賃金、昇進・昇格
1−2001.6.27 住友生命保険(既婚女性差別)事件
既婚であることを理由に、低く査定し、昇給させなかったことは、不法行為に当たるとした判例
[裁判所]大阪地裁
[年月日]2001(平成13)年6月27日判決
[出典] 労働判例809号5頁
[事実の概要]
原告ら(X1〜X12)は、被告会社に対し、被告会社が、原告らが既婚者であることを理由に、昇給昇格において違法に差別するとともに、数々の嫌がらせを行ってきたことは、労基法13条違反、債務不履行ないしは不法行為に基づく差額賃金ないしは差額賃金相当額の支払いを求めた。
[判決の要旨]
既婚女性への低査定は、人事権の濫用だとして、差額賃金相当額、慰謝料などを一部認めた。地位確認は認められていない。
「……以上のような、面接担当者の発言や婚姻、出産時の退職勧奨については、原告らを含む既婚女性の中でも、退職勧奨を受けなかった者もいることや、退職勧奨を受けた時期も一律ではなく、被告会社本社の指示によるとまでは認められないが、その数が多く、しかもかなり強く勧奨された者もあることからすると、被告会社の既婚女性の勤続を歓迎しない姿勢は被告会社の管理職従業員の姿勢となっていたものということはできる。」
「……上記の嫌がらせといってもいい事実については、個々の上司の問題であるとしても、現実に既婚女性が勤務を続けることを快く思わず、これを理由に嫌がらせといえるようなことをしたとすれば、それは嫌がらせを受けた各原告に対する不法行為になるから、その責任は被告会社において負担すべきことになる。」
「……査定については、それが被告会社による既婚女性従業員排除の方針の実現とまでいえなくても、現実に個々の具体的な人事考課において、既婚女性であることのみをもって一律に低査定を行うことは、人事考課、査定が、昇格、非昇格に反映され、賃金等労働条件の重要な部分に結びつく被告会社の人事制度の下では、個々の労働者に対する違法な行為となるといわなければならない。けだし、前述のとおり、被告会社における人事考課、査定は、個々の労働者の業績や能力等について、各考課要素に基づき判断するというものであり、婚姻の有無といった前記考課要素以外の要素に基づいて一律に査定することは本来就業規則で予定されている人事権の範囲を逸脱するものといえるからである。また、被告会社が人事考課において、産前産後の休業をとったり、育児時間を取得したこと自体をもって低く査定したのであれば、それは、労基法で認められた権利の行使を制限する違法なものというべきで、その場合、被告会社はその責任を負うことになる。被告会社の当時の社会状況に鑑みれば違法性がない旨の主張は、上記の理由で採用できない。」
「……しかし、個々の既婚女性従業員について、実際の労働の質、量が低下した場合にこれをマイナスに評価することは妨げられないであろうが、一般的に既婚女性の労務の質、量が低下するものとして処遇することは、合理性を持つものではない。上記主張の産前産後の休業、育児時間を取得したことによって労働の質、量が大きくダウンするという意味が、休業期間、育児時間に労働がなされていないことをもって労働の質、量が低いというのであれば、それは法律上の権利を行使したことをもって不利益に扱うことにほかならず、許されないことである。
被告会社は、労基法は、産前産後の休業や育児時間など労基法上認められている権利の行使による不就労を、そうした欠務のない者と同等に処遇することまで求めているものではないと主張する。確かに、労基法が欠務のない者と同等に処遇することを求めているとはいえないが、その権利を行使したことのみをもって、例えば、能力が普通より劣る者とするなど低い評価をすることは、人事制度が相対評価を採用している場合でも、労基法の趣旨に反するというべきである。
さらに、被告会社は、労基法上の権利行使による不就労により能力の伸長に差を生じたときには、能力考課にあたり、その差を評価の対象とするのは、やむを得ないと主張するが、一般的に不就労によって能力の伸長がないものと扱うことは許されないというべきである。」
「……被告会社は、原告Kが、産前産後に休業し、育児時間を取得したこと等から、その業績(成果)は他の職員よりも低いものとならざるを得なかったと主張するが、その主張する業績の低さが休業又は育児時間取得により就業しなかったことをいうのであれば、それは産前産後の休業、育児時間の取得をもって不利益に査定したというものであって、労基法上許されないというべきである。けだし、産休、育児時間、有給休暇を取得した結果、その間の業務量が他の職員より減少することはやむを得ないが、これを人事考課上のマイナス要因にすることは、それにより、労基法上の権利であるこれらの休業、休暇等の取得を事実上妨げるものであり、かかる権利を保障した趣旨を実質的に失わせることになるからである。
被告会社は、原告Kが、育児時間取得時期の後も家事や育児のため等により、殆ど定時に退社するという状況であったため、業務量が他の職員に比較すると少なく、原告Kの業務量を軽減してその分を他の職員にまわさざるを得ないことから、他の職員の負担増となっていた旨主張するが、残業命令違反があったものではないから、これをもって人事考課上のマイナス要因とすることは相当ではない。原告Kの定時退社によって負担増となった他の従業員と原告Kとに業務量に差がある場合に、これを考課において同等に扱う必要はないが、相対的評価をする場合であっても、普通以下の評価をすることは許されるべきではない。」
|
 |
 |
|
|



