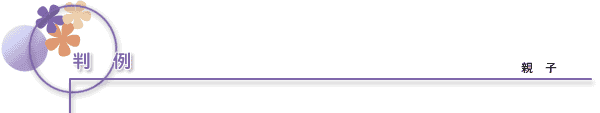 |
|
梴巕墢慻丒棧墢
俀侽俀侾丏俁丏俁侽
峈崘恖偑巰朣偟偨梴巕偲偺巰屻棧墢偺嫋壜傪媮傔偨帠埬偵偍偄偰丄尨懃偲偟偰嫋壜偡傋偒偱偁傞偑丄梴巕偺枹惉擭偺巕偑梴恊偐傜晑梴傪庴偗傜傟偢惗妶偵崲媷偡傞偙偲偲側傞側偳丄幮夛捠擮忋梕擣偟摼側偄帠忣偑偁傞応崌偵偼丄嫋壜偡傋偒偱偼側偄偲偟偨椺
[戝嶃崅嵸2021(椷3)擭3寧30擔寛掕丂敾僞1489崋64暸]
[寛掕偺奣梫]
梴巕墢慻偼丄梴恊偲梴巕偺屄恖揑娭學傪拞妀偲偡傞傕偺偱偁傞偙偲側偳偐傜偡傟偽丄壠掚嵸敾強偼丄巰屻棧墢偺怽棫偑惗懚梴恊枖偼梴巕偺恀堄偵婎偯偔傕偺偱偁傞尷傝丄尨懃偲偟偰偙傟傪嫋壜偡傋偒偱偁傞偑丄棧墢偵傛傝梴巕偺枹惉擭偺巕偑梴恊偐傜晑梴傪庴偗傜傟偢惗妶偵崲媷偡傞偙偲偲側傞側偳丄摉奩怽棫偰偵偮偄偰幮夛捠擮忋梕擣偟摼側偄帠忣偑偁傞応崌偵偼丄偙傟傪嫋壜偡傋偒偱偼側偄丅杮審偱偼丄棙奞娭學嶲壛恖(梴巕偺巕)偺廇楯幚愌傗憡摉懡妟偺堚嶻傪憡懕偟偰偍傝丄棙奞娭學嶲壛恖偑峈崘恖(梴恊)偺戙廝憡懕恖偺抧埵傪憆幐偡傞偙偲偲側偭偰傕惗妶偵崲媷偡傞偲偼擣傔傜傟側偄偙偲側偳偐傜丄幮夛捠擮忋梕擣偟摼側偄帠忣偑偁傞偲偄偆偙偲偼偱偒側偄丅偙偺偙偲偼丄峈崘恖偵棙奞娭學嶲壛恖傪帺傜偺憡懕恖偐傜攔彍偟偨偄偲偄偆巚偄偑偁傞偲偟偰傕嵍塃偝傟側偄傕偺偱偼側偄丅傛偭偰丄杮審怽棫偰傪嫋壜偡傞丅
俀侽俀侽丏俀丏俀俆
梴巕墢慻撏偺奜宍傗丄梴恊偺堄巚擻椡偺忬懺丄梴巕墢慻偵帄傞廬慜偺宱堒摍偐傜偡傞偲丄梴巕偺晝偑梴恊偵埶棅偝傟丄偦偺堄巚偵増偭偰梴巕墢慻撏偺彁柤傪戙昅偟偨傕偺偱偁傞偲偼偄偊偢丄梴巕墢慻偑梴恊偺堄巚偵婎偯偔傕偺偱偁傞偲擣傔傞偙偲偼偱偒側偄偲偟偰丄柉朄802忦1崋偵傛傝丄梴巕墢慻傪柍岠偲偟偨帠椺
[墶昹壠敾2020(椷2)擭2寧25擔丂敾僞1477崋251暸丄壠掚偺朄偲嵸敾33崋103暸]
[帠幚偺奣梫]
尨崘傜偺曣(A)偼崶堶偟丄旐崘偺晝(B)傪傕偆偗偨屻丄棧崶丅A偼嵞崶偟丄尨崘傜傪傕偆偗偨丅B偼A偺嵞崶憡庤偲梴巕墢慻偟偨丅偦偺屻丄B偼崶堶偟旐崘偑嶻傑傟偨丅B偲B偺嵢偼丄A偺椉恊偲梴巕墢慻偟丄傑偨丄B偺嵢偼丄A媦傃A偺晇偲梴巕墢慻偟偨丅
A偼丄2015擭2寧丄擣抦徢偲恌抐偝傟偨丅2016擭1寧丄A偼崪愜偟擖堾偟偨丅摨擭6寧丄A偼丄嵞搙丄崪愜偟擖堾偟偨丅擖堾拞偺宱夁婰榐偵傛傟偽丄乽摉堾擖堾楌偁傞偑杮恖妎偊偰偄側偄丅擔晅丄崱夞偺庴彎婡彉傕摎偊傜傟側偄丅乿側偳偺婰嵹偑偁偭偨丅傑偨丄摨寧丄挿扟愳幃娙堈抦擻僗働乕儖偺寢壥偼丄30揰枮揰拞5揰偱偁偭偨丅
2016擭7寧崰丄B偼丄梴巕墢慻撏弌梡巻傪弨旛偟丄偦偺乽梴巕偵側傞恖乿偺乽梴巕乿棑傪旐崘偵彁柤偝偣丄報娪偵偮偄偰偼丄B偑娗棟偟偰偄偨報娪傪墴報偝偣偨丅乽梴恊偵側傞恖乿偺乽梴曣乿棑偵偼丄B偑A偺彁柤傪戙昅偟丄B偑娗棟偟偰偄偨報娪傪墴報偟偰丄摨擭8寧丄墢慻撏傪栶強偵採弌偟偨丅側偍丄A偼丄B偵捓戄庁宊栺彂摍偺彁柤傪戙彂偝偣傞偙偲偑偁偭偨丅
[敾寛偺奣梫]
乽杮審梴巕墢慻撏偺乽梴恊偵側傞恖乿棑拞偺乽梴曣乿棑偺A偺彁柤偼丄B偺昅偵傛傞傕偺偱偁傞丅傑偨丄A偺彁柤偺墶偵墴偝傟偨報復偵偮偄偰傕丄A偺傒偑娗棟偟偰偄偨報復偵傛傞傕偺偲擣傔傞偵懌傝傞徹嫆偼側偔丄旐崘偺彁柤偺墶偵墴報偝傟偨報塭偲崜帡偟偰偄傞偙偲偐傜丄旐崘偺壠掚撪偵偍偄偰悽懷庡偱偁傞B偑娗棟偟偰丄壠懓偱嫟梡偟偰偄偨報娪偵傛傞傕偺偲悇擣偝傟傞丅偦偆偡傞偲丄杮審梴巕墢慻撏偺奜宍偐傜偼丄杮審梴巕墢慻撏偺A偺嶌惉晹暘偑A偺堄巚偵婎偯偄偰嶌惉偝傟偨偲偼擣傔傜傟側偄丅
偙偺揰偵偮偄偰丄旐崘偼丄B偑A偺堄巚傪妋擣偟偨忋偱丄偦偺堄巚偵婎偯偒丄摉帪暥帤傪彂偔偺偑擄偟偄忬懺偱偁偭偨A偵埶棅偝傟偰丄戙昅偟偨傕偺偱偁傞偲庡挘偡傞丅偟偐偟丄A偼丄暯惉27擭2寧仠擔偵偍偄偰婛偵乽擣抦徢乿偲恌抐偝傟偰偄偨偙偲丄暯惉28擭6寧仠擔偺堛椕婰榐偵傛傟偽丄乽摉堾擖堾楌偁傞偑杮恖妎偊偰偄側偄丄擔晅丄崱夞偺庴彎婡彉傕摎偊傜傟側偄丅乿側偳偲偺婰榐偑偁偭偨偙偲丄暯惉28擭6寧23擔偵幚巤偝傟偨挿扟愳幃娙堈抦擻僗働乕儖偺寢壥偼30揰枮揰拞5揰偲偄偆偐側傝掅偄揰悢(堦斒揑偵屻尒掱搙偵憡摉偡傞丅)偱偁偭偨偙偲側偳偵徠傜偟偰丄杮審梴巕墢慻摉帪丄A偺堄巚擻椡偼偐側傝掅壓偟偰偄偨傕偺偲偆偐偑傢傟傞偐傜丄A偑丄杮審梴巕墢慻偑偝傟傞偙偲傪廫暘擣幆偟偨忋偱丄B偑偦偺彁柤傪戙昅偡傞偙偲偵摨堄偟偨偲擣傔傞偵偼崌棟揑側媈偄偑巆傞丅乿偲偟偰梴巕墢慻偺柍岠傪妋擣偟偨丅
旐崘偼丄A偑偙傟傑偱捓戄庁宊栺彂摍偺彁柤傪B偵戙昅偝偣偰偄偨偙偲偐傜丄杮審梴巕墢慻撏傕摨條偵彁柤偺戙峴傪偝偣偨傕偺偱偁傞偲庡挘偟偰偄傞偑丄杮審梴巕墢慻撏偺梡巻偵偼丄乽昁偢杮恖偑彁柤偟偰偔偩偝偄乿偲偺拲堄彂偒偑晅偝傟偰偍傝梴巕墢慻偺廳梫惈偵徠傜偟偰傕丄A偑捓戄庁宊栺彂摍偲摨條偵旐崘偺晝偵彁柤傪戙昅偝偣偨偲偡傞偵偼媈栤偑偁傞丅側偍丄杮審梴巕墢慻撏偑偝傟偨屻偵丄栶強偐傜A偺廧強偵捠抦偑偝傟偨偼偢偱偁傞偑丄A偑偦偺捠抦傪尒偨偲偄偆徹嫆偼側偔丄壖偵丄A偵捠抦傪尒偣偨偲偟偰傕丄偦偺惛恄忬懺偵徠傜偟偰丄梴巕墢慻偑偝傟偨偙偲傪棟夝偱偒傞忬嫷偱偁偭偨偐媈栤偱偁傞丅
旐崘偼丄A偑丄旐崘偑20戙偺擭楊偺崰偐傜丄旐崘偲偺墢慻堄巚媦傃撏弌堄巚傪桳偟偰偄偨偲庡挘偡傞丅妋偐偵丄尨旐崘傜偺懏偡傞D壠偵偍偄偰梴巕墢慻偑戙乆峴傢傟偰偒偰偄偨偙偲偼擣傔傜傟傞偑丄A偲旐崘偲偺梴巕墢慻偺榖偑丄旐崘偑20戙偺擭楊偺崰(暯惉5丄6擭崰)偐傜弌偰偄偨偺偱偁傟偽丄偦傟傪丄20擭埲忋偵傢偨偭偰幚峴偣偢偵偄偨偙偲偼晄帺慠偱偁傞丅傑偨丄旐崘偼丄D壠偺嵿嶻傪暘嶶偝偣側偄偨傔偲偄偆摦婡傪庡挘偡傞偑丄偦偆偱偁傟偽丄堚尵偲偄偆庤抜傕偲傟偨偼偢偱偁傞偲偙傠丄A偑堚尵傪嶌惉偟偰偄側偄偺傕晄崌棟偱偁傞偲偄偊傞丅
埲忋偺師戞偱丄杮審梴巕墢慻撏偺A偺帺彁晹暘偵偮偄偰丄B偑A偵埶棅偝傟丄偦偺堄巚偵増偭偰彁柤傪戙昅偟偨傕偺偱偁傞偲偡傞旐崘偺庡挘偼嵦梡偡傞偙偲偑偱偒偢丄杮審梴巕墢慻偑A偺堄巚偵婎偯偔傕偺偱偁傞偲擣傔傞偙偲偼偱偒側偄丅偦偺梋偺庡挘傪敾抐偡傞偙偲側偔丄尨崘傜偺惪媮偼擣傔傜傟傞丅
俀侽侾俋丏俈丏俋
慶晝偲墢慻傪偟偨峈崘恖偑丄慶晝偺巰朣屻偵壠掚嵸敾強偵棧墢偺嫋壜傪媮傔偨偲偙傠丄墢慻偑嵿嶻偺憡懕傪栚揑偲偟偰偝傟偨傕偺偱偁偭偰傕丄梴恊偲峈崘恖偲偺娫偵朄掕寣懓娭學傪宍惉偡傞堄巚偑偁傞尷傝丄捈偪偵墢慻傪柍岠偲偡傞偙偲偼偱偒偢丄巰屻棧墢偺怽偟棫偰偑朄掕寣懓娭學偺摴媊偵斀偡傞湏堄揑偱堘朄側傕偺偲傕擣傔傞偵懌傝傞帠忣傕側偄偲偟偰丄怽棫偰傪嫋壜偟偨椺
[搶嫗崅嵸2019(椷榓尦)擭7寧9擔寛掕丂壠掚偺朄偲嵸敾33崋67暸]
[帠幚偺奣梫]
梴恊偼C偲偺娫偵幚巕D丄E丄F丄G傪傕偆偗丄偙偺4柤偺偆偪丄D偵偼H偑丄F偵偼I偑丄G偵偼峈崘恖偑偦傟偧傟偺巕(梴恊偵偲偭偰偼懛)偲偟偰弌惗偟偨丅懠曽丄E偵偮偄偰偼丄攝嬼幰枖偼捈宯斱懏偼懚嵼偟側偐偭偨丅梴恊偼丄H丄I媦傃峈崘恖偲偺娫偱墢慻傪偟丄偦偺屻巰朣偟偨丅C偼婛偵巰朣偟偰偄偨偙偲偐傜丄梴恊偺朄掕憡懕恖偼丄D丄E丄F丄G丄H丄I媦傃峈崘恖偺7柤偱偁偭偨丅7柤偼堚嶻暘妱嫤媍傪惉棫偝偣丄梴恊偺堄岦偵増偭偰丄幚巕E偲懛H丄I媦傃峈崘恖偺4柤偑丄梴恊偺嵿嶻傪憡懕偟偨丅峈崘恖偼丄壠掚嵸敾強偵梴恊偲棧墢偡傞怽偟棫偰傪偟偨偑(柉朄811忦6崁)丄尨怰偼丄梴恊偲峈崘恖偲偺墢慻偼墢慻堄巚傪寚偒柍岠偱偁傞偲偟偰丄巰屻棧墢偺怽棫偰偺懳徾傪寚偒晄揔朄偱偁傞偲偟偰丄峈崘恖偺怽棫傪媝壓偟偨偨傔丄峈崘恖偑懄帪峈崘偟偨丅
[寛掕偺奣梫]
梴恊偼丄帺屓偺嵿嶻傪巕傜偺偆偪攝嬼幰媦傃巕偺側偄E偵壛偊偰丄懛偱偁傞H丄I媦傃峈崘恖偺3柤偵捈愙憡懕偝偣傞偙偲傪栚揑偲偟偰懛傜3柤偲墢慻傒傪偟丄梴恊偺憡懕恖傜偼丄惗慜偺梴恊偺堄岦偵廬偄堚嶻暘妱傪偟偨偙偲偑擣傔傜傟傞丅懠曽丄峈崘恖偑墢慻慜偵晑梴媊柋傪晧偭偰偄偨偺偼丄婛偵巰朣偟偰偄偨傕偺傪彍偒丄捈宯寣懓偱偁傞峈崘恖偺晝丄曣丄梴恊(慶晝)丄慭慶曣偺4柤偱偁傝(柉朄877忦1崁)丄嶰恊摍撪偺恊懓偱偁傞E丄D媦傃F偵懳偟偰偼壠掚嵸敾強偺怰敾偵傛傝晑梴媊柋傪晧偆壜擻惈偑偁傞偵偲偳傑偭偰偄偨偲偙傠(摨忦2崁)丄梴恊偲偺墢慻偵傛偭偰丄峈崘恖偼丄E傜3柤偵懳偟偰傕壠掚嵸敾強偺嫋壜傪懸偨偢偵晑梴媊柋傪晧偆偵帄偭偨偙偲偑擣傔傜傟傞丅傕偭偲傕丄D媦傃F偵偼偄偢傟傕攝嬼幰媦傃捈宯斱懏偑偍傝丄峈崘恖偑椉柤偺晑梴媊柋傪棜峴偡傞昁梫偑惗偢傞偙偲偼憐掕偟擄偔丄梴恊偲偺墢慻偵傛偭偰幚幙揑側曄壔偑惗偠偨偺偼E偵懳偡傞晑梴媊柋偵尷傜傟偰偍傝丄壖偵巰屻棧墢傪嫋壜偟偨偲偟偰傕丄峈崘恖偲E偲偺朄掕寣懓娭學偑廔椆偡傞傢偗偱偼側偔丄峈崘恖偼丄壠掚嵸敾強偺怰敾偵傛偭偰E偺晑梴媊柋傪晧偆壜擻惈偑偁傞偙偲丄峈崘恖偵傛傞巰屻棧墢偼丄E偺幚偺偒傚偆偩偄偱偁傞D丄F媦傃G偺E偵懳偡傞晑梴媊柋偵徚挿傪棃偡傕偺偱偼側偔丄巰屻棧墢偺嫋壜偑E偵偲偭偰晄棙側寢壥偲側傞帠懺偼憐掕偟擄偄偙偲丄E偼杮審堚嶻暘妱偵傛偭偰搚抧7昅丄梐挋嬥側偳懠偺憡懕恖偲斾妑偟偰懡偔偺堚嶻傪庢摼偟丄挿偔夛幮嬑傔傪偟偰偄偨偙偲傕偁傝丄惗妶偡傞偵廫暘側帒嶻傪桳偡傞偲偺峈崘恖偺庡挘偵媈偄傪書偐偣傞帒椏傕側偄丅偦偆偡傞偲丄杮審怽棫偰偑墢慻偵傛偭偰晧扴偟偨晑梴媊柋傪柶傟傞偨傔偵偝傟偨傕偺偲偼擣傔傜傟側偄丅偦偺懠丄杮審怽棫偰偑丄惗懚朄掕寣懓偱偁傞峈崘恖杮恖埲奜偵傛傞傕偺偱偁傞丄梴恊偺恊懓偵傛傞嫮梫偵婎偯偔側偳偲偄偭偨帠忣傗愱傜慶愭偺嵳釰傪柶傟傞栚揑偱偝傟偨偲偄偆傛偆側帠忣傪尒弌偡偙偲偼偱偒偢丄懛偵捈愙堚嶻傪憡懕偝偣傞偨傔偵墢慻傪偡傞偙偲偺摉斲偼暿偲偟偰丄杮審怽棫偰偑朄掕寣懓娫偺摴媊偵斀偡傞湏堄揑偱堘朄側傕偺偱偁傞偲偼擣傔傞偵懌傝側偄丅
俀侽侾俋丏俆丏俀俈
儀僩僫儉嵼廧偺擔杮恖晇晈偲儀僩僫儉崙愋偺巕偺摿暿梴巕墢慻偵偮偒擔杮偺嵸敾強偺崙嵺嵸敾娗妽傪擣傔偨椺
[搶嫗壠嵸2019(椷榓尦)擭5寧27擔怰敾丂壠掚偺朄偲嵸敾28崋131暸]
[帠幚偺奣梫]
儀僩僫儉嵼廧偺擔杮恖晇晈偑儀僩僫儉崙愋偺巕偲偺摿暿梴巕墢慻傪擔杮偺壠掚嵸敾強偵怽棫偰偨丅儀僩僫儉偱偼偡偱偵梴巕墢慻偑擣傔傜傟偰偄偨丅
擔杮偺嵸敾強偺娗妽偺桳柍偼怰敾摍偺怽棫帪傪婎弨偲偟偰寛掕偝傟傞(壠帠帠審庤懕朄3忦偺15乯偲偙傠丄杮審偼2018(暯惉30)擭拞偵怽棫偰傜傟偰偍傝丄杮審怽棫偰帪偵偍偄偰丄杮審偵娭偡傞崙嵺嵸敾娗妽偺柧妋側婯掕偼懚嵼偟側偐偭偨丅
偦偺屻丄2019(暯惉31)擭4寧傛傝巤峴偝傟偨恖帠慽徸朄摍偺堦晹傪夵惓偡傞朄棩偵傛傝丄梴巕墢慻偺嵸敾娗妽偵偮偄偰偼丄乽梴恊偲側傞傋偒幰枖偼梴巕偲側傞傋偒幰偺廧強(廧強偑側偄応崌枖偼廧強偑抦傟側偄応崌偵偼丄嫃強)偑擔杮崙撪偵偁傞偲偒偼丄娗妽尃傪桳偡傞乿(壠帠帠審庤懕朄3忦偺5)偙偲偲側偭偨偑丄偄偢傟偵偟偰傕怽棫帪偵偼丄杮審偼丄柧妋偵擔杮偺嵸敾強偵嵸敾娗妽偑擣傔傜傟傞帠埬偱偼側偐偭偨丅
[怰敾偺奣梫]
儀僩僫儉偱梴巕墢慻偑惉棫偟偰偄偨偲偟偰傕丄彨棃丄枹惉擭幰偑棃擔偟偨嵺偺懾嵼婜娫傗廇妛摍偵偍偗傞巟忈傪夞旔偡傞偨傔偵夵傔偰擔杮偵偍偄偰摿暿梴巕墢慻傪惉棫偝偣傞昁梫偑偁偭偨偙偲丄怽棫恖傜偑庡偲偟偰儀僩僫儉偱惗妶偟偰偄傞傕偺偺1擭偺偆偪憡摉婜娫偼擔杮偵懾嵼偟偰偄傞偙偲丄懾嵼帪偵偼擔杮偱偺梴恊偺搊榐廧強抧偵懾嵼偟偰偍傝偦傟偼嫃強偲傕偄偊傞偙偲丄梴恊偼偄偢傟傕擔杮崙愋幰偱偁傞偙偲摍偺彅帠忣傪峫椂偟偰丄寢壥偲偟偰嵸敾偺嫅斲偲側傞偙偲傪夞旔偡傞偨傔偺偄傢備傞嬞媫娗妽揑側崙嵺嵸敾娗妽偑擣傔傜傟偨丅
偦偟偰丄偡偱偵儀僩僫儉偵偍偄偰梴巕墢慻偑桳岠偵惉棫偟偰偄傞偆偊丄擔杮偺壠掚嵸敾強挷嵏姱偵偍偄偰傕挷嵏偑側偝傟偰巕偺暉巸偐側偆偙偲偑妋擣偝傟偨偙偲偐傜丄摿暿梴巕墢慻偑擣梕偝傟偨丅
俀侽侾係丏俀丏侾侽
恊偺摨堄偑側偔偰傕摿暿梴巕墢慻偑擣傔傜傟偨帠椺
[塅搒媨壠嵸2014乮暯惉26乯擭2寧10擔怰敾丂2014擭4寧9擔晅枅擔怴暦挬姧]
[帠幚偺奣梫]
弌惗捈屻偐傜彈帣傪7擭娫堢偰偰偒偨撊栘導偺50戙偺晇晈偑丄彈帣偲摿暿梴巕墢慻偺惉棫傪媮傔偨丅側偍丄彈帣偼幚偺恊偐傜媠懸傪庴偗偨宱尡偼側偄丅
[怰敾偺奣梫]
枅擔怴暦偺曬摴偵傛傞偲丄怰敾偼丄乽幚偺恊偐傜偼彈帣偲偺岎棳傗宱嵪揑巟墖偺怽偟弌傕側偄丅怴偨側恊巕娭學傪抸偔偙偲偑巕偺暉巸偺偨傔偵側傞乿偲偟偰丄幚偺恊偺摨堄偑側偔偰傕丄摿暿梴巕墢慻偺惉棫傪擣傔偨丅
[傂偲偙偲]
柉朄817忦偺6偼丄摿暿梴巕墢慻偺惉棫偵偼尨懃偲偟偰幚晝曣偺摨堄傪偲偟丄媠懸偑偁傞摍椺奜揑側応崌偼椺奜偲偟偰摨堄傪梫偟側偄偲偟偰偄傞丅杮審帠埬偱偼晇晈偼偙傟傑偱2搙丄塅搒媨壠嵸偵彈帣偲偺摿暿梴巕墢慻傪媮傔偨偑丄偄偢傟傕幚偺恊偺摨堄偑側偄偲偟偰戅偗傜傟偰偄偨偲偄偆丅
俀侽侾俀丏俁丏俀
惈暿偺庢傝埖偄傪彈惈偐傜抝惈偵曄峏偡傞巪偺怰敾傪庴偗偨晇偲丄偦偺嵢偑丄戞嶰幰偐傜惛巕偺採嫙傪庴偗偰嵢偑弌嶻偟偨巕偲偺娫偵摿暿梴巕墢慻傪怽偟棫偰丄摨怽棫偰偑擣傔傜傟偨帠椺
[恄屗壠嵸2012(暯惉24)擭3寧2擔怰敾丂壠寧65姫6崋112暸]
[帠幚偺奣梫]
怽棫恖晇偼丄2007擭偵惈暿偺庢傝埖偄傪彈惈偐傜抝惈傊曄峏偡傞巪偺怰敾傪庴偗丄2008擭偵怽棫恖嵢偲寢崶傪偟偨丅偦偺屻丄椉幰偼戞嶰幰偺惛巕採嫙傪庴偗丄2010擭偵丄怽棫恖嵢偑巕傪弌嶻偟偨丅摨晇晈偼丄摉奩巕傪宲懕偟偰娔岇丒梴堢偟偰偄傞丅偦偟偰丄2011擭偵摨晇晈偼丄摉奩巕傪摿暿梴巕偲偡傞摿暿梴巕墢慻惉棫偺怽棫偰恄屗壠掚嵸敾強偵懳偟偰峴偭偨丅
[寛掕偺奣梫]
杮寛掕偼丄摿暿梴巕墢慻偺奺梫審偵偮偄偰丄偙傟傑偱偺宱堒摍偺帠幚傪擣掕偟偨忋偱丄柉朄817忦偺3偐傜摨忋偺6媦傃8偺婯掕偡傞梫審傪慡偰廩偨偡偲敾抐偟偨丅側偍丄柉朄817忦偺6(幚晝曣偺摨堄)偵偮偄偰偼丄乽惛巕採嫙幰偺摨堄偼側偄偑丄惛巕採嫙幰偼丄帠審杮恖(巕)傪擣抦偟偰偍傜偢丄朄棩忋帠審杮恖偺晝偲偄偊側偄偐傜丄偦偺摨堄偼晄梫偱偁傞偲夝偝傟傞乿偲偟偨丅
偝傜偵丄摨忦偺7偺梫審(巕偺棙塿偺偨傔偺摿暿偺昁梫惈)偵偮偄偰偼丄乽帠審杮恖偺弌惗偺宱堒傗偦偺屻偺娔岇忬嫷摍偵徠傜偡偲丄杮審摿暿梴巕墢慻偵偼丄帠審杮恖偲惛巕採嫙幰偲偺恊巕娭學傪抐愨偝偣傞偙偲偑憡摉偱偁傞偲偄偊傞偩偗偺摿暿偺帠忣偑偁傝丄帠審杮恖偺棙塿偺偨傔偵摿偵昁梫偱偁傞偲擣傔傜傟傞偐傜丄偦偺梫審傪廩偨偡偲偄偊傞乿偲敾抐偟偨忋偱丄怽棫恖傜偺摿暿梴巕墢慻惉棫偺怽棫偰傪憡摉偲偟丄摨恖傜偺娫偵摿暿梴巕墢慻傪惉棫偝偣偨丅
俀侽侾俀丏俀丏俀俁
梴巕偲側傞幰偑6嵨偵払偡傞慜偐傜堷偒懕偒梴恊偲側傞幰偵娔岇偝傟偰偄偨(柉朄817忦偺5扐彂)偲偟偰摿暿梴巕墢慻傪惉棫偝偣偨帠椺丅
[嵸敾強]暉壀崅嵸
[擭寧擔]2012(暯惉24)擭2寧23擔寛掕
[弌揟]壠寧64姫9崋48暸
[帠幚偺奣梫]
峈崘恖X晇嵢偼摿暿梴巕墢慻傪帇栰偵擖傟偰丄暯惉17擭偵仜仜導偺仜仜僙儞僞乕偵棦恊搊榐傪偟丄暯惉18擭偵帠審杮恖(摉帪3嵨9僇寧)傪徯夘偝傟偨丅偦偺屻丄X晇嵢偼帠審杮恖偲偺娫偱丄柺夛丄奜攽偵傛傞岎棳傪懕偗偨丅忋婰僙儞僞乕偼丄暯惉20擭偵X晇嵢偵懳偟丄棦恊埾戸寛掕傪偡傞梊掕偩偭偨偑丄晇晈偺堦曽偺擖堾偵傛傝墑婜偝傟丄忋婰僙儞僞乕偼暯惉21擭偵6嵨2僇寧偺帠審杮恖偵偮偒棦恊埾戸寛掕傪偟偨丅帠審杮恖偼杮審摿暿梴巕墢慻怽棫偰帪(暯惉22擭)偵偼丄7嵨11僇寧偵側偭偰偄偨丅
尨怰偼柉朄817忦偺5偨偩偟彂偺乽堷偒懕偒乿偺娔岇偑側偄偲偟偰怽棫偰傪媝壓偟偨丅X晇嵢偼峈崘偟偨丅
[寛掕偺奣梫]
柉朄817忦偺5扐彂偺庯巪偼丄摿暿梴巕偲側傞幰偑6嵨枹枮偺帪偐傜梴恊偲側傞幰偵尰幚偵娔岇偝傟偰偄傞応崌偵偼丄偦偺帪偐傜帠幚忋偺恊巕娭學偑偁傞傕偺偲偄偊傞偙偲偐傜丄擭楊梫審偺娚榓傪擣傔偨傕偺偱偁傞偲偟偨丅
杮審偺応崌丄嘆X晇嵢偑摿暿梴巕墢慻傪棙梡偡傞偙偲傪憐掕偟偰棦恊搊榐傪偟丄帠審杮恖偲岎棳傪怺傔偰偄傞偙偲丄嘇暯惉20擭偵棦恊埾戸寛掕傪梊掕偟偰偄偨偙偲丄嘊X晇嵢偺堦曽偺擖堾偺偨傔摨寛掕偑墑婜偝傟偨傕偺偺寛掕偑庢傝傗傔偲側偭偨傕偺偱偼側偄偙偲丄嘋X晇嵢偺堦曽偑擔忢惗妶偵暅婣屻丄棦恊埾戸寛掕傪懸偪朷傒丄帠審杮恖偲廬慜埲忋偺昿搙側偄偟枾搙偱岎棳傪帩偭偰偄偨偙偲丄嘍帠審杮恖偑暯惉19擭崰偐傜X晇嵢偺偙偲傪乽偍晝偝傫乿乽偍曣偝傫乿偲屇傇傛偆偵側偭偰偄偨偙偲丄嘐帠審杮恖偑X晇嵢戭傪帺戭偲擣幆偟巒傔丄X晇嵢戭偱偺惗妶傪朷傓傛偆偵側偭偰偄偨偙偲丄嘑X晇嵢傕帠審杮恖偵懳偟晝曣偲偟偰愙偟偰椙岲側娭學傪抸偄偰偄偨偙偲丄嘒杮審婡娭(忋婰僙儞僞乕)傕丄帠審杮恖偲X晇嵢偑摿暿梴巕墢慻傪峴偆傕偺偲擣幆偟丄偦偺傛偆偵巜摫偟偰偄偨偙偲傪巜揈偟丄偙傟傜偺帠幚偵傛傟偽丄帠審杮恖偑6嵨偵払偡傞埲慜偐傜丄帠審杮恖偵懳偟偰丄憡摉掱搙丄捈愙揑側娔岇傪峴偆婡夛偑偁傝丄X晇嵢偺傒側傜偢丄杮審婡娭丄偦偟偰杮審巤愝偵偍偄偰傕丄X晇嵢偑棦恊偲偟偰帠審杮恖偵愙偟偰偄傞傕偺偲擣幆偟偰偄偨偙偲傪擣傔傞偙偲偑偱偒傞偺偱偁傝丄X晇嵢偺堦曽偑擔忢惗妶偵栠傝丄帠審杮恖偲枾愙側岎棳傪嵞奐偟偨暯惉20擭崰偐傜偼丄X晇嵢傜偵傛傞帠審杮恖偺娔岇偑偝傟偰偄偨傕偺偲偄偆傋偒偱偁傞偲偟偰丄柉朄817忦偺5扐彂偺梫審傪枮偨偡傕偺偲偟偰摿暿梴巕墢慻傪惉棫偝偣偨丅
[傂偲偙偲]
尨怰偼摉帠幰偺堄巚丒擣幆偵偼尵媦偣偢丄岎棳偺掱搙傗棦恊埾戸寛掕偑峴傢傟傞傑偱偺宱夁傪尩奿偵偲傜偊丄乽堷偒懕偒乿偺娔岇偑側偄偙偲傪棟桼偵怽棫偰傪媝壓偟偨丅
堦曽偱丄杮寛掕偼丄柉朄817忦偺5扐彂偺庯巪傪丄摿暿梴巕偲側傞幰偑6嵨枹枮偺帪偐傜梴恊偲側傞幰偵尰幚偵娔岇偝傟偰偄傞応崌偵偼丄偦偺帪偐傜帠幚忋偺恊巕娭學偑偁傞傕偺偲偄偊傞偲偙傠偐傜丄擭楊梫審傪娚榓偟偨傕偺偱偁傞偲偟偨忋偱丄帠審杮恖偲X晇嵢偺岎棳忬嫷傗丄帠審杮恖傗X晇嵢丄娭學婡娭偺堄巚丒擣幆摍傪峫椂偟偰丄柉朄817忦偺5扐彂偺梫審傪枮偨偡偲敾抐偟偨丅巕偺暉巸偵偐側偆敾抐偲峫偊傜傟傞丅
俀侽侾侽丏俋丏俁
擣抦徢摍偵滊姵偟偨梴恊偵梴巕墢慻偺堄巚偑側偐偭偨偲偟偰梴巕墢慻柍岠妋擣惪媮偑擣梕偝傟偨帠椺
[嵸敾強]柤屆壆壠嵸
[擭寧擔]2010(暯惉22)擭9寧3擔敾寛
[弌揟]敾僞1339崋188暸
[帠幚偺奣梫]
崅楊偺壋栰攡偼丄暯惉15擭崰丄懱椡偑悐偊丄挿彈暩愳嶗巕晇晈傗摨晇晈偺巕壴巕偺悽榖傪庴偗傞傛偆偵側傝丄暯惉16擭崰偐傜丄壴巕偲偺梴巕墢慻傪朷傓敪尵傪偟偨丅懠曽丄攡偼丄擇抝晇晈偐傜悽榖傪庴偗傞偙偲傕偁傝丄擇抝偺嵢偵懳偟偰偼帺暘偺悽榖傪摨恖偵埶棅偡傞敪尵傪偟偰偄偨丅
攡偼丄暯惉19擭1寧丄崅寣摐惈崹悋偺偨傔峛昦堾偵擖堾偟丄擣抦徢丄摐擜昦摍偲恌抐偝傟丄帇椡畻庭尵岅偲傕憡摉掅壓偟丄曕峴丄怘帠丄峏堖丄擖梺丄愻柺丄攔煏偵偮偒慡柺揑偵夘彆偑昁梫側忬懺偱偁偭偨丅揮堾愭偺壋昦堾偵偍偄偰傕丄擣抦徢丄摐擜昦摍偲恌抐偝傟丄怮偨偒傝丄堓釕偐傜偺宱挵塰梴丄幐岅偺徢忬傪掓偟丄扴摉堛偲堄巚慳捠傪偡傞偙偲偑偱偒側偄忬懺偱偁偭偨丅
偙偺忬嫷壓偱丄攡偺晇懢榊偑暩愳嶗巕偵懳偟丄攡偺堄巚偵婎偯偒攡偲壴巕娫偱墢慻傪偡傞巪揱偊丄嶗巕晇晈媦傃壴巕偑偙傟傪彸戻偡傞偵帄偭偨丅墢慻撏偺乽梴恊偵側傞恖乿棑偵攡偺晇懢榊偑攡偺彁柤墴報傪偟丄乽梴巕偵側傞恖乿棑偵偼壴巕偑彁柤墴報偟偰墢慻撏偑嶌惉偝傟丄暯惉19擭11寧丄壴巕傜偵傛偭偰採弌偝傟偨丅攡偺屻尒恖倃偼丄壴巕偵懳偟丄墢慻柍岠妋擣偺慽徸傪採慽偟偨丅
[敾寛偺奣梫]
(攡偺)峴摦傗丄摨恖偺摉帪偺擭楊S恎忬懺偐傜偡傞偲丄摨恖偺曎幆椡粧f椡摍偵偐側傝偺悐偊偑偁偭偨偲擣傔傜傟丄偦偺応偺忬嫷師戞偱偼丄堄巚偺擛壗偲偼暿偵丄偨傗偡偔恎嬤側恖偺堄岦偵増偆敪尵傪偡傞傛偆側惛恄忬懺偵偁偭偨偲悇擣偱偒傞丅傑偨丄攡偑峛昦堾偵擖堾偟偨屻偵偍偄偰偼丄壴巕傗嶗巕晇晈偼丄懢榊傪捠偠偰攡偺墢慻堄巚傪妋擣偡傞偺傒偱偁偭偨偲偄偆偺偱偁傝丄幚嵺偵懢榊偑攡偺墢慻堄巚傪妋擣偟偨帠幚傪擣傔傞偵懌傝傞揑妋側徹嫆偼側偄丅偟偨偑偭偰丄攡偑旐崘偲偺梴巕墢慻傪婓朷偡傞敪尵傪偟偨偐傜偲偄偭偰丄恀偵旐崘偲偺梴巕墢慻偺堄巚偑偁偭偨偲尵偆偙偲偼偱偒側偄丅
偺傒側傜偢丄忋婰擣掕帠崁偵徠傜偣偽丄攡偼丄帺傜杮審墢慻撏偵帺彁墴報偟偰偍傜偢丄懢榊偑杮審墢慻撏偺乽梴恊偵側傞恖乿棑偺強掕帠崁媦傃攡偺彁柤墴報傪峴偭偨偵偡偓偢丄攡偑丄杮審梴巕墢慻偵摉偨偭偰丄懢榊偵杮審墢慻撏偺彁柤墴報偺戙峴傪埶棅偟偨帠幚傗丄杮審梴巕墢慻傪捛擣偟偨帠幚傪擣傔傞偵懌傝傞媞娤揑側徹嫆偼側偄丅
偟偐傕丄攡偼丄杮審梴巕墢慻偺栺10僇寧慜偺暯惉19擭1寧19擔偵崅寣摐惈崹悋偵娮偭偰峛昦堾偵擖堾偟丄摨擭6寧18擔偵壋昦堾偵揮堾偟偰偄傞偲偙傠丄擣抦徢摍偲恌抐偝傟丄怮偨偒傝偺偨傔慡柺揑偵夘彆偑昁梫側忬嫷偵偁傝丄堛巘摍偺栤偄偐偗偵斀墳偣偢丄屇柤偵乽偼乕乿偲墳偊傞偺傒偱丄堄枴晄柧偺婏惡傪敪偟丄堄巚慳捠偑壜擻側忬嫷偱偼側偐偭偨偺偱偁傞偐傜丄杮審梴巕墢慻傪峴偆偵懌傝傞堄巚擻椡偑偁偭偨偲偼擣傔擄偄丅
[傂偲偙偲]
梴巕墢慻偵昁梫側乽墢慻堄巚乿偼丄幚嵺偵梴恊巕娭學傪宍惉偡傞堄巚乮幚幙揑堄巚乯偱偁傞偲偝傟傞偑丄崅楊偵側傝梴恊偺敾抐擻椡偑掅壓偟偨抜奒偱墢慻偑峴傢傟傞偙偲傕彮側偔側偄丅傑偨丄崅楊幰偼丄暋悢偺巕傗懛偦傟偧傟偵丄懡彮寎崌偟偰堎側傞堄巚昞帵傪偟偰偄傞偙偲偼捒偟偔側偔丄杮審傕偦偺堦椺偱偁傞丅偐偮丄擣抦徢偺掱搙傪峫椂偟丄墢慻傪峴偆偵懌傝傞擻椡偑側偐偭偨偲擣掕偝傟偨丅堚尵柍岠偲摨偠偔丄憡懕偵捈寢偡傞偺偱丄崱屻傕摨條偺暣憟偼懕偔偲巚傢傟傞丅
俀侽侽俋丏俉丏侾係
恄怑傪悽廝偡傞幮壠偺彸宲傪庡側栚揑偲偟偰丄枹惉擭幰偵偮偄偰梴巕墢慻嫋壜偺怽棫偰傪偟偨偑丄媝壓偝傟偨帠椺
[嵸敾強]嵅夑壠嵸
[擭寧擔]2009(暯惉21)擭8寧14擔怰敾
[弌揟]壠寧62姫2崋142暸
[帠幚偺奣梫]
怽棫恖(摉帪85嵨)偺攝嬼幰偺惗壠偼丄乑乑恄媨偺偄傢備傞幮壠偲偟偰丄戙乆恄媨傪攜弌偟偰偒偨壠宯偱偁傝丄怽棫恖偺攝嬼幰傕幮壠傪彸宲偟丄乑乑恄媨偺戝嵳偺巟墖傗抧堟妶摦偵廬帠偟偰偒偨丅怽棫恖傜晇晈偼丄幚巕偑偄側偄偨傔丄彨棃丄怽棫恖偺柮偺巕偺擇抝偱偁傞枹惉擭幰(10嵨)偵幮壠傪彸宲偟偰傕傜偆偨傔丄梴巕偲偟偨偄偲婓朷偟偰偄傞丅枹惉擭幰偺椉恊偼梴巕墢慻傪彸戻偟偨偑丄墢慻屻傕枹惉擭幰偲堦弿偵惗妶偟娔岇梴堢偟偨偄偲峫偊偰偄傞丅怽棫恖偼攝嬼幰偲偲傕偵丄壠掚嵸敾強偵梴巕墢慻嫋壜偺怽棫偰傪偟偨丅側偍丄怽棫偰屻偵怽棫恖偺攝嬼幰偑巰朣偟偨偨傔丄攝嬼幰偺怽棫偰偵學傞晹暘偼帠審偑廔椆偟偰偄傞丅
[怰敾偺奣梫]
恄怑傪悽廝偡傞幮壠偺彸宲傪庡側栚揑偲偡傞梴巕墢慻偵偮偄偰丄枹惉擭幰偑杮審梴巕墢慻偵傛傝憡懕摍傪捠偠偰怽棫恖強桳偺晄摦嶻傪忳傝庴偗傞偙偲偵側傞偲偄偆嵿嶻忋偺棙塿偑側偄偱偼側偄傕偺偺丄彨棃偼丄忋婰晄摦嶻偵嫃廧偟丄幮壠傪宲偄偱偦偺妶摦偵廬帠偡傞偙偲偑嫮偔婜懸偝傟傞偙偲偵側傝丄枹惉擭幰偺彨棃傪偐側傝惂栺偡傞壜擻惈偑惗偠傞偙偲丄幚晝曣偑偙傟傪彸戻偟丄枹惉擭幰傕堦墳椆夝偡傞堄岦傪帵偟偰偄傞偲偟偰傕丄枹惉擭幰偼10嵨偱偁傝丄帺暘偺彨棃愝寁偵偮偄偰揑妋偵敾抐偟摼傞偩偗偺擻椡傪旛偊偰偄傞偲偼偄偊偢丄杮審梴巕墢慻偺栚揑傗幮壠偺栶妱摍傪廫暘偵棟夝偡傞偵偼帄偭偰偄側偄偙偲丄崱屻傕堷偒懕偒幚晝曣偺壓偱揔愗偵娔岇梴堢偝傟傞偙偲偑婜懸偝傟傞忬嫷偵偁傞偙偲側偳偺帠忣偵徠傜偡偲丄尰帪揰偵偍偄偰杮審梴巕墢慻偼枹惉擭幰偺暉巸偵偐側偆偲偼偄偊偢丄偙傟傪嫋壜偡傞偙偲偼偱偒側偄丅傛偭偰丄杮審怽棫偰偼媝壓偡傞丅
[傂偲偙偲]
枹惉擭幰傪梴巕偵偡傞応崌偵尨懃偲偟偰壠掚嵸敾強偺嫋壜偑昁梫偵側傞偑(柉朄798忦)丄廬棃丄壠柤彸宲傗嵳釰彸宲幰偺妋曐傪栚揑偲偡傞怽偟棫偰偼嫋壜偝傟偰偄側偄丅杮審傕幮壠偺彸宲偑庡側栚揑偲偝傟丄枹惉擭幰偺暉巸傪峫椂偟丄媝壓偝傟偨丅
俀侽侽俋丏俉丏俇
擣抦徢偺榁恖偺偟偨梴巕墢慻撏弌偑墢慻堄巚傪寚偒柍岠偲偝傟偨椺
[嵸敾強]搶嫗崅嵸
[擭寧擔]2009(暯惉21)擭8寧6擔敾寛
[弌揟]敾僞1311崋241暸
[尨怰]搶嫗壠嵸2009(暯惉21)擭1寧22擔敾寛
[帠幚偺奣梫]
峛彈偼丄暯惉16擭丄慡嵿嶻傪峛彈偺朣巓偺挿抝偱偁傞X抝偺媊棟偺巓壋彈偵堚憽偡傞巪偺岞惓徹彂堚尵(嘆堚尵)傪嶌惉偟偨偑丄暯惉18擭9寧偵偼丄峛彈偲偦偺朣晇偺巓偺懛偱偁傞Y彈偵慡嵿嶻傪憡懕偝偣傞巪偺堚尵彂(嘇堚尵)傪嶌惉偟偨丅偟偐偟丄嘇堚尵偼丄堚尵彂偲偟偰偺條幃傪旛偊偰偄側偄柍岠偺傕偺偱偁偭偨丅
暯惉18擭11寧埲崀丄峛彈偼傾儖僣僴僀儅乕宆榁擭惈抯曫偁傞偄偼抯曫媈偲恌抐偝傟偨丅
偝傜偵暯惉19擭1寧丄峛彈偼Y彈偲梴巕墢慻傪偟偨丅偙偺墢慻偑側偝傟傞嵺丄峛彈偵懳偟偰丄嘆堚尵偵偮偄偰偺愢柧偑側偝傟偨傝丄嘆堚尵偺撪梕偲梴巕墢慻偺椉幰傪懳斾偟偰峛彈偺堄巚偺妋擣偑側偝傟偨傝偡傞偙偲偼側偐偭偨丅
側偍丄峛彈偺朄掕憡懕恖偼X抝偺傒偱偁偭偨偑丄忋婰梴巕墢慻偑側偝傟傞偙偲偵傛傝丄朄掕憡懕恖偼Y彈偺傒偲側偭偨丅
X抝偼丄忋婰梴巕墢慻偼丄峛彈偺墢慻堄巚傪寚偒柍岠偱偁傞偲偟偰丄梴巕墢慻柍岠妋擣慽徸傪採婲丅尨怰偑偙傟傪擣梕偟丄Y彈偑峊慽偟偨丅
[敾寛偺奣梫]
峛彈偵偼丄榁擭惈擣抦徢偺徢忬偑弌傞慜偐傜丄壋彈偵慡嵿嶻傪忳傝偨偄偲偄偆堄巚偲丄Y彈偵慡嵿嶻傪忳傝偨偄堄巚偲偑暪懚偟偰偍傝丄偳偪傜偐堦曽偑恀堄偱偁傞偲偼尵偊側偄忬懺偱偁偭偨偲擣掕偟偨忋偱丄偙偺傛偆側忬嫷偐傜偡傞偲丄忋婰梴巕墢慻撏偼丄峛彈偺擇偮偺憡柕弬偡傞堄巚偺偆偪偺堦偮偵婎偯偔傕偺偱偁傝丄榁擭惈擣抦徢偵滊姵偟偰挊偟偄婰柫椡丒婰壇椡忈奞偑惗偠偰偄傞峛彈偵偮偄偰偼丄乽懠偺峫偊偑懚偡傞偙偲傪拲堄姭婲偟偨忋偱丄帺傜偺敾抐偵傛傝柕弬偡傞擇偮偺堄巚偺偄偢傟偐傪慖戰偡傞傛偆懀偡偙偲偑側偄尷傝丄憡柕弬偡傞擇偮偺堄巚偺偄偢傟偐傪桪墇偟偨堄巚偲偟偰擣傔傞偙偲偼偱偒側偄忬嫷偵偁偭偨乿偲偟偰丄寢嬊丄忋婰梴巕墢慻偼丄峛彈偺墢慻堄巚傪寚偒柍岠偱偁傞偲偟偨丅
[傂偲偙偲]
擣抦徢偺榁恖偑憡柕弬偡傞擇偮偺堄巚傪桳偟偰偄偨偲偟丄偦偺偆偪偺堦偮偵婎偯偔墢慻堄巚傪斲掕偟偨働乕僗丅
俀侽侽俋丏俆丏俀侾
幚晝偺摨堄偑側偄偑丄摨堄尃偺棓梡偵偁偨傞偲偟偰摿暿梴巕墢慻傪惉棫偝偣偨帠椺
[嵸敾強]惵怷壠嵸屲強愳尨巟晹
[擭寧擔]2009(暯惉21)擭5寧21擔怰敾
[弌揟]壠寧62姫2崋137暸
[帠幚偺奣梫]
暯惉16擭丄1嵨10僇寧偺A傪棦恊埾戸偝傟偨怽棫恖晇晈偼丄摨擭偵A偲偺摿暿梴巕墢慻偺怰敾傪怽偟棫偰偨偑丄A偺幚晝偺摨堄偑摼傜傟側偐偭偨偙偲偐傜偄偭偨傫怽棫偰傪庢傝壓偘偨丅怽棫恖晇晈偼偦偺屻傕A傪惗堢偟丄暯惉20擭偵丄嵞搙A偲偺摿暿梴巕墢慻偺怰敾傪怽偟棫偰偨丅
側偍丄A偺幚孼傕丄帣摱憡択強傊偺捠崘傗擕帣堾傊偺擖強慬抲摍偑孞傝曉偝傟偰偄偨丅A偺幚晝曣偼棧崶偟丄幚晝偼丄嵞崶幰偲偺娫偵巕傪傕偆偗偰偄傞偑丄偦偺巕偵偮偄偰傕帣摱梴岇巤愝傊偺擖強傗棦恊埾戸摍偑側偝傟偰偄偨丅堦曽幚曣偼丄傾儖僶僀僩摍傪偟偮偮抝惈偲摨惐偡傞側偳偺惗妶傪憲偭偰偍傝丄A偺摿暿梴巕墢慻偵摨堄偟偰偄偨丅
[怰敾偺奣梫]
怽棫恖晇晈偼丄宱嵪揑丒幮夛揑偵埨掕偟偰偄傞偙偲丄嫟偵A偵懳偡傞廫暘側垽忣偵棤晅偗傜傟偨嫮偄梴堢堄梸傪帵偟偮偮丄A偵懳偟偰揔愗側娔岇梴堢傪宲懕偟偰偄傞偙偲丄媦傃丄A偼1嵨10僇寧偺帪偐傜尰嵼傑偱怽棫恖晇晈偺傕偲偱5擭埲忋偺娫偵傢偨偭偰弴挷偵惗堢偟偰偄傞偙偲傪擣掕偟偨忋偱丄幚晝曣偺奺幚忣偐傜偡傟偽丄巕偺棙塿偺偨傔偺摿暿偺昁梫惈(柉朄817忦偺7)偼擣傔傜傟傞偲偟偨丅
偝傜偵丄幚晝偺摨堄偑側偄揰偵偮偄偰偼丄A偺幚孼偺忬嫷傗幚晝偺嵞崶憡庤偲偺娫偺巕偺忬嫷丄幚晝偑A堷偒庢傝偺庤懕傪壗傜偟偰偄側偄偙偲丄幚晝偺徠夛彂摍傊偺晄墳摎丄怰敾婜擔傊偺晄弌摢側偳偺帠幚偐傜偡傟偽丄幚晝偺晄摨堄偼摨堄尃偺棓梡偵摉偨傞偲偟偰丄巕偺棙塿傪挊偟偔奞偡傞帠桼偑偁傞応崌(柉朄817忦偺6扐彂)偵奩摉偡傞偲偟偨丅
俀侽侽俋丏俆丏侾俆
嘆憡懕嵿嶻朄恖偑梴巕墢慻柍岠妋擣慽徸偺尨崘揔奿傪桳偡傞丄嘇嵿嶻傪憡懕偝偣傞偙偲偺傒傪栚揑偲偟偰峴傢傟偨梴巕墢慻偼墢慻堄巚傪寚偒柍岠偱偁傞丄偲偟偨帠椺
[嵸敾強]戝嶃崅嵸
[擭寧擔]2009(暯惉21)擭5寧15擔敾寛
[弌揟]敾帪2067崋42暸
[帠幚偺奣梫]
A偼丄晇巰朣屻丄椬恖偺B偵恎偺夞傝偺悽榖傪偟偰傕傜偭偰偄偨丅B偺挿彈Y乮峊慽恖乯偼丄B偲摨嫃偟偰偍傝丄椬恖偲偟偰A偲柺幆偼偁偭偨傕偺偺丄A偲偺岎棳偼慡偔側偐偭偨丅暯惉14擭丄A偼帩昦偑埆壔偟偰擖堾偟偨偑丄擖堾拞偵丄A傪梴恊丄Y傪梴巕偲偡傞墢慻撏偑嶌惉偝傟丄B偑杮審墢慻撏傪栶強偵採弌偟偨丅A偺擖堾拞丄B偑A偺悽榖傪偟偰偍傝丄Y偼壗夞偐尒晳偄偵朘傟偨偺傒偱偁偭偨丅A偺戅堾屻傕丄A偺恎偺夞傝偺悽榖偼愱傜B偑峴偭偰偍傝丄Y偑峴偆偙偲偼側偔丄Y偑A偺壠偵攽傑偭偨偙偲傕側偐偭偨丅傑偨丄Y偼丄A偺恊懓娭學傪攃埇偟偰偍傜偢丄摨恖偐傜巰屻偺嵳釰偵偮偄偰埶棅偝傟偨偙偲傕側偐偭偨丅暯惉16擭丄A偼嵞擖堾偟昦堾偱巰朣偟偨偑丄偦偺娫丄Y偑A傪尒晳偆偙偲偼傎偲傫偳側偐偭偨丅B枖偼Y偼丄A偑巰朣偟偨梻擔偵A柤媊偺挋嬥岥嵗傪夝栺偟暐栠偟傪庴偗偰偍傝丄梻擭侾寧偵偼丄A偺梐嬥摍偺岥嵗傪夝栺偟暐栠偟傪庴偗丄摨擭2寧偵偼丄Y偑A強桳晄摦嶻偵偮偒憡懕傪尨場偲偡傞強桳尃堏揮搊婰庤懕傪峴偭偰偄傞丅
A偺晇偲偦偺慜嵢偲偺娫偺巕C媦傃D偼丄A偺憡懕嵿嶻娗棟恖偺慖擟傪媮傔傞怰敾傪怽棫偰丄X乮旐峊慽恖乯偑A偺憡懕嵿嶻娗棟恖偲偟偰慖擟偝傟偨丅X偑丄A偺憡懕嵿嶻朄恖傪戙昞偟偰Y偵懳偟丄A傪梴恊丄Y傪梴巕偲偡傞梴巕墢慻偺柍岠妋擣慽徸傪採婲偟偨偲偙傠丄尨怰偼丄杮審慽徸偺揔朄惈傪擣傔偨偆偊丄杮審墢慻偼丄墢慻堄巚傪寚偒柍岠偱偁傞偲偟偰丄X偺惪媮傪擣梕偟偨丅偙傟偵懳偟丄Y偑嘆憡懕嵿嶻朄恖偼梴巕墢慻柍岠妋擣慽徸偺尨崘揔奿傪桳偟側偄丄嘇A媦傃Y偵偼墢慻堄巚偑偁偭偨側偳偲庡挘偟峊慽偟偨丅
[敾寛偺奣梫]
嘆偵偮偄偰乽憡懕嵿嶻朄恖偼丄憡懕奐巒帪偵偍偗傞旐憡懕恖偵懏偟偰偄偨堦愗偺尃棙媊柋媦傃偦偺懠偺朄棩娭學傪彸宲偡傞偺偱偁傞偐傜丄偙偺柺偱偼丄旐憡懕恖偺尃棙媊柋傪彸宲偟偨憡懕恖偲摨條偺抧埵偵偁傞偲偄偆偙偲偑偱偒傞乿乽A偺憡懕嵿嶻朄恖偱偁傞旐峊慽恖偼丄杮審梴巕墢慻偑柍岠偱偁傞偐斲偐偵傛偭偰憡懕偵娭偡傞抧埵偵捈愙塭嬁傪庴偗傞幰偲偟偰丄杮審梴巕墢慻偺柍岠妋擣傪媮傔傞朄棩忋偺棙塿傪桳偡傞偲偄偆傋偒偱偁傝丄尨崘揔奿傪寚偔偲偼偄偊側偄丅乿
嘇偵偮偄偰乽柉朄802忦1崋偵偄偆乽墢慻傪偡傞堄巚乿乮墢慻堄巚乯偲偼丄恀偵幮夛捠擮忋恊巕偱偁傞偲擣傔傜傟傞娭學偺愝掕傪梸偡傞堄巚傪偄偆傕偺偲夝偡傋偒偱偁傝丄偟偨偑偭偰丄偨偲偊墢慻偺撏弌帺懱偵偮偄偰摉帠幰娫偵堄巙偺崌抳偑偁傝丄傂偄偰偼丄摉帠幰娫偵丄堦墳朄棩忋偺恊巕偲偄偆恎暘娭學傪愝掕偡傞堄巚偑偁偭偨偲偄偊傞応崌偱偁偭偰傕丄偦傟偑丄扨偵懠偺栚揑傪払偡傞偨傔偺曋朄偲偟偰梡偄傜傟偨傕偺偱丄恀偵恊巕娭學偺愝掕傪梸偡傞堄巚偵婎偯偔傕偺偱側偐偭偨応崌偵偼丄墢慻偼丄摉帠幰偺墢慻堄巚傪寚偔傕偺偲偟偰丄偦偺岠椡傪惗偠側偄傕偺偲夝偡傋偒偱偁傞丅偦偟偰丄恊巕娭學偼昁偢偟傕嫟摨惗妶傪慜採偲偡傞傕偺偱偼側偄偐傜丄梴巕墢慻偑丄庡偲偟偰憡懕傗晑梴偲偄偭偨嵿嶻揑側娭學傪抸偔偙偲傪栚揑偲偡傞傕偺偱偁偭偰傕丄捈偪偵墢慻堄巚偵寚偗傞偲偄偆偙偲偼偱偒側偄偑丄摉帠幰娫偵嵿嶻揑側娭學埲奜偵恊巕偲偟偰偺恖娫娭學傪抸偔堄巚偑慡偔側偔丄弮悎偵嵿嶻揑側朄棩娭學傪嶌弌偡傞偙偲偺傒傪栚揑偲偡傞応崌偵偼丄墢慻堄巚偑偁傞偲偄偆偙偲偼偱偒側偄丅乿乽杮審梴巕墢慻偵傛傞恊巕娭學偺愝掕偼丄B偺庡摫偺傕偲丄愱傜丄恎婑傝偺側偄A偺嵿嶻傪峊慽恖偵憡懕偝偣傞偙偲偺傒傪栚揑偲偟偰峴傢傟偨傕偺偲悇擣偡傞傎偐偼側偄丅埲忋偵傛傟偽丄杮審梴巕墢慻偼丄摉帠幰偺墢慻堄巚傪寚偔偙偲偵傛傝丄柍岠偱偁傞偲偄偆傋偒偱偁傞丅乿
[傂偲偙偲]
墢慻堄巚偵偮偄偰偼丄崶堶堄巚摨條丄宍幃堄巚偱懌傝傞偐丄偁傞偄偼幚幙堄巚偑昁梫偐(捠愢丒敾椺)偲偺媍榑偑偁傞丅杮敾寛偼屻幰傪嵦梡偟偨敾椺偺1偮丅乽恀偵幮夛捠擮忋恊巕偱偁傞偲擣傔傜傟傞娭學偺愝掕傪梸偡傞堄巚乿偑昁梫偱偁傞偲偟偰偄傞丅
偟偐偟丄憡懕惻愡惻偁傞偄偼丄嵿嶻憡懕偺偨傔偺懛梴巕偑峀偔擣傔傜傟偰偄傞傛偆偵丄崶堶堄巚偲堎側傝丄幚幙堄巚偺敾抐偼梕堈偱偼側偄丅杮審偼恖娫娭學偑傑偭偨偔側偄偙偲偑億僀儞僩偱偁偭偨傛偆偱偁傞乮A偲B偑墢慻偟偰偄偨傜桳岠偵側偭偨偲巚傢傟傞乯丅
俀侽侽俉丏侾俀丏俀俇
戙棟夰戀幰偲巕偺娫偵曣巕娭學偑惉棫偡傞偲偺嵟崅嵸寛掕傪慜採偲偟偰丄慶曣偑戙棟弌嶻偟偨柡晇晈偺巕偲柡晇晈偲偺摿暿梴巕墢慻偺惉棫傪擣傔偨帠椺
[嵸敾強]恄屗壠嵸昉楬巟晹
[擭寧擔] 2008(暯惉20)擭12寧26擔怰敾
[弌揟]壠寧61姫10崋72暸
[帠幚偺奣梫]
X1媦傃X2偼崶堶偟偨晇晈偱偁傞偑丄X2偼恎懱忋偺棟桼偐傜弌嶻偡傞偙偲偑偱偒側偐偭偨丅偦偙偱丄X2偺幚曣峛偑X1偺惛巕偲X2偺棏巕傪庴惛偝偣偨泱偺堏怉傪庴偗偰擠怭偟丄暩傪弌嶻偟偨(埲壓丄乽杮審戙棟弌嶻乿偲偄偆丅)丅X2偼丄暩偺弌惗偵崌傢偣偰曣擕傪弌偡偨傔偺栻傪堸傒丄暩偵梌偊偨丅傑偨丄X1偲X2偼丄弌嶻屻傑傕側偔暩傪堷偒庢傝丄埲屻栺10儢寧丄暩傪娔岇梴堢偟偰偒偨丅X1媦傃X2偼丄暩偲偺摿暿梴巕墢慻傪怽偟棫偰偨丅
[怰敾偺奣梫]
戙棟弌嶻偺朄惂搙偵偮偄偰偼専摙偺梋抧偑偁傞偲偟偮偮傕丄弌惗偟偨巕偲寣墢忋偺恊偲偺娫偺娭學偵偮偄偰偼丄弌惗偟偨巕偺暉巸傪拞怱偵専摙偡傞偺偑憡摉偲偺尒夝傪帵偟偨忋偱丄杮審偵偍偄偰偼丄X1X2晇晈偺梴恊偲偟偰偺揔奿惈媦傃暩偲偺揔崌惈偵偼偄偢傟傕栤戣偑側偄偙偲丄X1X2偼暩偺寣墢忋偺恊偱偁傝丄暩傪愑擟傪帩偭偰娔岇梴堢偟偰偄偔恀潟側堄岦傪帵偟偰偄傞偙偲丄峛壋晇晈偼X1X2晇晈偑暩傪愑擟傪傕偭偰堢偰傞傋偒偱偁傞偲峫偊偰偍傝丄暩傪帺恎傜偺巕偲偟偰娔岇梴堢偟偰偄偔堄岦偼側偄偙偲側偳偺帠忣傪偁偘丄X1X2偲暩偲偺摿暿梴巕墢慻怽棫偰傪擣傔偨丅
[傂偲偙偲]
戙棟弌嶻偺応崌丄弌惗偟偨巕偺曣偼丄偦偺巕傪夰戀偟弌嶻偟偨彈惈偲側傞偙偲偵偮偄偰偼丄嵟崅嵸寛掕暯惉19擭3寧23擔(俀侽侽俈丏俁丏俀俁)杮審偱偼丄偙偺暯惉19擭嵟寛偺敾抐傪慜採偲偟偮偮丄惛巕媦傃棏巕採嫙幰偱偁傞晇晈偐傜弌惗巕偲偺摿暿梴巕墢慻偺怽棫偰偑側偝傟丄怽棫偰偑擣傔傜傟偨丅
俀侽侽俈丏俋丏俀侽
屻尒恖偑帺屓偺捈宯斱懏偱偁傞枹惉擭旐屻尒恖傪梴巕偲偡傞応崌偺丄壠掚嵸敾強偺嫋壜偺梫斲媦傃怰嵏尃尷偵偮偄偰帵偟偨帠椺
[嵸敾強]戝嶃崅嵸
[擭寧擔]2007(暯惉19)擭9寧20擔寛掕
[弌揟]敾帪2033崋24暸丂敾僞1260崋330暸
[帠幚偺奣梫]
丂丂丂丂倃乮怽棫恖乯
丂丂丂丂乥
丂丂丂丂俙亖俛乮偦偺屻丄A偲B偼棧崶丅A偑恊尃幰偲側傞偑丄媠懸偱恊尃憆幐乯
丂丂丂丂丂乥
丂丂丂丂丂俠
X(怽棫恖)偺挿彈A偼丄B偲偺娫偵C傪弌嶻偟偨丅A偲B偼丄C偺恊尃幰傪A偲掕傔偰嫤媍棧崶偟偨偑丄A偼C偵懳偡傞帣摱媠懸偵傛傝恊尃傪憆幐偟丄X偑C偺枹惉擭屻尒恖偵慖擟偝傟偨丅偦偺屻丄X偼丄C傪梴巕偲偡傞偙偲偺嫋壜傪媮傔傞怰敾傪怽偟棫偰偨丅
尨怰偼丄乽杮審梴巕墢慻偑嫋壜偝傟偰傕丄摉暘丄C偺惗妶偺幚懺偼傎偲傫偳曄傢傜側偄偲偄偆傋偒偱偁傝丄尰帪揰偵偍偄偰偁偊偰X偲C偲偺娫偱梴巕墢慻傪偡傋偒昁梫惈偼朢偟偄丅傓偟傠丄B偑C偺梴堢堄梸傪帵偟偰偄傞偙偲傗C偺擭楊偐傜偡傟偽丄尰帪揰偵偍偄偰B偑恊尃幰偲側傞梋抧傪暵偞偡宍偵偟偰偟傑偆偙偲偼丄憡摉偲偼偄偊側偄丅偙傟傜偺帠忣傪峫椂偡傞偲丄杮審梴巕墢慻偑枹惉擭幰偺暉巸偵揔偆傕偺偲偄偆偙偲偼偱偒側偄乿偲偟偰丄X偺怽棫傪媝壓偟偨丅X偼丄峈崘偟偨丅
[寛掕偺奣梫]
屻尒恖偲旐屻尒恖偺墢慻偵偮偒壠掚嵸敾強偺嫋壜傪昁梫偲掕傔傞柉朄794忦偼丄恊尃幰偲摨條偺嵿嶻娗棟尃傪桳偡傞屻尒恖偑旐屻尒恖偲墢慻偡傞偙偲傪擣傔傞偲丄屻尒恖偺嵿嶻娗棟偵懳偡傞柉朄偺尩奿側婯惂傪夞旔偡傞偙偲偑帠幚忋壜擻偲側傞偙偲偐傜丄偦偺婋尟傪攔彍偡傞庯巪偱愝偗傜傟偨婯掕偲夝偝傟傞丅
師偵丄柉朄798忦偼丄枹惉擭幰傪梴巕偲偡傞偵偼丄壠掚嵸敾強偺嫋壜傪摼傞傋偒偙偲傪掕傔偰偄傞偑丄摨忦偨偩偟彂偒偼丄枹惉擭幰偑帺屓枖偼攝嬼幰偺捈宯斱懏偱偁傞偲偒偼丄偦偺傛偆側墢慻偑摉奩枹惉擭幰偺暉巸偵斀偡傞傛偆側偙偲偼捠忢惗偠側偄偱偁傠偆偲偺棫朄惌嶔忋偺敾抐偐傜丄壠掚嵸敾強偺嫋壜傪晄梫偲偡傞巪掕傔偨傕偺偱偁傞丅
杮審偼丄X偑帺屓偺捈宯斱懏偱偁傞C傪梴巕偲偡傞応崌偱偁傞偐傜丄C偺暉巸妋曐偺娤揰偐傜杮審墢慻偺摉斲傪怰嵏偡傞昁梫偑側偄偙偲偼柧傜偐偱偁傝丄柉朄794忦偺婯掕偺庯巪偵廬偄丄C偺嵿嶻揑抧埵偵懳偡傞婋尟傪攔彍偡傞偲偄偆娤揰偐傜嬦枴傪壛偊傟偽懌傝傞偺偱偁偭偰丄偦偺傛偆側嵿嶻娗棟忋偺栤戣偑擣傔傜傟側偄応崌偵偼丄杮審墢慻偵嫋壜傪晅梌偡傞偺偑憡摉偲偄偆傋偒偱偁傞丅傛偭偰丄尨敾寛傪庢傝徚偟丄梴巕墢慻傪嫋壜偡傞丅
[傂偲偙偲]
柉朄794忦偲798忦偺庯巪偵偮偄偰捠愢揑棫応偵婎偯偄偨夝庍傪帵偟偨忋偱丄杮審偺傛偆側働乕僗偱偼柉朄798忦扐彂偵傛傝嫋壜晄梫偱偁傝丄傑偨枹惉擭幰偺暉巸偵揔偆偐斲偐偵偮偄偰傕怰嵏晄梫偲偟偨丅偦偺寢壥丄幚晝偑巕偺恊尃幰偲側傞摴傪帠幚忋暵偞偟偨丅枹惉擭幰偺暉巸偺娤揰偐傜怰嵏偟偨尨怰偲偼懳徠揑側寛掕偲側偭偨丅
偟偐偟丄柉朄798忦扐彂偵偮偄偰偼丄乽楢傟巕偲偺墢慻偑巕偵僾儔僗偵側傞偐摍愱栧壠偑怲廳偵挷嵏偟偨忋偱壠嵸偺敾抐傪偁偍偖傋偒乿乽棫朄榑偲偟偰媈栤乿乽桳奞乿偲偺妛愢傕桳椡偱偁傞丅
俀侽侽俈丏俈丏俀侽
梴恊偺堦恖偲梴巕偑僀儔儞恖偺梴巕墢慻帠審偵偍偗傞杮崙朄傪擔杮朄偲偟偨忋丆梴巕墢慻偺壜斲偵偮偄偰僀儔儞朄傪揔梡偡傞偙偲偑岞彉偵斀偡傞偲偟偨帠椺
[嵸敾強]塅搒媨壠嵸
[擭寧擔]2007(暯惉19)擭7寧20擔怰敾
[弌揟]壠寧59姫12崋106暸
[帠幚偺奣梫]
僀儔儞恖抝惈A偲擔杮恖彈惈B偺晇晈偑丆A偺枀D偲A偺尦晇E(偲傕偵僀儔儞恖)偺枹惉擭巕C傪擔杮崙撪偱梴堢偟偰偄傞丅D(僀儔儞偱偺棧崶敾寛偱丆C偺梴堢尃傪庢摼)偼丆AB偲C偺梴巕墢慻傪嫮偔朷傫偱偄傞丅E偼強嵼晄柧偱偁傞丅AB偼嫟偵C偲偺梴巕墢慻傪媮傔偰杮怽棫偵媦傫偩丅
[怰敾偺奣梫]
僀儔儞偼廆嫵偵傛傝恎暘朄傪堎偵偡傞恖揑晄摑堦朄崙偱偁傝丆強懏偡傞廆嫵擛壗偵傛偭偰摉奩僀儔儞恖偺杮崙朄傪寛掕偟側偗傟偽側傜側偄偲夝偝傟傞偲偙傠丆C偺強懏偡傞廆嫵偼枹偩寛傑偭偰偄側偄偙偲偑擣傔傜傟傞偐傜丆C偺杮崙朄偼丆僀儔儞偺婯懃偵廬偄巜掕偝傟傞朄偑側偄偨傔丆C偵嵟傕枾愙側娭學偑偁傞擔杮朄偱偁傞偲夝偝傟傞乮捠懃朄40忦1崁慜抜丆屻抜嶲徠乯丅
僀僗儔儉朄偵偍偄偰偼丆梴巕墢慻偼擣傔傜傟偰偄側偄偺偱丆A偲C偺娭學偵偍偄偰偼丆僀僗儔儉朄偺揔梡偵傛傝丆梴巕墢慻偼擣傔傜傟側偄偙偲偵側傞偲偙傠丆偙偺傛偆側寢壥偼丆擔杮崙柉朄傪揔梡偟偨寢壥偲堎側傞(B偲C偺娭學偵偍偄偰偼丆梴巕墢慻偑擣傔傜傟傞)摍偺棟桼偐傜丆晄摉偱偁傞丅偟偨偑偭偰丆A偲C偲偺梴巕墢慻偺壜斲偵娭偟偰丆僀僗儔儉朄傪揔梡偡傞偙偲偼丆岞彉偵斀偡傞傕偺偱偁傝丆捠懃朄42忦偵傛傝丆偦偺揔梡傪斲掕偟丆擔杮崙柉朄傪揔梡偟丆梴巕墢慻傪嫋壜偟偨丅
[傂偲偙偲]
僀儔儞朄傪岞彉偵傛偭偰攔愃偟丆擔杮朄偱梴巕墢慻傪嫋壜偟偨怰敾偼丆僀儔儞偵傛偭偰彸擣偝傟側偄偙偲偵側傝丆偐偊偭偰巕偺暉巸偵斀偡傞寢壥偲側傝摼傞偲偺斸敾傕偁傞乮怉徏恀惗乽梴巕墢慻帠審偵偍偗傞僀儔儞恖偺杮崙朄偺寛掕偍傛傃僀儔儞朄揔梡偺斀岞彉惈乿亀僕儏儕僗僩亁噦1376丆333暸側偄偟335暸乯丅
俀侽侽俀丏侾俀丏侾俇
埨掕偟偨娔岇娐嫬傪梡堄偣偢丄偐偮柧妋側彨棃寁夋傪帵偣側偄偙偲偺傒傪傕偭偰偼丄柉朄817忦偺6扐彂媦傃摨忦偺7偺梫審傪枮偨偟偰偄傞偲偄偆偙偲偼偱偒側偄偲偝傟偨帠埬
[嵸敾強]搶嫗崅嵸
[擭寧擔]2002(暯惉14)擭12寧16擔寛掕
[弌揟]壠寧55姫6崋112暸
[帠幚偺奣梫]
Y偼A偲崶堶偟丄BC傪傕偆偗偨屻丄暯惉12擭侾寧侾擔偵D傪弌嶻偟偨偑丄偦偺偙傠Y偲A偲偼帠幚忋偺暿嫃忬懺偵偁偭偨偙偲偐傜丄A偼丄D偑懠偺抝惈偺巕偱偼側偄偐偲偺媈擮傪桳偟偰偍傝丄D傪摿暿梴巕偵弌偡偙偲偵愊嬌揑偱偁偭偨丅Y偼廰乆偙傟偵摨堄偟丄摨寧24擔丄D偼X晇晈偵梐偗傜傟丄娔岇梴堢偝傟偨丅X晇晈偵傛傞娔岇梴堢偵摿抜偺栤戣偼尒傜傟側偄丅偦偺屻Y偼丄摿暿梴巕墢慻偺摨堄揚夞彂傪壠掚嵸敾強偵採弌偟丄暯惉13擭12寧3擔偵庴棟偝傟偨丅X晇晈偑D傪摿暿梴巕偲偡傞巪傪怽棫偰偨偺偵懳偟丄尨怰偼丄嘆Y偑埨掕偟偨娔岇娐嫬傪梡堄偣偢丄偐偮嘇柧妋側彨棃寁夋傪帵偣側偄偺偱偼丄D偺惗妶傪晄埨掕偵偟丄寬慡側惉挿偵懡戝側埆塭嬁傪媦傏偡偺偱丄柉朄817忦偺6扐彂偺帠桼偑偁傝丄摨朄817忦偺7摍偺梫審傕枮偨偡偲偟偰丄怽棫傪擣梕丅Y偑懄帪峈崘丅
[寛掕偺奣梫]
峈崘怰偼丄師偺棟桼偱尨寛掕傪庢徚偟丄嵎栠偟偨丅
柉朄817忦偺6扐彂乽偦偺懠梴巕偲側傞幰偺棙塿傪挊偟偔奞偡傞帠桼偑偁傞応崌乿偲偼丄媠懸丄埆堄偺堚婞偵斾尐偡傞傛偆側晝曣偺懚嵼帺懱偑巕偺棙塿傪挊偟偔奞偡傞応崌傪偄偆偲偙傠丄忋婰嘆媦傃嘇傪傕偭偰捈偪偵忋婰扐彂偺帠桼偵偁偨傞偲寢榑晅偗傞偙偲偼偱偒側偄丅
柉朄817忦偺7偺乽晝曣偵傛傞梴巕偲側傞幰偺娔岇偑挊偟偔崲擄乿偱偁傞応崌偲偼丄媠懸傗挊偟偔曃偭偨梴堢傪偟偰偄傞応崌傪巜偟丄乽偦偺懠摿暿偺帠忣偑偁傞応崌乿偲偼丄偙傟傜偵弨偠傞帠忣偑偁傞応崌傪偄偆偲偙傠丄忋婰嘆媦傃嘇偺傒偱摨忦偺乽巕偺棙塿偺偨傔偵摿暿偺昁梫偑偁傞乿偲偄偆偙偲偼偱偒側偄丅
[傂偲偙偲]
嵎栠怰偼丄挷嵏姱挷嵏傗摉帠幰怰栤傪峴偄丄娭學幰偺惗妶忬嫷摍傪徻嵶偵擣掕偟偰摿暿梴巕墢慻偺怽棫傪擣梕偟丄偦偺峈崘怰傕嵎栠怰偺敾抐傪堐帩偟偨丅
|
 |
 |
|
|



