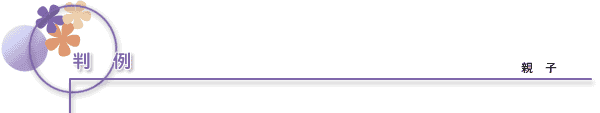 |
|
嫡出推定・認知・親子関係
父子関係(実子)は、嫡出推定(民772)と認知(779)により成立し、母子関係(実子)は、民法779条にかかわらず分娩者が母とされる(最判昭和37(1962).4.27)。
民法772条については、最高裁判例は外観説を採用し(後記各判例)、妻が夫の子を懐胎することが客観的に不可能であることが明白である場合(破綻し同居の事実がなかった、一方が海外に滞在、収監されていたなど)には民法772条の推定は及ばないとし、父子双方からのみでなく利害関係人からも親子関係存否確認の訴の提起を認める。
一方、民法772条の推定が及ぶ場合には、これを覆すには嫡出否認の訴え(775)によることになるが、原告は父のみ、提訴期間は出生を知ってから1年、と厳しい制限が付されている。嫡出推定が及ぶ場合には、親子関係不存在確認請求の訴訟要件はなく、提訴しても却下される。
一方、父母が婚姻していない場合、父子関係は父からの認知により成立するが、認知は父の死後3年までと制限がなされる反面、認知無効には期間制限がなく、子の立場は不安定である。
親子は実際の父子として長年生活を営んできたのに、子の生後何十年も経てから、時には親が死亡してから、親族から相続権にからんで親子関係不存在確認請求がなされるといった不都合を回避するため、最判(二小)2006(平18).7.7は、一定の場合に、請求が権利の濫用にあたりうることを認めた。
2021.3.12
家事事件手続法279条1項本文に基づき異議を申し立てられる「利害関係人」は、審判により直接身分関係に何らかの変動が生ずる者に限られず,当該審判によって変動する身分関係を前提として,自らの身分関係に変動を生ずる蓋然性のある者も含まれる、とした事例
[大阪高裁2021(令3)年3月12日決定 判タ1489号67頁]
[事案の概要]
父と子の間に親子関係が存在しないことを確認する旨の審判について、抗告人(母と性交渉を伴う交際関係にあった者)が、家事事件手続法279条1項本文に基づき,本件審判の利害関係人として異議を申し立てた。
原審(大阪家裁)は、抗告人は利害関係人には当たらないとして,異議の申立てを却下した。そこで,抗告人が,これを不服として即時抗告をした。
[決定の概要]
「法279条1項本文の利害関係人とは…審判により直接身分関係に何らかの変動が生ずる者に限られず,当該審判によって変動する身分関係を前提として,自らの身分関係に変動を生ずる蓋然性のある者も含まれるというべきである。」
「抗告人は,母が本件子を懐胎したと考えられる平成28年当時,母と性交渉をしたこと…少なくとも本件父と抗告人以外に,母が平成28年当時性交渉をした男性がいる事実は認められないこと…本件子と本件父との間に父子関係がある確率は0%である旨の鑑定書が存在すること,抗告人は,本件父及び母の双方から,本件子の実父であるとされ,本件父に慰謝料及び不当利得金を支払う旨の本件合意書を作成したり,母から認知及び養育費の支払に係る法的手続を申し立てる旨の予告を受けていることが認められることなどからすると,本件審判が確定することにより,抗告人は,母から認知請求を受け,本件子との親子関係が形成され,さらには,母から養育費の請求を受け,養育費の支払義務が形成される蓋然性があることが認められる。そうすると,抗告人は,本件審判に関し,法律上の利害関係を有すると認めることが相当である。」
「以上によれば,抗告人がした法279条1項本文に基づく本件審判に対する異議は適法というべきであるから,これと異なる原審判は相当ではなく,本件抗告は理由がある。よって,原審判を取り消すこととして,主文のとおり決定する。」
2018.8.30
嫡出否認の訴えを提起できるのは夫のみとする民法772条は、子の利益を保護する観点から合理性を欠くとはいえないとして違憲の主張をしりぞけ、国に対する損害賠償請求の訴えを棄却した例
[大阪高裁2018(平成30)年8月30日判決 戸籍時報773号37頁、LEX/DB25449692]
[事案の概要]
2017.11.29に同じ。
[判決の概要]
1(1)早期に父子関係を確定して身分関係の法的安定を保持することに係る利益と生物学上の父との間の父子関係と法律上の父子関係とを一致させることに係る利益(嫡出否認に係る利益)とでは、前者が優位な関係に立つとみるべきである。
(2)上記に照らせば、嫡出否認権の行使は、これを認めるにしても、限定的、謙抑的であることが望ましいことになる。
夫に嫡出否認権が付与されるのは、夫が嫡出推定により形成される父子関係の当事者であり、父子関係が形成されることにより扶養義務を負い、子が自らの相続人の地位におかれるなど直接の法的権利義務関係が生じる立場にあるからであると解される。
これに対し、妻は、父子関係の当事者ではなく、嫡出推定により直接の法的権利義務関係が生じるものではない。
そもそも、夫は、妻が他の男と性交渉を持ち、懐胎することを事実上阻止し得ないのに対し、妻は、懐胎の時期を選択することによって夫以外の生物学上の父が生じる機会を管理することができる。
そうすると、嫡出否認権を夫にのみ認めるという区別には、直接の法的権利義務関係の有無、生物学上の父を生じさせる機会の管理の可能性の有無という点で、一応の合理性があるというべきである。
(3)子は、出生直後及び主に未成熟子の期間は、専ら養育の対象であるから、子に嫡出否認によって直接の法的義務を免れる利益は通常考えられない。
子は、出生後間もない時期においては嫡出否認権を行使できる判断能力を有しない。また、成長した後に嫡出否認権を行使できるとした場合にはそれまでに築かれた法律関係が覆されることになりかねず、早期に父子関係を確定して子の身分関係の安定を図る嫡出推定の制度趣旨からは問題が生じることになる。
そうすると、父と子でみても、直接の法的権利義務関係の有無、身分関係の法的安定の利益との衝突の広狭という点で、嫡出否認を父にのみ認めるという区別に一応の合理性があるということができる。
(4)したがって、本件各規定は憲法14条1項及び24条2項に違反しない。
2(現行制度に)合理性があるからといって、妻や子に嫡出否認権を認めることが不合理となるものではない。国会の立法裁量に委ねられるべき問題と考えられる。
[ひとこと]
立法への期待をにじませる判決である。
2017.11.29
子と夫の間に父子関係がないとする嫡出否認の訴えを提起できるのは夫のみとする民法772条は、子の利益を保護する観点から合理性を欠くとはいえないとして、違憲の主張をしりぞけ、国に対する損害賠償請求の訴えを棄却した例
[神戸地裁2017年11月29日判決 法学教室450号138頁、法学セミナー760号118頁、LEX/DB25548884]
[事案の概要]
原告Dは、夫から継続的に暴力を振るわれ、離婚の手続きをとることができないまま、30年以上前に別居した。別居の翌年、Dは別の男性との間の娘である原告Aをもうけた。Dは実父を父とする出生届を出したが、「妻が婚姻中に懐胎した子は夫の子と推定する」との民法772条1項の規定により、出生届は受理されず、Aの戸籍は作成されないままとなった。
Aはその後、原告B及び原告Cを出産したが、B及びCも戸籍のないままとなった。DはAを出産した後に夫と離婚した。元夫はその後死亡したが、Dは元夫が死亡した事実を平成25年に知り、Aより実父に対する認知調停の申立てを行い、認知を認める審判がなされた。その後、A、BおよびCの無戸籍は解消された。
A、B、CおよびDの4人は、国を被告として、民法772条は憲法14条1項、24条2項に違反しているが国会は正当な理由なく長期にわたってその改正を怠ったとして訴え、合計金220万円の損害賠償請求をした。
[判決の概要]
「出産後、一定期間内に婚姻の解消(又は離婚訴訟の提起)がされること〔子の法律関係の早期安定を図る基礎が揺らいでいることをうかがわせる要件〕、生物学上の父による認知が得られること〔嫡出推定に代わる子の利益の保護を図る要件〕を要件として妻に嫡出否認の訴えを提起することを認める等、要件設定次第では、子の利益の保護に欠けることがない制度を構築することは不可能とはいえない。また、このような補完的な制度の設置により、母において子が生物学上の父とは異なる夫の戸籍に入籍することを嫌忌して出生届の提出を控え、無戸籍となる事態(いわゆる無戸籍児問題)を防止する余地があると考えられる。しかし、前記のとおり、現行民法下の嫡出推定制度を前提としても、子の利益は図りうると考えられるから、このような補完的な制度を設けるか否かは国会の立法裁量に属するといえ、設けないことが欠陥にあたるとまではいえない。・・・本件各規定は、憲法14条1項に違反しない。・・・妻や子について、その嫡出否認に係る利益を考慮しても、夫と同様に嫡出否認権を認めることには必ずしも合理性があるということはできない。そうであるとすれば、嫡出否認権を行使することができる主体を夫に限る本件各規定について、憲法24条2項の観点からも合理性を欠くということはできず、同条に違反しない。」
[ひとこと]
民法772条に問題があり、夫や元夫の暴力等を恐れて、連絡や裁判をためらい、出生届出を回避し、子が無戸籍となる例が少なからずあることは古くから指摘されてきた。判決での違憲性の有無の判断とは別に、是正すべき法律の1つである。
国は、無戸籍解消に向けて、母らが手続きをとることを支援しはじめている。
2014.12.24
子を認知した男性の父母を、認知無効を主張しうる民法786条所定の「利害関係人」に当たるとした例
[東京高等裁判所2014(平成26)年12月24日判決 判時2286号48頁、判タ1424号132頁、LEX/DB25542636]
[事案の概要]
男性aと女性eは、平成24年に婚姻し、子fをもうけた。同年、aはeの子bを、自分が血縁上の父ではないと知りつつ認知した。aの父cと母dは、a及びbを被告として、認知無効の訴えを提起した。一審は、cdは民法786条の「利害関係人」にあたらないとして訴えを却下した(東京家判平成26年7月22日)。cdが控訴した。
[判決の概要]
「本件認知により、控訴人らと被控訴人bとの間には二親等の直系血族関係が生じ、控訴人らには被控訴人bに対する扶養義務が生じている(民法877条1項)。また、控訴人らは、被控訴人aの父母であるから、被控訴人aの相続に関して、民法889条1項1号により第二順位の相続権を有するところ、本件認知により、被控訴人bは、二男fとともに第一順位の相続権を有することとなるから、これにより控訴人らの相続権が侵害される関係に立つ。したがって、控訴人らは、本件認知の無効によって自己の扶養や相続の関係において直接影響を受けるのであり、民法786条所定の「利害関係人」に当たるというべきである。・・扶養や相続への影響が生じる可能性が低いことをもって、その影響が間接的であるということはできない。・・血縁関係のない者が親子関係を形成することを望む場合,本来養子縁組によるべきであり・・・本件認知の効力を否定することが被控訴人bの福祉に反するということはできない。」として、東京家庭裁判所に差し戻した。
2014.10.10
無戸籍の女性が求めた死亡した実父への認知請求が認められた事例
[大阪家庭裁判所2014(平成26)年10月10日判決 未公表]
[事案の概要]
判決に添付された別紙(訴状請求原因)によると、女性の母は、夫から執拗な暴力を受けたため1976(昭和51)年に別居した。その後、1981(昭和56)年ころ父と知り合い、1983(昭和58)年に妊娠し、その後女性(原告)を出産した。
女性は母が母の夫との婚姻中に生まれた子であるが、母と母の夫とは1976(昭和51)年以降一切性交渉はない。
女性は、出生届出がなされず、戸籍も住民票もないまま、父母のもとで慈しまれて養育されてきた。
女性は、2008(平成20)年、父を相手方とする認知調停を申し立てたが、母の離婚が未了なら認知は認められないと告げられ、取り下げた。2009(平成21)年、母の調停離婚が成立し、同年、父母が婚姻した。2011(平成23)年、再度認知調停を申し立てようとしたが、健康状態の悪化した父が出頭できないのであれば調停できないといわれ、申立てを断念した。その後、父は死亡した。
女性が死後認知を請求。
[判決の概要]
原告は、実質的には母の前夫の嫡出子であるとの民法772条の推定を受けない子と認めることができ、また、原告と亡某との間に、原告を子、亡某を父とする生物学的父子関係の存在を推認することができる。
以上より、原告の請求は理由があるとして、認知請求を認めた。
[ひとこと]
女性の代理人長谷川京子弁護士によると、無戸籍解消のため、死誤認知を認めたのは初めて。また、同弁護士は、原告は裁判所より誤った情報(母の離婚が未了なら認知は認められない)を伝えられ、調停を取り下げているものとして、批判している(東京新聞2014年10月11日)。
2014.9.18
夫と別居中に他の男性の子を懐胎・出産し、離婚後出生届を出さないまま前夫が死亡したところ、子が母の前夫との間に親子関係が存在しないことの確認を求める訴えを提起した事例
[東京地裁2014(平成26)年9月18日判決 2014年9月19日朝日新聞デジタル]
[事案の概要]
Xの母Cは、Aと婚姻したが、Aの暴力などが原因で昭和55年に別居し、別居中に他の男性Bとの間にXを懐胎し、昭和56年に出産した。なおBの所在は不明である。Xの母CはXの出生届を出さないまま、昭和59年にAと離婚した。Aはその後死亡した。Xが検察官を被告として、Aとの間に親子関係がないことの確認を求める訴えを提起した。
[判決の概要]
「以上の認定事実に基づけば、原告(X)はCを母として昭和56年×月×日に出生したが、実父は亡Aではなく、かつ、原告の懐胎時期以前からCは戸籍上の夫であった亡Aと別居し、まったく交渉を断って夫婦の実態は失われていたものであり、事実上の離婚状態にあったものと認められる。そうすると、原告は民法772条1項による嫡出の推定を受けず、原告と亡Aとの間には父子関係はないと認めることができる。」
[ひとこと]
民法772条1項は、「妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する」と規定しているが、懐胎時に夫婦が事実上の離婚状態にあったことを認定し、嫡出推定を排除した一例である。
本件は32年間も無戸籍状態が続いていたというケースである。
2014.7.17−3
夫婦が同居中に懐胎した子について、嫡出否認期間を過ぎたあとに、元夫から、DNA鑑定を根拠に提訴した父子関係不存在確認請求を棄却した例
[最高裁第一小法廷2014(平成26)年7月17日判決 平成26年(オ)第226号 法学教室411号42頁、LEX/DB25446513]
2014.7.17−1、2
夫が単身同居中に懐胎した子について,その後,父母が別居し,母がDNA鑑定で父とされる男性と同居し共に5歳の子を養育している事案において,嫡出推定が及ぶとされた例
[最高裁第一小法廷2014(平成26)年7月17日判決 平成25年(受)第233号 判タ1406号67頁、判時2235号21頁、LEX/DB25446514]
[同日付最一小判平成24(受)第1402号 原審札幌高裁 同旨 民集68巻6号547頁、判タ1406号59頁、判時2235号14頁、LEX/DB25446515]
2014.3.28
血縁関係のないことを知りながら認知した認知者からの認知無効の請求を認容した例
[最高裁第二小法廷2014(平成26)年3月28日判決 裁判所時報1601号1頁、判例時報2226号20頁]
[事実の概要]
被上告人(認知者)は、平成14年、上告人(認知を受けた子)の母Aと婚姻するに際して、Aに請われて血縁上の父子関係がないことを知りながら上告人を認知した。被上告人、Aと子は、被上告人が購入したマンションの一室で共に暮らしたが、平成16年、被上告人はAから締め出されて別居した。平成17年、Aの求めにより被上告人とAは協議離婚し、同室をAに贈与した。子と被上告人はその後、ほとんど交流していない。Aは、平成17年、別の男性Bと再婚し、子はBと養子縁組をした。
[判決の抜粋]
「認知者は、民法786条に規定する利害関係人に当たり、自らした認知の無効を主張することができるというべきであり、この理は、認知者が血縁上の父子関係がないことを知りながら認知をした場合においても異なるところはない」「具体的な事案に応じてその必要(制限の必要)がある場合には、権利濫用の法理などによりこの主張を制限することで足りるものと解される」とし、上告を棄却した。
最三小判2014(平成26).1.14と同旨である。
2014.1.14
血縁関係のないことを知りながら認知した認知者自身も認知無効を主張できるとした例
[最高裁第三小法廷2014(平成26)年1月14日判決 民集68巻1号1頁、判時2226号18頁、判タ1403号80頁]
[事実の概要]
原審は広島高判2011年4月7日(新判例解説Watch12巻109頁)。
日本人男性Xとフィリピン人女性YIは2003(平15)年に婚姻し,YIは2003年に来日した。2004年,Xは血縁関係がないことを知りながらYIの子(1996年生,約8歳女子)Y2を認知し,日本に呼び寄せ,2005年,XとY2は同居を開始した。同年YIは日本国籍を取得した。XはY2に連日一緒に入浴するよう求めたり,抱きすくめてキスをするようなこともあった。2007年にYIは遠方で働くことになり,YIとY2は転居し,Xと別居した。2009(平21)年には同居を再開しようとしたところ,Y2はXに恐怖感を持ち,児童相談所に一時保護されるなどした。YIは仕事をやめ,Y2と生活支援施設で生活している。高裁判決時,Y2は14歳である。
Xは認知無効の訴えを提起し,広島家裁,広島高裁ともに,Xの請求を認めた。
原審は,「本件認知の無効請求が認容されたとすれば,…Y2の日本国籍の取得も無効となると解されるが,…XとY2とは一貫して不仲であり,今後ともその修復の可能性はほとんど考えられないというのであるし,Y2(現在14歳である。)は,8歳までフィリピンで実兄らと生活しており,…フィリピンには実兄も,祖母もいるほか,Y2とは母語であるタガログ語で会話する日常生活を送っていることが認められるのであるから,Y2の日本国籍の取得が無効となり,これにより,在留資格を喪失してフィリピンに退去強制されたとしても,看過し難いほどの重大な不利益を被ることになるわけではない。…本件認知の無効請求を認容することにより,既に血縁上の父と死別したY2が更に法律上の父を失うことになるとしても,それによりY2が被る精神的,経済的不利益が大きいということはできず,また,本件認知がXとY1との婚姻に伴ってされた連れ子養子の実質を有するものであり,後記のとおり,その婚姻関係が破綻した場合であっても,これを解消する制度がないことなどの本件認知やその無効請求が権利の濫用に当たるということはできない。」とした。
子側が上告した。
[判決の抜粋]
上告棄却
多数意見
「血縁上の父子関係がないにもかかわらずされた認知は無効というべきであるところ,認知者が認知をするに至る事情は様々であり,自らの意思で認知したことを重視して認知者自身による無効の主張を一切許さないと解することは相当でない。また,血縁上の父子関係がないにもかかわらずされた認知については,利害関係人による無効の主張が認められる以上(民法786条),認知を受けた子の保護の観点からみても,あえて認知者自身による無効の主張を一律に制限すべき理由に乏しく,具体的な事案に応じてその必要がある場合には,権利濫用の法理などによりこの主張を制限することも可能である。そして,認知者が,当該認知の効力について強い利害関係を有することは明らかであるし,認知者による血縁上の父子関係がないことを理由とする認知の無効の主張が民法785条によって制限されると解することもできない。
そうすると,認知者は,民法786条に規定する利害関係人に当たり,自らした認知の無効を主張することができるというべきである。この理は,認知者が血縁上の父子関係がないことを知りながら認知をした場合においても異なるところはない。」
大橋正春裁判官の反対意見
「認知した父に反対の事実の主張を認めないことにより,安易な,あるいは気まぐれによる認知を防止し,また認知者の意思によって認知された子の身分関係が不安定となることを防止するとの立法理由には十分な合理性がある。・・・本件では,上告人は被上告人の認知によって平成17年〇月▲日に日本国籍を取得して以来今日まで長年にわたり日本人としての生活を送ってきたもので,被上告人の請求が認められる場合には日本国籍を失いフィリピンに強制送還されるおそれがあり,上告人の地位が被上告人の意思によって不安定なものとなることは明らかである。民法785条及び786条はこうした事態を避けるために,認知した父に反対の事実を主張して認知の無効の主張をすることを許さない旨定めたものであると解すべきである。…法律上の父子関係は,血縁上の父子関係を基礎とするものではあるものの,民法上,血縁上の父子関係が存しなければ法律上の父子関係も存し得ないものとはされていないこと,あるいは血縁上の父子関係が存すれば必ず法律上の父子関係が存することになるものともされていないことは,嫡出否認制度や認知制度などに照らしても明らかであり,このような点からみても,上記のように解し,その結果として血縁上の父子関係の存しない法律上の父子関係の存在を容認することになったとしても直ちに不合理であるとはいえない」
[ひとこと]
民法786条は,「子その他の利害関係人は,認知に対して反対の事実を主張することができる」と規定しているが,利害関係人に認知者も含むか,特に,血縁がないと知りつつ認知した者(不実認知をした者)も含むかが争われてきた。大判大11.3.27の傍論は,不実認知者の認知も有効としていた。しかし,その後の下級審裁判例は,不実認知者の認知無効請求を認めてきた。本件では,権利濫用にもあたらないとした点に疑問が残る。
2013.12.10
特例法により性別変更した父Aと婚姻した母Bが,婚姻中に懐胎した子Cにつき,民法772条の嫡出推定が及び,Aの嫡出子であるとした例
[最高裁第三小法廷2013(平成25)年12月10日決定 民集67巻9号1847頁、判時2210号27頁]
[事実の概要]
2012.12.26事案の上告審。
[決定の抜粋]
特例法4条1項は,性別の取扱いの変更の審判を受けた者は,民法その他の法令の規定の適用については,法律に別段の定めがある場合を除き,その性別につき他の性別に変わったものとみなす旨を規定している。したがって,特例法3条1項の規定に基づき男性への性別の取扱いの変更の審判を受けた者は,以後,法令の規定の適用について男性とみなされるため,民法の規定に基づき夫として婚姻することができるのみならず,婚姻中にその妻が子を懐胎したときは,同法772条の規定により,当該子は当該夫の子と推定されるというべきである。もっとも,民法772条2項所定の期間内に妻が出産した子について,妻がその子を懐胎すべき時期に,既に夫婦が事実上の離婚をして夫婦の実態が失われ,又は遠隔地に居住して,夫婦間に性的関係を持つ機会がなかったことが明らかであるなどの事情が存在する場合には,その子は実質的には同条の推定を受けないことは,当審の判例とするところであるが(最高裁昭和43年(オ)第1184号同44年5月29日第一小法廷判決・民集23巻6号1064頁,最高裁平成8年(オ)第380号同12年3月14日第三小法廷判決・裁判集民事189号497頁参照),性別の取扱いの変更の審判を受けた者については,妻との性的関係によって子をもうけることはおよそ想定できないものの,一方でそのような者に婚姻することを認めながら,他方で,その主要な効果である同条による嫡出の推定についての規定の適用を,妻との性的関係の結果もうけた子であり得ないことを理由に認めないとすることは相当でないというべきである。
そうすると,妻が夫との婚姻中に懐胎した子につき嫡出子であるとの出生届がされた場合においては,戸籍事務管掌者が,戸籍の記載から夫が特例法3条1項の規定に基づき性別の取扱いの変更の審判を受けた者であって当該夫と当該子との間の血縁関係が存在しないことが明らかであるとして,当該子が民法772条による嫡出の推定を受けないと判断し,このことを理由に父の欄を空欄とする等の戸籍の記載をすることは法律上許されないというべきである。
[ひとこと]
賛成意見3,反対意見2であり,詳細な補足意見,反対意見が付されている。今後,民法772条や人工生殖をめぐる立法の議論が活発化することを期待したい。
2012.12.26
特例法により性別変更した父Aと婚姻した母Bが生んだ子Cにつき、民法772条の嫡出推定は及ばず、婚外子であるとした例
[東京高裁2012(平24)年12月26日決定 民集67巻9号1900頁、判タ1388号284頁]
[事実の概要]
2012.10.31に同じ。
[決定の概要]
原審判(東京家審平成24年10月31日)の示した理由を支持しつつ、「嫡出親子関係は、生理的な血縁を基礎としつつ、婚姻を基盤として判定されるものであって、父子関係の嫡出性の推定に関し、民法772条は、妻が婚姻中に懐胎した子を夫の子と推定し、婚姻中の懐胎を子の出生時期によって推定することにより、家庭の平和を維持し、夫婦関係の秘事を公にすることを防ぐとともに、父子関係の早期安定を図ったものであることからすると、戸籍の記載上、生理的な血縁が存しないことが明らかな場合においては、同条適用の前提を欠くものというべきであり、このような場合において、家庭の平和を維持し、夫婦関係の秘事を公にすることを防ぐ必要があるということはできない。また、抗告人らの主張する特例法4条の規定も、同法3条1項4号に規定する場合を前提とするものであるから、その場合の民法の規定の適用に変更を加えるものではない。そして、本件戸籍記載はCの父欄を空欄とするものであって、前記引用に係る原審判の「理由」欄の第3の4項のとおり、戸籍上の処理は、あくまでもCが客観的外観的に抗告人らの嫡出子として推定されず、嫡出でない子であるという客観的事実の認定を記載したものであるから、抗告人らの主張を考慮しても、本件戸籍記載が憲法14条又は13条に反するものということはできない。」と述べ、抗告を棄却した。特別抗告がなされた。
2012.11.2
[大阪高裁2012(平成24)年11月2日判決 戸籍時報692号4頁]
[事実の概要]
A女とY男は婚姻したが、勤務の事情から、Yが単身赴任する形で婚姻共同生活を開始し、月に何度か自宅に戻っていた。1年数か月、同居できた時期もあった。婚姻から約5年後、AはXを出産した。AとYは、お宮参りや保育園の行事等に夫婦として参加したりしていた。しかし、Xの誕生から約2年後、YはAとZ男の交際を知り、AはYに離婚を求めたがYは応じなかった。数か月後、AはXを連れて別居し、現在、AXZの3人は同居生活を送っている。XはYに対して親子関係不存在確認の調停を申し立てたが不成立となり、提訴した(MがAの特別代理人に選任されている)。
[判決の概要]
DNA鑑定の結果からXがYの生物学上の子でないことは明白であること、YもXの生物学上の父親がZであること自体を積極的に争っていないこと、現在、XはZの自宅でAやZに育てられ、Zを「お父さん」と呼んで順調に成長していること、面談した特別代理人Mも、このような状況を確認していることにも照らし、「Xには民法772条の嫡出推定が及ばない特段の事情があるものと認められる」とした。また、嫡出否認制度が法律上の親子関係とその早期安定を一定限度保護しているとしても、そのことから直ちに上記保護の要請が血縁上の親子関係を確認する利益よりも常に優先するとは考えがたいし、本件の場合は、上記の事情から、「Xの福祉の観点からも、民法772条の推定を受けないものと解すべきである」から、親子関係不存在確認の訴えを提起することができ、またその確認の利益もあると認め、Xの請求を認容した原判決(大阪家審2012年4月)は相当とし、Yの控訴を棄却した。
[ひとこと]
現在、最高裁判所に係属している。民法772条につき最高裁判所判例が従来採用してきた外観説との関係の行方が注目されている(朝日新聞2014.1.19)。
2012.10.31
特例法により性別変更した父Aと婚姻した母Bが生んだ子Cにつき、民法772条の嫡出推定は及ばず、婚外子であるとした例
[東京家裁2012(平24)年10月31日審判 民集67巻9号1897頁、新・判例解説Watch(2013年4月号)]
[事実の概要]
父Aは、性同一性障害者の性別の取扱いに関する特例法3条に基づき、男性へ変更する審判を受け、その後、母Bと婚姻し、母は、人工授精により婚姻後200日以降に子Cを出産した。2012(平12)年父は、子を父母の嫡出子として出生届出をしたが、同年、新宿区長は、子の父欄を空欄とし、母の非嫡出子とする戸籍記載を行った。申立人(AとB)は、Aを父としCをABの嫡出子とする戸籍訂正許可(戸籍法13条に基づく)を家庭裁判所に申立てた。
[審判の概要]
「男性としての生殖能力がないことが戸籍記載上から客観的に明らかであって、Cは申立人ら夫婦の嫡出子とは推定できない」「以上の戸籍上の処理は、あくまでもCが客観的外観的に申立人らの嫡出子として推定されるかどうかという客観的事実認定の問題であって、申立人Aを性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律に基づき男性として取り扱うべきであるとの法律上の要請に反するものではなく、かかる取扱いは憲法14条で禁止された差別には該当しない。なお、本件のように非配偶者間人工授精によって妻が懐胎した子について、夫の同意があることを要件に、夫の子とする立法論はあり得るところであるが、そのような法律が成立すれば格別、我が国においては未だそのような立法がされていないのであるから、申立人Aが人工授精に同意していることをもって、Cとの父子関係を認めることもできない。現状では、本件のような場合には、特別養子縁組をすることで対応することになるが、手続の煩わしさはあるとしても、それによって特別養親関係が成立すれば、子の法的保護には欠けるところはない。」とした。
2011.11.4
日本人夫からフィリピン人妻に対する離婚請求及び夫が認知した妻の子に対する認知無効確認請求について、日本に国際裁判管轄を認めたうえ、いずれの請求も認容した事例
[広島高裁2011(平成23)年4月7日判決 戸籍時報692巻39頁]
[事実の概要]
日本人Xは、3人の子がいるフィリピン国籍のY1と婚姻し、Y1の子のうちY2について、実子ではないと知りながら、Xが父となっている虚偽の出生証明書を入手して、認知の届出をした。Y2は来日し、XY1と同居を始め、日本国籍を取得した。同居中、Y2は、Xに髪を引っ張られたり、胸など触られたりしたため、児童相談所の一時保護施設に入所し、Y1もXと別居し、福祉施設内で生活をしている。
XはY2が自分の実子ではないことを理由に、Y2に対して認知無効確認請求をするとともに、Y1に対して離婚請求をした。原審は、Xのいずれの請求も認めた。
[判決の概要]
1国際裁判管轄について
X及びYらはいずれも日本国内に生活しており、認知無効事件及び離婚事件のいずれについても、我が国に国際裁判管轄が認められることは明らかである。
2準拠法について
(1)認知無効事件
①認知の当時、Y2はフィリピン国籍を有していたと認められる。法の適用に関する通則法(以下「通則法」という。)29条1項及び2項によれば、認知に関しては、子の出生時における父の本国法によるほか、認知の当時における認知者又は子の本国法によるとされていて、渉外認知の成立をなるべく容易にするという認知保護の政策に基づいて選択的連結が導入されている。そうすると、認知の無効については、上記の選択的連結を導入した趣旨を考慮して、上記すべての法律によっても認知が無効である場合のみ、これを無効とすることができると解される。
②本件では、X及びY2の本国法は日本法であるが、認知当時のY2の本国法はフィリピン法である。しかし、フィリピン法においては(フィリピン家族法175条、172条。なお、同法には認知の制度は存在しない。)、事実主義を採用していると解されていることから、フィリピン法は認知に関する準拠法とはいえず、認知無効に関する準拠法ともならない。実際、本件においては、申立人と相手方の血縁上の親子関係がないから、同法による父子関係が認められないことは明らかである。
③よって、日本法によって、認知無効が認められるのであれば、XはY2に対し認知無効を求めることができる。
(2)離婚事件
通則法25条により、夫婦の常居所地法は同じ日本法であると認められるから、離婚事件についても日本法が適用される。
3認知の撤回及び慰謝料請求について
(1)「・・・民法785条については第一義的には認知の撤回を認めないという趣旨にとどまり、血縁上の親子関係が存在しない場合であっても、認知者の認知の取消しや無効の主張を認めないという趣旨までも含むことは困難であると思われる。・・・よって、XのY2に対する認知無効請求には理由がある。」
[ひとこと]
認知無効確認訴訟の国際裁判管轄については、裁判例が確立していないが、本判決は関係者がすべて日本国内で生活していることを認定して、日本に国際裁判管轄を認めている。理由を明記していないが、条理を基準とする判例に照らし結論は妥当である。現在、家事・人訴事件についての国際裁判管轄の法制化の作業中であるが、現在の国際裁判管轄の判例基準を追認する形で法文化しようとしているので、成立後も、本件の結論が妥当すると思われる。本件では、認知者自身が無効を主張しうるか否かについても問題となっている。本判決は、通説判例に従って肯定し、Xの請求を認めたが、Xは血縁関係がないことを知りながら違法な手段で認知の手続をしていること、Y2に対する性的虐待、認知無効が認められるとY2の日本国籍がはく奪されることなどから、Xの主張は権利濫用とすべき、という批判もある。
2010.9.6
産院で取り違えられたため、生物学的な親子関係がない夫婦の実子として戸籍に記載され、長期間にわたり実の親子と同様の生活実態を形成してきたが、両親の死後、遺産争いを直接の契機として、戸籍上の弟らが提起した親子関係不存在確認請求は、権利の濫用に当たるとされた事例
[裁判所]東京高裁
[年月日]2010(平成22)年9月6日判決
[出典]判タ1340号227頁
[事実の概要]
被控訴人Yは、A(夫)B(妻)間の長男として戸籍に記載され、ABに養育され、大学卒業後は会社勤めをし、結婚して、妻との間に二人の子が生まれた。Yは会社勤めの後、退職し、Aの不動産業を手伝い、その後、独立した。控訴人Xらは、ABの子であり、Yの戸籍上の弟である。YはABの死後、Xらと相続をめぐって対立し、XらはYに対し、ABとYとの間に親子関係が存在しないことの確認を求める訴訟を提起した。
原審において、Xら申請のDNA鑑定が採用され、YとABとの間には生物学的な親子関係が存在しない旨の鑑定結果が得られた。原審は、鑑定結果に基づいて、ABとYとの間には親子関係が存在しないことを確認する判決を言い渡した。Yが、本件請求は権利の濫用に当たるとして控訴した。
[判決の概要]
①YとAB夫婦との間で長期間にわたり(Aについて約54年半、Bについて約46年)実の親子と同様の生活の実体があったこと、②ABはいずれも既に死亡しており、YがAB夫婦との間で養子縁組をすることがもはや不可能であること、③親子関係不存在が確認された場合、Yが重大な精神的苦痛及び少なからぬ経済的不利益を受けること、④XらとYの関係、XらがYとAB夫婦との親子関係の不存在確認請求をするに至った経緯及び請求をする動機、目的、⑤親子関係が存在しないことが確認されない場合、Xら以外に不利益を受ける者はいないことなどを考慮すると、Xらの親子関係不存在確認請求は、権利の濫用に当たり、許されないというべきである。
[ひとこと]
最判2006(平成18)年7月7日は、実子でない子を実子として届け出るいわゆる藁の上からの養子のケースについて、当該親子関係不存在確認請求が権利の濫用に当たると判断したが、本件は、産院で取り違えられた子のケースについて、同判決の示した具体的判断基準をあてはめ、権利濫用を認めた1例である。
2010.1.20
戸籍上嫡出子と記載されている子について、亡父の弟から父子関係不存在の確認を求めたのに対し、在留資格取得目的での婚姻であったことを認定し、嫡出の推定が排除されるとした上、請求を認めた事例
[裁判所]東京高裁
[年月日]2010(平成22)年1月20日判決
[出典]判時2076号48頁、判タ1325号222頁
[事実の概要]
Yは、父A(日本人)と母B(ルーマニア人)の嫡出子として戸籍上記載されている。
AはBと離婚後死亡した。
Aの弟Xは、YはAの子ではないとして、親子関係不存在確認訴訟を提起した。
原審はXの請求を認め、Yはその取消しを求めて控訴した。
[判決の概要]
1 嫡出推定について
本件親子関係不存在確認訴訟が適法とされるためには、本件において、妻が夫の子を懐胎する可能性がないことが外観上明白な事情があることから、嫡出の推定が排除される場合に当たることが必要となる。
①Bは、本邦に最初に入国した後の、日本語による日常会話にも不自由していたと見られる時期に、結婚を前提とする交際期間もないままに、従前、何らの接点もない生活保護受給者で重い腎臓病の持病のある16歳も年上のAと突然婚姻した。
②AとBは、Yの出生直前(9日前)に協議離婚をした。
③夫婦の転居の時期が異なる。
④婚姻後間もなく、Bの在留資格期間が日本人配偶者(1年)と変更されている。
⑤Yの出生直前の協議離婚は、Yが誕生すれば、その母親にあたるBは婚姻を続けなくても在留資格を得られることによるものと推認され、実際にもYの出生後Bの在留資格期間は定住者(1年)と変更されている。
⑥BがYを懐胎したと見られる時期にはAと同居していた事実がない。
したがって、BとAの婚姻は、Bの在留資格の取得又は維持の目的で法律上の婚姻関係が形成されたものであると推認することができ、夫婦の生活実態も存在しないものであったと評価するのが相当である。本件においては、妻が夫の子を懐胎する可能性がないことが外観上明白な事情があるといえ、嫡出の推定が排除される。
2 親子関係について
①保険会社の担当者の訪問を受けた際に、担当者の「(Yは)あなたの子供ですか」という質問に対し、Bは、「違います」と答えたこと、
②BはYとAとの間の父子関係の有無についてのDNA鑑定につき、協力しない姿勢に終始したこと(裁判所に顕著な事実) は、YとAとの間の親子関係の不存在を推認しうる重要な間接事実である。
YとAとの間に父子関係は存在しないと認めるのが相当である。
[ひとこと]
最判H12.3.14の採用した外観説に依拠しつつ、間接事実を詳細に検討・評価したうえで、嫡出推定(民772)が排除されるとした判例であり、その判断手法は参考になる。
また、DNA鑑定に協力しなかったことを、「親子関係の不存在を推認しうる重要な間接事実」であると判断した点も参考になる。従来、認知訴訟等においても、科学鑑定への非協力は同様に扱われてきた。人事訴訟法においては真実の発見が重要であるので、一般の民事訴訟における弁論主義は制限され、職権証拠調べ(人訴19、20)が行われるが、「証明妨害と立証責任の転換」や「事実及び証拠に近い者の事案解明義務及びそれに基づく主張・証明責任の転換」は、実際には人事訴訟でも行われている典型例である。
2010.1.14
離婚後300日以内に生まれた子は前夫の子とする民法772条の規定には合理性があるなどとして違憲ではないと判断した事例
[裁判所]岡山地裁
[年月日]2010(平成22)年1月14日判決
[出典]法学教室159頁、家月64巻5号78頁
[事実の概要]
原告Dの母親Aは,平成18年2月にBと婚姻するも,Bの暴力が原因で実家に帰り,同年10月及び平成19年4月に,Bに対し,それぞれDV法に基づく保護命令決定を得た後,平成20年3月,Bと和解離婚した。他方,Aは,平成20年1月ないし同年2月ころ,Cの子であるD(原告)を懐胎し,同年10月、再婚禁止期間6ヶ月を経過して10日ほど後に、Cと婚姻,同年11月にDを分娩した(AとBの離婚日から300日以内の出生。)。Cを父とするDの出生届が不受理とされたことにつき,Dが,憲法14条違反や民法772条1項違反などを理由として損害賠償等を求めた。
[判決の概要]
民法772条1項の規定について,「一般に婚姻中に妻が懐胎した子の父は夫である可能性が高い」ことから憲法14条に違反するものではないとした。また,本件不受理処分等についても,戸籍や出生届の添付資料などからは,Dの懐胎時期におけるAとBの関係が明らかではなく,保護命令の効力も懐胎時期には既に失われていたのであるから,Aの懐胎がBによるものではないことが明白であったとはいえず,憲法14条に違反するとは言えないとした。さらに,本件不受理処分等は,民法772条1項や児童の権利に関する条約7条に違反するものでもないとした。
[ひとこと]
原告より控訴がなされた。
2009.11.10
真実に反することを認識しながら認知をした父が、認知の無効確認の訴えを提起することができるとした事例
[裁判所]大阪高裁
[年月日]2009(平成21)年11月10日判決
[出典]家月62巻10号67頁
[事実の概要]

控訴人A(夫)はC(妻)と出会い交際を開始した。CにはAと知り合う以前に出産した子である被控訴人Bがいた。CはAの子を懐妊し、AはCとの婚姻届及びBを認知する旨の届出をした(戸籍上BはACの長男)。Aは婚姻後も一人暮らしを続け、CはBと暮らしながらA宅に通い、AはCに婚姻費用を支払っていた。CはE(戸籍上は二男)を出産した。その後、AはDと交際を開始した。Aは夫婦関係調整調停事件を申し立てたが同調停は不成立となった。Aは真実に反する認知をしたことを理由にBに対する認知の無効確認を求めた(①)。原審は、Aは自らがBの実父でないことを認識しながら任意に認知をしたのであるから、Cとの婚姻が継続する以上、認知の無効確認を求めることができないとして、Aの請求を棄却した。そこで、Aが控訴をした。
なお、本件では、①のほかに、②AからCに対する離婚及び慰謝料請求、③CからA及びDに対する慰謝料請求(②への反訴)、④AがBに対して認知の無効確認を求めたことによって、Bを事実上の養子として成人に達するまで養育していく旨の約束に違反したとして、BからAに対する養育費相当額の損害賠償請求(①への反訴)が併合されている。
[判決の概要]
控訴人Aと被控訴人Bとの間には、血縁上の父子関係がないにもかかわらず、Aは、Cとの婚姻に伴い、同人の子であったBの父として養育する意思で認知をしたということができる。このような認知(不実認知)の無効を認知者自身が主張することができるかについては、民法785条(認知者自身による認知の取消しを否定)との関係で、これを消極に解する見解もあり得る。しかしながら、認知が、血縁上の父子関係の存在を確認し、その父子関係を法律上の実親子関係にするための制度であり、同法786条が、子その他の利害関係人が、認知に対して反対の事実を主張すること(不実認知の無効確認を求めること)ができる旨規定することからすれば、認知者自身も不実認知の無効を主張することができると解するのが相当である。そして、このことは、上記認知が母との婚姻に伴って子を養育する意思でなされたものであり、認知者と母との法律上の婚姻関係が継続しているといった事情があっても同様である(ただし、このような事情が、認知者が被認知者の母である妻に対して負担するべき婚姻費用の金額の算定において、民法760条の「その他一切の事情」として考慮されるかどうかは別の問題であり、認知者が認知の際に自分の子として養育する意思を有していた以上、婚姻費用の増額事由として考慮されるべきであると解される。)。従って、Aは、Bに対し、認知の無効確認請求をすることができる。
なお、子から認知者に対する養育費相当額の損害賠償請求(④)については、不実認知の無効確認が違法な行為でないこと、仮に認知が無効と確認されても、上述したように婚姻費用を算定する際に増額事由として考慮されるべき場合があることから、理由がないとされた。
[ひとこと]
認知者自身による認知の無効主張について、原審は親子関係の成立に意思的要素を重視しこれを否定したが、控訴審では親子関係成立の事実的要素を重視し、これを肯定した。
古い判例は、認知者は反対事実を主張できないとしたが(大判大11.3.27民集1-137)、現在、真実に反する認知は、それが誤認によって行われたか、故意に行われたかを問わず、無効と解することでほぼ異論がなく、本件高裁判決は通説に沿ったものである。
2008.12.25
親子関係不存在確認請求が著しく不当な結果をもたらすとまではいえず、権利の濫用にあたらないとして、請求が認容された事例
[裁判所]名古屋高裁
[年月日]2008(平成20)年12月25日決定
[出典]判時2042号16頁
[事実の概要]
控訴人(昭16生、72歳)はAB夫婦の実子、被控訴人(昭11年生)はAの兄の子であり実子ではないが実子として出生届出がなされ、実際にも実子として育てられた。ABはいずれも既に死亡したが遺産分割はなされていなかった。控訴人はAの事業を承継したが、平成19年に家業を廃業し、A名義の土地を売却して借金を返済しようしたが、Bはその協力を断った。控訴人から被控訴人に対して親子関係不存在確認請求がなされ、原判決(名古屋地判2008.3.27)は権利濫用にあたるとして棄却した。
[決定の概要]
「身分関係の存否確認請求が権利の濫用に当たるか否かは、①実の親子と同様の生活の実態のあった期間の長さ、②判決をもって実親子関係不存在を確定することにより、子及びその関係者の受ける精神的苦痛、経済的不利益、③改めて養子縁組をすることにより、子の身分を取得する可能性、④親子関係不存在確認請求訴訟をするに至った経緯、動機、目的、⑤控訴人以外に著しく不利益を受ける者の有無を総合して、実親子関係の不存在を確定することが著しく不当な結果をもたらすものといえるときには、当該請求は権利の濫用に当たり許されないというべきである。」とし、本件では、被控訴人は中学生の頃から実子でないことを知っていたので精神的打撃が甚大であるとまではいえないこと、親子関係を否定するとABは死亡しているのでこれから養子縁組はできず相続権を失うこと、しかし、事実上の財産分けを受けていること、他方、控訴人は高卒後進学を断念して家業をつぎ、病弱のAに代わり家業を盛り立て財産を形成し維持してきたことから、被控訴人が生活保護を受けていることを考慮しても、「実親子関係の不存在を確定することが著しく不当な結果をもたらすものとまでは認めることはできない。」として、親子関係不存在確認請求は権利の濫用にあたらないとした。
[ひとこと]
親子関係不存在確認請求が権利の濫用にあたるとした最判2007(平成18)年7月7日の示した具体的判断基準を踏襲しつつ、結論は、逆に権利濫用にあたらないとした事案である。現在の出生届出の様式では右に医師の出生証明欄があり、実子でない子を実子として届け出ること(藁の中の養子)は不可能であるので、今後は次第に少なくなっていく訴訟類型だが、珍しいので掲載した。
2006.10.13
父子関係不存在の23条審判に対し、血縁上の父は利害関係人として異議申立てできるとした例
[裁判所]東京高裁
[年月日]2006(平成18)年10月13日決定
[出典]家月59巻3号69頁
[事実の概要]
当事者関係は、母D、子B、Bの戸籍上の父C、鑑定でBの実父とされた抗告人A。Bと母Dが、嫡出否認の訴え提起期間を徒過しているのに、Cに対して親子関係不存在確認を求めその23条審判がなされた。これに対し、実父のBから異議申立がなされ、原審判は「法律上の利害関係がない」として異議を却下した。これに対し、Aが抗告した。
BとDはAに対し、認知、月5万の養育費、未払い養育費85万円、出産費用25万円の請求をしていた。
[決定の概要]
「家事審判法23条の審判に対して異議の申立てをすることができる「利害関係人」は、当該審判により直接身分関係に何らかの変化が生じる蓋然性が現実化している者もこれに含まれる。・・抗告人は、本件審判が確定することにより、Bとの親子関係が形成される可能性があり・・・Bとの親子関係を前提に親としての義務を請求されているという関係にあるから、本件審判につき法律上の利害関係があるというべきである。」として、原審判を取り消した。
[ひとこと]
離婚後300日問題では、血縁上の父が法律上の父親になりたくても簡単になれないが、本件は逆である。家裁月報に搭載された情報からは十分な事情はわからないが、妥当な結論である。血縁で親子関係がすべてが決まるわけではない。
2006.7.7
戸籍上の父母とその嫡出子として記載されている者との間の実親子関係について父母の子が不存在確認請求をすることが権利の濫用に当たらないとした原審の判断に違法があるとされた例
[裁判所]最高裁二小
[年月日]2006(平成18)年7月7日判決
[出典]家月59巻1号92頁 判時1966号58頁
[事実の概要]
YはAB夫婦の実子として養育された。相続の問題を契機に同夫婦の長女XがYとABとの親子関係不存在確認請求訴訟を提起した。原審は、XによるYとABの実親子関係不存在確認請求は権利の濫用に当たらないと判断した。
[判決の概要]
戸籍上AB夫婦の嫡出子として記載されているYが同夫婦の実子ではない場合において、Yと同夫婦との間に約55年間にわたり実親子と同様の生活の実体があったこと、同夫婦の長女Xにおいて、Yが同夫婦の実子であることを否定し、実親子関係不存在確認を求める本件訴訟を提起したのは、同夫婦の遺産を承継した次女Cが死亡し、その相続が問題となってからであること、判決をもって実親子関係の不存在が確定されるとYが軽視しえない精神的苦痛及び経済的不利益を受ける可能性が高いこと、同夫婦はYとの間で嫡出子としての関係を維持したいと望んでいたことが推認されるのに、同夫婦は死亡しており、Yが養子縁組をして嫡出子としての身分を取得することは不可能であること、Xが実親子関係を否定するに至った動機が合理的なものとはいえないことなど判示の事情の下では、上記の事情を十分検討することなく、Xが同夫婦とYとの間の実親子関係不存在確認請求をすることが権利の濫用に当たらないとした原審の判断には、違法がある。
〔ひとこと〕
真実の実親子関係と戸籍の記載が異なる場合、実親子関係不存在確認請求をすることができるのが原則だが、最高裁は一定の場合に例外を認めた。2006.7.7も同様のケースである。
2006.7.7
戸籍上自己の嫡出子として記載されている者との間の実親子関係について不存在確認請求をすることが権利の濫用に当たらないとした原審の判断に違法があるとされた例
[裁判所]最高裁二小
[年月日]2006(平成18)年7月7日判決
[出典]家月59巻1号98頁
[事案の概要]
YはXの実子ではないが、戸籍上はXの嫡出子を記載されていた。Xは長期間Yと実の親子と同様に生活してきたものの、Yに対し、実親子関係不存在確認請求訴訟を提起。原審は、Xの請求は権利の濫用に当たらないと判断した。
[判決の概要]
戸籍上Xと亡夫との間の嫡出子として記載されているYがXの実子ではない場合において、YとXとの間には、XがYに対して実親子関係不存在確認調停を申し立てるまでの約51年間にわたり実親子と同様の生活の実体があり、その間、XはYがXの実子であることを否定したことがないこと、判決をもって実親子関係の不存在が確定されるとYが軽視し得ない精神的苦痛及び経済的負担を受ける可能性が高いこと、XがYに対して実親子関係不存在確認を求める本件訴訟を提起したのは、上記調停の申し立てを取り下げて10年が経過した後であり、Xが本件訴訟を提起するに至ったことについて実親子関係を否定しなければならないような合理的な事情があるとは伺われないことなど判示の事情の下では、上記の事情を十分検討することなく、XがYとの間の上記実親子関係不存在確認請求をすることが権利の濫用に当たらないとした原審の判断には、違法がある。
2000.3.14
同居中の懐胎であるため嫡出の推定を受ける子に対する親子関係不存在確認の訴えは認められないとされた事例
[裁判所]最高裁三小
[年月日]2000(平12)年3月14日判決
[出典]民集197号375頁、判時1708号106頁
[事案の概要]
X(夫)とA(妻)は平成3年2月に婚姻し、同年9月2日に子Yを出産したが、約3年後の平成6年6月に協議離婚した。離婚後の平成7年に、XはYに対し、親子関係不存在確認の訴えを提起した。Xは、離婚後にYはXの子ではなくBの子であることを知り、それから速やかに本件訴えを提起したのであるから、嫡出否認の訴えの出訴期間経過後であっても例外的に親子関係不存在確認の訴えによって身分関係の確定を図ることができると主張した。
一審は、民法772条の規定によりYがXの子であることが推定されるのであるから、AがXによって懐胎することが客観的に不可能な事実がある場合を除いては、XがYに対して親子関係不存在確認の訴えを提起することはできないものとして、訴えを却下した。
これに対し、原審は、嫡出推定及び嫡出否認の制度の基礎である家族共同体の実体がすでに失われている場合に、父子間の自然的血縁関係の存在に疑問を抱かせるべき事実が知られた後相当の期間内に提起されたのであれば、いわゆる血縁主義、真実主義を優先させ、例外的に親子関係不存在確認の訴えを許すのが相当であるとして、一審判決を取り消して、事件を一審に差し戻した。
[判決の概要]
原判決を破棄し、下記の通り述べて、Xの控訴を棄却した。
「民法772条により嫡出の推定を受ける子につき夫がその嫡出であることを否認するためには、専ら嫡出否認の訴えによるべきものとし、かつ、嫡出否認の訴えにつき1年の出訴期間を定めたことは、身分関係の法的安定を保持する上から十分な合理性を有するものということができる。そして、夫と妻との婚姻関係が終了してその家庭が崩壊しているとの事情があっても、子の身分関係の法的安定を保持する必要が当然になくなるものではないから、右の事情が存在することの一事をもって、嫡出否認の訴えを提起し得る期間の経過後に、親子関係不存在確認の訴えをもって夫と子との間の父子関係の存否を争うことはできない。・・・もっとも、民法772条2項所定の期間内に・・・夫婦間に性的関係を持つ機会がなかったことが明らかであるなどの事情が存在する場合には、・・実質的には民法772条の推定を受けない嫡出子に当たるということができるから、・・夫は・・父子関係の存否を争うことができると解」されるが、「本件においては、右のような事情は認められず、他に本件訴えの適法性を肯定すべき事情も認められない。」とした。
[ひとこと]
最判1998.8.31に続いて、最高裁は民法772条の解釈に関し、「推定の及ばない子」の範囲について外観説を採用した。これによって、下級審判例では一般的になりつつあった家庭破綻説(上記の原審判決はこの立場である)を採用しないことを明言し、血縁上の親子関係と異なる法律上の親子関係の存在を堅持することを改めて示したものとして重要である。
1998.8.31
夫婦が別居を開始してから9カ月余り後に出生した子を被告として夫が提起した親子関係不存在確認の訴えが不適法とされた事例
[裁判所]最高裁二小
[年月日]1998(平成10)年8月31日判決
[出典]家月51巻4号33頁、判時1655号112頁、判タ986号160頁
[事案の概要]
X(男性)は、昭和62年11月、Aと婚姻し同居を開始したが、昭和63年10月、別居するに至った。同年11月、XとAとの間に性交渉があり、同年12月、Xは、Aから妊娠したことを知らされた。平成元年6月、XとAの間に、Xが婚姻費用を分担し、出産費用を支払う旨の調停が成立した。同年7月、AはYを出産した。Xは、その直後にY出産の事実を知った。
Xは、平成元年11月にYを相手方として嫡出否認調停を申し立てるも、平成2年10月15日、調停不成立となった。Xは、同年11月15日にYを被告として嫡出否認の訴えを提起したが、平成3年1月、同訴えを取り下げた。家事審判法26条2項は調停不成立後2週間以内に提訴すれば調停申立時に訴えの提起があったとみなすとしているが、2週間を徒過していた。また、民法777条は嫡出否認の出訴期間を「子の出生を知ったときから1年」と定めるが、本件提訴はこの期間も徒過していた。
Xは、平成3年11月、Yを相手方として親子関係不存在確認調停を申し立てるも、平成4年2月に調停不成立となった。そこで、Xが、平成4年2月にYを被告として、親子関係不存在確認訴訟を提起したのが本件である。
1審は、父子関係を客観的かつ明白に否定する証拠はないから嫡出推定は排除されず、嫡出否認の訴えによるべき場合であるとして訴えを却下し、2審も1審の判断を相当としてXの控訴を棄却した。そこで、Xが上告した。
なお、XとAとの間には、平成9年8月、Yの親権者をAとして、協議離婚が成立した。
[判決の概要]
上告棄却。
Xは、YとAとの婚姻が成立した日から200日を経過した後にAが出産した子であるところ、Xは、Yの出生する9箇月余り前にAと別居し、その以前からAとの間には性交渉がなかったものの、別居後Yの出生までの間に、Aと性交渉の機会を有したほか、Aとなお婚姻関係にあることに基づいて婚姻費用の分担金や出産費用の支払に応ずる調停を成立させたというのであって、XとAとの間に婚姻の実態が存しないことが明らかであったとまではいい難いから、Yは実質的に民法772条の推定を受けない嫡出子に当たるとはいえないし、他に本件訴えの適法性を肯定すべき事情も認められない。
[ひとこと]
昭和44.5.29最判以来の民法772条についての外観理論を維持する判例。親子鑑定などの科学の進展、子の出自を知る権利など、種々の点から疑問は呈されており、立法論も活発である。
1998.8.31
婚姻成立の日から200日以後に出生した子に対して父親の死亡後にその養子が提起した親子関係不存在確認の訴えが適法とされた事例
[裁判所]最高裁二小
[年月日]1998(平成10)年8月31日判決
[出典]家月51巻4号75頁、判時1655号128頁
[事案の概要]
A男とB女は、昭和18年10月に婚姻した。A男は、同年10月に応召・出征し、昭和21年5月28に帰還した。A男の出征中、B女は、C男と性的関係を持った。昭和21年11月、B女はXを出産した。Xは、A男・B女夫婦の嫡出子として届け出られたが、昭和22年8月、C男の養子とされ、以来、C男のもとで暮らし、C男・D女夫婦(昭和27年に婚姻)の子として育てられた。Xは、A男・B女夫婦とは没交渉の状態にあった。他方、A男・B女夫婦は、昭和26年3月にYを養子として、同居生活を送ってきた。平成4年4月、A男が死亡した。そこで、Yが、Xに対して、XとA男との間の親子関係不存在確認を求める訴えを提起したのが本件である。1審、2審とも、B女が、XをA男の子として懐胎することは客観的に見て不可能であったとして、Yの親子関係不存在確認の訴えを適法と判断し、Yの請求を認容した。Xが上告。
[判決の概要]
上告棄却。
A男は、応召した昭和18年10月から帰還した昭和21年5月28日の前日まで、B女と性的関係を持つ機会がなかった。仮に、B女がA男の帰還後にXを懐胎したものとすると、B女は最長でも26週目にXを分娩したことになるが、昭和21年当時の医療水準を考慮すると、そのような子が生存する可能性は極めて低い。したがって、B女がXを懐胎したのは昭和21年5月28日より前であると推認すべきであるから、B女がA男の子を懐胎することが不可能であったことは明らかである。よって、Xは、実質的には、民法772条の推定を受けない嫡出子であり、A男の養子であるYがA男とXとの間の父子関係の存否を争うことが権利濫用に当たると認められるような特段の事情の存しない本件においては、Yの親子関係不存在確認の訴えは適法である。
[ひとこと]
同日付最判と同じく、外観説にたつ最判の1つ。子出生から40年以上経過した後に、父親の養子から提起された親子関係不存在確認の訴えであるという点も特徴的であるが、本件ではXはAB夫婦と長年没交渉であり、実質的な親子関係もなかったというのであるから、権利濫用法理による訴えの棄却(最判平成18.7.7が示唆)もありえなかった事案である。
1969.5.29
婚姻解消後300日以内に出生した子が、嫡出の推定は受けず、嫡出否認の訴えを提起しなくとも実父への認知請求が認められるとされた事例
[裁判所]最高裁一小
[年月日]1969(昭44)年5月29日判決
[出典]民集23巻6号1064頁
[事案の概要]
昭和21年にA(妻)とB(夫)が婚姻したが、昭和24年には事実上の離婚状態となり、昭和26年10月2日に離婚の届出がなされた。その後、離婚から300日を経過しない昭和27年3月28日に子Xが生まれた。原告(被控訴人・被上告人)Xは、事実上の父と思われるYを相手として、認知を求める訴訟を提起した。
原審・控訴審ともに、Xの認知請求を認めた。これに対して、父と思われるYが上告。Yの上告理由は、子XはAB間の婚姻の解消から300日以内に出生しており、そのような場合に戸籍上の父との父子関係を切断するには、戸籍上の父であるBが嫡出否認の訴えを提起する方法しかなく、そのような方法に従っていない本件訴訟は不適法であり却下すべきである、というものであった。
[判決の概要]
上告棄却。
被上告人XはAB間の婚姻解消の日から300日以内に出生した子であるけれども、AB間の夫婦関係は、離婚の届出の約2年半前にあたる昭和24年に事実上の離婚をして以来「夫婦の実態は失われ、たんに離婚の届出が遅れていたにとどまるというのであるから、被上告人Xは実質的には民法772条の推定を受けない嫡出子というべく、同被上告人はBからの嫡出否認を待つまでもなく、Yに対して認知の請求ができる」。
[ひとこと]
最高裁が外観説を採用したリーディング判例である。民法772条に関し、当時としては、解釈により柔軟な対応をできるよう修正したものといえる。外観説とは、懐胎期間中の夫の失踪、事実上の離婚など、懐胎期間中に夫との性行為がなかったことが、同棲の欠如によって外観上明白な場合に限り、嫡出推定が及ばないとし、親子関係不存在確認請求により父子関係を否定することを認める立場である。この判例は長年余り注目されていなかったが、2008年頃にマスコミが300日問題として取り上げるようになった以来、よく知られるようになり、家庭裁判所でも、嫡出否認を経ずに実父による「認知調停申立」からスタートし「合意に代わる審判」によって認知を認める方法が広がることとなった。子の戸籍がまだ作成されていない段階では、民法772条により形式上推定される父の関与することなく父子関係を否定できる方法でもあるが、家裁の合意に代わる審判では、再び、前夫の意見も確認する手続きに戻っているようである。
|
 |
 |
|
|



